2014年09月30日
捨てずに活かそうネットワーク新着情報#14 カーテン生地等
高松市市民活動センターでは、
「捨てずに活かそうネットワーク」事業により、
などがもつ資源を市民活動団体等に提供する橋渡しをしています。
申込番号:#14
提供元:株式会社シンコール
提供内容:カーテン生地等
詳細:
カーテン生地、クッションフロア等の提供
募集団体:5団体 ※郷東町まで、直接取りに行くことの出来る団体に限る。
※郷東町まで、直接取りに行くことの出来る団体に限る。
※参加者は、1団体につき2名まで可。
※引取日は平成26年10月16日(木)10:00からで、当日参加できること。
締切:平成26年10月7日(火)
お申込みには、事前に「捨てずに活かそうネットワーク」への登録が必要です。登録には1週間程度かかります。
物件情報は、センターHP「ふらっと高松」http://www.flat-takamatsu.net/、
申込番号:#14
提供元:株式会社シンコール
提供内容:カーテン生地等
詳細:
カーテン生地、クッションフロア等の提供
募集団体:5団体
 ※郷東町まで、直接取りに行くことの出来る団体に限る。
※郷東町まで、直接取りに行くことの出来る団体に限る。※参加者は、1団体につき2名まで可。
※引取日は平成26年10月16日(木)10:00からで、当日参加できること。
締切:平成26年10月7日(火)
お申込みには、事前に「捨てずに活かそうネットワーク」への登録が必要です。登録には1週間程度かかります。
物件情報は、センターHP「ふらっと高松」http://www.flat-takamatsu.net/、
フェイスブックでもご覧いただけます。
タグ :すていか
2014年09月24日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」プレセミナー(第2回)
「プレセミナー(第2回)」が終了しました。
前回の開催場所は、高松港に近い高松城趾(玉藻公園被雲閣)、
今回の開催場所は、高松港から船に乗って小豆島へ。
高松港のフェリー乗り場に集まり、参加者の皆さんと土庄までフェリーで1時間。
そして、土庄港から一緒に歩いて会場へ。
この日、9月15日(月・祝)は、秋空でしたが日差しが強かった。
でも、会場はリノベーションされた、明治時代の「蔵」。涼しくて快適でした!

会場のMeiPAM(メイパム)
Meiro Performance Art Marche

人見コーディネータの進行で始まりました
では、当日の様子、
(1)講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
(2)プレゼンター(2人)のお話と、講師・会場とのセッション
(3)塾の紹介
の3つにわけてレポートします。
(1) 講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
尾野さん
埼玉県出身です。通販の古本屋をやっています。
2006年、人口3,700人の島根県のまちへ、本社をまるごと移転して活動しています。
この塾は、移住・定住とか、起業とか、そういうのにとらわれないで、いろんな立場の人が気軽に地域にたずさわる。
そんな方法があってもいいんじゃないかと始めた取り組みです。
今日はプレセミナーです。塾でどんなことをやるのか、少しでも感じ取ってもらえればと思います。
*
眞鍋さん
高松市出身です。高校を出て東京でいて、2年半前、「地域おこしを“なりわい”にしよう」と、Uターンじゃなく、ここ、小豆島へ移住しました。
地域資源を使って、何か新しいモノができないか。
ないものねだりではなく、あるもの探しをする。あるものを違うカタチで世に出して、収益が生まれるようにする。そういうことを、常日頃、考えています。
地域づくり。一歩、踏み出したいと思っている人、多いと思います。
その時、ハードルになっているのが、<1人じゃやり方がわからない>と<1人じゃ恥ずかしい>の二つだと感じています。
この塾で、仲間づくりができる。いろんなアイディアが出る中で、自分に近いモノを見つけていける。そんな場ができるよう、お手伝いできればと思っています。
*
眞鍋さん、「もっとしゃべりたいの、グッとガマンした」と笑われていましたが、
お2人には、かなり短時間でお話いただきました。
講師お2人の自己紹介、第1回プレセミナーのレポートでは省略してしまいましたので(~ごめんなさい)、今回、ほぼそのまま、紹介させていただきました。
(2)プレゼンター(2人)のお話
さて、本日のメイン、プレゼンターの登場です。
今回は、このお2人。
*小豆島出身、「醤油ソムリエ」* 黒島慶子さん
*横浜出身、本日の会場「MeiPAM」代表* 磯田周佑さん
人見コーディネータから、
「地元で、地域課題をとらえて活動されているお2人に話をいただきます」とのアナウンスを受けて、まずは、黒島さんから。
○「醤油ソムリエ」黒島さん

仲間から「ケリーちゃん」と呼ばれている、黒島さん
黒島さん
小豆島出身です。
「醤油ソムリエ」として、皆さんから声をかけていただいて活動しています。
「醤油ソムリエ」というのは自称です。結構“うさんくさい”肩書きだと思います。
眞鍋さん
“うさんくさい”って、自分で言っちゃった(笑)
〔醤油ソムリエの仕事〕
いきなり、小豆島の仲間、眞鍋さんから突っ込みがはいりました。
そんな黒島さんの仕事は、醤油の「作り手と使い手をつなぐ」こと。
*“情報発信”。旅館や飲食店に醤油をお薦めしたり、もちろん、雑誌やHPでも。
*“醤油ワークショップ”の開催。あちこちへ行って、醤油の選び方、使い方を知ってもらい、自分好みの醤油を探してもらう。
*その他、レシピ開発、メニュー開発などなど。
「作り手と使い手をつなぐためなら、何だってやります」と話される黒島さん、
活動を始められたのは、大学3回生の時だそうです。
〔キッカケは、芸大の卒業制作〕
絵が好きで、芸術系の大学へ進学し、アート漬けの生活を送っていた大学3回生の時、
これから社会へ出るというのに“このままで良いんだろうか”、悩まれたそうです。
~コレを創ったところでどうなるんだろう。社会に影響を与えてる実感がない。
~ただ、やりたいことをやってるだけ、何の価値もないものを創ってるんじゃないか。
そんなむなしさを感じるようになり、
卒業制作では、<社会の役に立つもの>、<私でないとできない作品>を創ろうと決められます。
〔小豆島と向き合う〕
自分が発想できるもの、表現できるもの、培ってきたもの、体験してきたもの…。
それは、私をつくってくれた小豆島。私のDNAとして根付いているだろう小豆島しかない。
それまで、島を出たい、都会へ行きたいと思っていたけど、
生まれてはじめて小豆島と向き合い、
そして、島の、いろんな人の話を聞きにまわり始めます。
〔小豆島、こんなところです〕
小豆島、結構、広いです。簡単にはまわれません。だから、知らないことも多いんです。
小豆島の産業は加工業が盛んです。
そうめんや醤油は400年前から。最近だと、オリーブや佃煮の加工。
農地が少ないし、水も足りないので、大豆や小麦といった素材が豊富なわけではなくて、
海運で運んできて、加工して、出す。そういう島です。
私は、小豆島の片隅、醤油蔵や佃煮屋さんが軒を連ねる「醤の郷」(ひしおのさと)で生まれ育ちました。
電信柱と同じように醤油蔵の桶があって、醤油の香りがしている「醤の郷」。
親戚にもご近所さんにも、醤油屋さんがいっぱいいます。
〔“醤油”でつなぐ〕
半年間、島のいろんな人の話を聞いてまわった。
楽しい。でも、ピンとこない。
そして、最後、
避けていた醤油蔵、親戚や知り合いが多いので避けていた醤油蔵へ向かいます。
小豆島の全蔵をまわった時、「あぁ、これだ」と思ったと話される黒島さん。
“蔵びと”と話しているとワクワクするんです。
今も、「醤油蔵でいる時が、一番元気だね」って言われます。
ネガティブな話も多いですけど、
醤油という産業を未来へつなげていく、作り手と使い手をつないでいく。
これを、一生の仕事にしようと決めました。
醤油を<選んで>使っている人、ほとんどいないと思うんです。
でも、少しでも知ってもらって、使ってもらえれば。
それが、島の子供たちのためにもなる。そんな想いでやっています。
*
プレゼンが終わると、すぐに、講師とのセッションが始まります。
眞鍋さん
前からケリーちゃんに聞きたかったんだけど、
「醤油ソムリエ」って、それまでなかった仕事じゃないですか。
最初、大変だったと思うんだけど、仕事になりだしたキッカケは何だったんですか。
黒島さん
自分でも、よく仕事が続いてると思いますけど(笑)
私、島に戻ってくるまでの6年間も、ずっと醤油の情報を発信してたんです。
学生時代は、「女子大生が“蔵びと”にはまっている」という記事を書き続け、
卒業後、島外で普通に就職してたんですけど、時間をつくって“蔵びと”を訪ね歩いて、毎月、“蔵びと情報”を出し続け、
勝手に「醤の郷のHP」をつくって、商工会へ「公式HPにしてください」ってお願いに行って。
そんなことしてたら、「なんか変な娘がいる」と面白がられるようになって、
“蔵びと取材”の仕事のオファーが来たりするようになって。
会社に勤めてたから、そんな仕事、受けられないんですけど、「戻ってこい」と言われだしたりして。
それで、島に戻ってきたら、「よく戻ってきた」と面白がって仕事をくれる人がいて。
そんな感じなので、キッカケというと、戻ってくるまでの、学生や会社勤めをやってた6年間でしょうか。
私、情報は持ってるけど、どこにも所属してないフリーランスで、商品すら持ってないんですよね。
だから、何にもとらわれずに動ける、個別の醤油をお薦めできる。
だから、素人が今もやれてるんだと思ってます。
尾野さん
「醤油ソムリエ」って、やりたいことを、誰にでも印象づけられるワンフレーズですよね。こういうフレーズ、大事だけど、つくるのはかなり難しいと思うんです。思いついた“いきさつ”を教えてください。
黒島さん
醤油ソムリエって“うさんくさい”でしょ(会場…笑)
自分で考えたんじゃないんです。周囲の人が呼ぶようになったんです。面白がって。
でも、呼ばれるようになっても、自分では名乗りませんでした。だって、あまりにもおこがましいじゃないですか。
もともと、私、ブログとかにも、自分の名前や顔を出してなかったんです。
オモテに出るのは“蔵びと”だけでいいと思っていて。
ところが、島に戻ってくると、名前が知られはじめて。
ちょうど、小豆島で、醤油サミットが開かれて、
全国のお醤油屋さんが集まるというので、行って、交流会に出て、こんなことやってますと自分がやってることを話して、
「まわりからは“醤油ソムリエ”と呼ばれています」と言ったら、
そこにいた全国のお醤油屋さんが「それ、面白い。名乗れ、名乗れ」、「名刺に“醤油ソムリエ”って書いとけ」、「ブログにも顔出せ」って言われて。
あ、はい、わかりましたと、急遽、名刺に書いて、ブログにも顔出して。
~いわゆる“悪のり”ってやつですね。(by尾野さん)
その後も、講師や会場とか質問が相次ぎましたが、省略させていただいて、
○続いて、「MeiPAM」代表 磯田さん

悪そうに見えるけど、見かけで判断しないように、
と、磯田さん
今日の会場、「MeiPAM」という美術館とカフェを、迷路の街「土庄町」でやっています。
MeiPAMのビジョンは「この街ににぎわいを取り戻す」です。
私は、横浜で生まれ・育ち、2013年4月に小豆島へ移住して来ました。
と話し始められました。
〔競争して大企業へ〕
いわゆる団塊ジュニアの世代。
同世代が多いので、大学進学も、就職も、競争が激しかった時代。
そして、大きな会社に入れば良いという時代。
そんな中、大企業に就職され、ロンドンへ留学、帰国後は会社のメイン部署で働き、
30歳前半で大きなプロジェクトを任されます。
〔何とかしようとMBAへ〕
ところが、失敗。会社に大きな損失を与えてしまったそうです。
落ち込んで、改めて社内を見渡すと、同世代はいっぱいいるし、上もいっぱいいる。
こんな中でやっていかないといけないのか。
人間関係でもつまずいて、このまま働いても、難しいかなと思うようになっていた時、
同期がMBAを取ったというのを聞き、自分も取ろうと、週末、大学へ通い始められます。
〔君は、東京ではコモディティだ〕
MBAで、一つの会社だけで働いていること、なんて意味のないことかと知りました。
その会社で偉くなるためのスキルしか学んでない。
財務諸表も読めないのに、プロジェクトリーダーになって意気揚々としてたし、
浅い仕事しかしてないと痛感しました。
そんなある日、出会った教授に言われたそうです。
「君みたいなのは、東京にはイッパイいる。
そういうの、コモディティって言うんだ。君は、東京ではコモディティだよ」
ガクゼンとしたそうです。そりゃそうでしょうね。
その教授は続けて、
「君は、でかい会社ではやっていけないよ。人間関係とか使いこなせないでしょ。
君みたいなピュアなタイプは、地域へ行きなさい」と。
競争に勝とうとMBAの大学へ来てるのに、「君は地域が良いよ」と言われて…。
全く、飲み込めなかったそうです。

〔地域へ〕
でも、東京。確かに、オレみたいなのはイッパイいるんですよ。電車に乗って見渡すだけでもイッパイいる。
コイツらと競争してるのか。
自分の個性を伸ばすとかじゃなく、ただ、勝つために。
でも、それって、何か変じゃないか。
競争に勝つという気持ちでしか仕事ができなくなっている自分に気がついたそうです。
それで、改めて、地域。日本のあるエリアで起きている問題を考えてみると、
その問題は、将来、必ず、日本全国、東京でも起きる問題。
それを、自分の目で、目の当たりに見て、肌で感じる。
それって、最先端じゃないか。
そう気づいた時、自分の中で文脈がバチンと変わったそうです。
地域の方が良い、地域へ行こう。
〔日本のミニチュア、小豆島〕
そして、縁があって、小豆島に来られた磯田さん。
小豆島。さっき、ケリーちゃんも言ってたけど、加工業が盛んだし。
海、山があって、商業があって、街がある。
東京とかの人は、日本の原風景、農村ってイメージなんだろうけど、違う。
農業の島とかでなく、多様性がある島。まさに、日本の超ミニチュア。
ココで何かの問題解決に向かうことは、今後の日本、20年後の東京につながる。
〔軸〕
ケリーちゃんは「醤油、産業で人をつなぐ」という<軸>を見つけているけど、僕は、まだ、模索していて。
最近、3か月ぐらい前、これが軸になるかなと頭に置いてることは、「小豆島に仕事をつくる」ということ。
土庄高校で話をする機会があって、
高校生に、卒業後、どうするのかって聞いたら、9割が島から出ていくという。
驚いた。
人口減少対策だといって、「移住政策」が盛んにいわれてるけど、
移住って、すごいリスクです。そんな簡単にできるのか。
私は移住者だけど、サラリーマンです。
オリーブオイルの会社に勤めていて、仕事でMeiPAMをやってる。
私は、仕事と地域活性が一体化してるという、非常に恵まれた環境にいるけど、こんな人、ほとんどいないと思う。
移住政策よりも、高校生たちが、ここで学んで、ここで働ける。そういうシステムができないか。
MeiPAMがココにあって、空き家再生プロジェクトみたいなのをやっていて、近くに小学校や高校がある。
そういう場で、人がつながったり、感じたりできないか。
そんなことを軸に、5年10年やってみたいと思っています。
*
眞鍋さん
そうなんですよね。小豆島、高校が2つあって、去年だと、卒業生があわせて239人いて、でも、島に残る卒業生は1割もいない。
19歳で移住してくる人、まず、いないから、小豆島、人口3万人だけど、19歳は20人もいない。そんな状況なんですよ。
でも、高校を卒業して出て行くことが、必ずしも悪いことだとは思わないんですよね。
僕は、出て行かないようにしようというのではなく、
出て行くのは自由だけど、戻ってくる選択肢、働き場をつくることが必要なんじゃないかと思ってるんですが。
磯田さん
そのとおりだと思います。
説明不足だったんですが、気になってるのは、ネガティブに出て行く高校生なんです。
「親が言うから(出て行く)」、「どうせ、島ではやることないから(出て行く)」。
そこを何とかしたいと思ってます。
尾野さん
1年半前に移住してこられて、仕事というか“なりわい”としてMeiPAMとかをやってこられて、つい3か月前ぐらい前に、自分がやりたいことに気づいた。(そうです~磯田さん)
その間、どういう想いで暮らしていましたか。
磯田
東京の生活とのギャップは、すぐには埋まらなくて、体と考え方を慣らせるのに、猶予期間が必要でした。
振り返ると、オリーブの会社で仕事をする中で、小さい企業、地域の企業で働くということをゆっくり感じ取っていったんじゃないかと思います。
そして、見えてきた現実、思いと違ってたこととかが明らかになってきて、
それが一つずつ問題意識になって、
自分とからめた時に、どう解決できるのか。
それを、ここ3か月で考え始めた。そんな状況です。
(3)塾の紹介
最後に塾の紹介を。

尾野さんから塾を紹介
<会場>は、コンクリート禁止にしています。今回の蔵、MeiPAMのように、古くて良いモノを活かすということを意識してやっています。
<今年は全国8箇所>で開催します。東北が2箇所、石川県の七尾市、高松市、岡山県が津山市と笠岡市、そして、島根県が江津市と、最初、2011年に始めた雲南市です。
5回シリーズの講座では<毎回、マイプランを考えます>。そして、6回目に最終発表会をします。
マイプランを考えるために、枠がある資料をお配りしますので、枠に沿って、自分が考えていることを書いて埋めていきます。そして、発表してもらいます。
誰でも発表できます。発表できるよう、我々も全力でサポートします。皆さんの良い話を引き出します。
<毎回、前半は>、地域で活動している方のゲストプレゼンを聞きます。
<後半は>、グループワークとして、自分たちが考えているマイプランを話し、聞いてもらいます。
<夜は>、気楽に、話をしあいます。お酒を飲んで遅くまで話し合う地域もあれば、ノンアルコールでやっている地域もあります。
<視察>に行きます。やろうとしてることに参考になる人を紹介しますので、視察に行って視野を広げます。
<一番の特徴>は、塾が終了した後、起業しなくても良いということです。
起業しなくて良いのですが、4年ぐらいやっているので、これまでに<卒業した塾生の状況>がわかってきはじめました。
まず、10人塾生がいると、マイプランをそのまま実践し続ける方は、1人か2人です。
そのまま実践してはいないけど、マイプランを考えた結果、地域づくりにもっと関わっていきたいと、中間支援機関とか、別のカタチで地域づくりに携わる方が、2~3人でしょうか。
そのほかの方は、そのままですが、他の塾生の活動を手伝ったりして、ゆるく、つながっている人もいます。
今回の高松は1期目ですが、できれば、2期、3期と続いて、20~30人のゆるやかなつながりの輪ができていく。そういう場を見届けたいと思っています。
難易度でいうと、収益計算とかもやらない<簡単な入門編>です。
興味があれば、資金計画とかをやるガチンコの塾はたくさんありますので、紹介します。
<塾への参加方法>は、塾生になる以外に、単発で参加する一般聴講でも参加可能です。
お待ちしています。
尾野さんからの紹介後、人見さん、眞鍋さんからもコメントがありました。
人見さん
この講座は、「意味」を考える講座だと思っています。
意味がわかっていないと、カタチにとらわれがちです。カタチを整えようとします。
この場合の「カタチ」とは、法人格とか団体。
しかし、この講座は、意味をとことん考えます。
従って、終了後、そのまま活動している人は1~2割だけれど、残りの人は、中間支援機関に携わったり、ほかの人の活動を助けたり、自分なりに意味のある活動へと展開しているのだと思います。
自分なりの意味をとことん考える、そんな半年間だと思ってください。
眞鍋さん
今回、はじめて副塾長をやるので、ホットながらも、ちょっと客観的に塾の紹介を聞いてました。
創業セミナーってよくありますよね、商工会議所や会計事務所がよくやってるセミナー。
事業計画・モデルや資金計画をつくるのなら、そういうセミナーの方が優れているのかも知れないですけど、
この塾の特徴は、「近さ」なのかも知れないなと感じました。
まあ、講師だといいながら、2人ともハーフパンツを履いている時点で、近いんですけど(笑)
何でも聞けるのが良いんだと思います。
そして、何回も何回もマイプランを練って、プレゼンするっていうのは、各々が舞台に上がって、各々が当事者になるということ。まさに地域づくりと同じですよね。
そういう機会が用意されているのが、この塾の特徴のような気がします。
そういうところに飛び込んでみたい、仲間入りしたいと思う方は、ぜひ、参加されたら良いんじゃないかと思います。

終了後、大人気の眞鍋さん。
磯田さんに写真を撮ってもらってます。
そして、磯田さんに案内いただき、迷路のまち「土庄」の街歩きへ。
子供たちが元気いっぱい でした。


文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
前回の開催場所は、高松港に近い高松城趾(玉藻公園被雲閣)、
今回の開催場所は、高松港から船に乗って小豆島へ。
高松港のフェリー乗り場に集まり、参加者の皆さんと土庄までフェリーで1時間。
そして、土庄港から一緒に歩いて会場へ。
この日、9月15日(月・祝)は、秋空でしたが日差しが強かった。
でも、会場はリノベーションされた、明治時代の「蔵」。涼しくて快適でした!

会場のMeiPAM(メイパム)
Meiro Performance Art Marche

人見コーディネータの進行で始まりました
では、当日の様子、
(1)講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
(2)プレゼンター(2人)のお話と、講師・会場とのセッション
(3)塾の紹介
の3つにわけてレポートします。
(1) 講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
尾野さん
埼玉県出身です。通販の古本屋をやっています。
2006年、人口3,700人の島根県のまちへ、本社をまるごと移転して活動しています。
この塾は、移住・定住とか、起業とか、そういうのにとらわれないで、いろんな立場の人が気軽に地域にたずさわる。
そんな方法があってもいいんじゃないかと始めた取り組みです。
今日はプレセミナーです。塾でどんなことをやるのか、少しでも感じ取ってもらえればと思います。
*
眞鍋さん
高松市出身です。高校を出て東京でいて、2年半前、「地域おこしを“なりわい”にしよう」と、Uターンじゃなく、ここ、小豆島へ移住しました。
地域資源を使って、何か新しいモノができないか。
ないものねだりではなく、あるもの探しをする。あるものを違うカタチで世に出して、収益が生まれるようにする。そういうことを、常日頃、考えています。
地域づくり。一歩、踏み出したいと思っている人、多いと思います。
その時、ハードルになっているのが、<1人じゃやり方がわからない>と<1人じゃ恥ずかしい>の二つだと感じています。
この塾で、仲間づくりができる。いろんなアイディアが出る中で、自分に近いモノを見つけていける。そんな場ができるよう、お手伝いできればと思っています。
*
眞鍋さん、「もっとしゃべりたいの、グッとガマンした」と笑われていましたが、
お2人には、かなり短時間でお話いただきました。
講師お2人の自己紹介、第1回プレセミナーのレポートでは省略してしまいましたので(~ごめんなさい)、今回、ほぼそのまま、紹介させていただきました。
(2)プレゼンター(2人)のお話
さて、本日のメイン、プレゼンターの登場です。
今回は、このお2人。
*小豆島出身、「醤油ソムリエ」* 黒島慶子さん
*横浜出身、本日の会場「MeiPAM」代表* 磯田周佑さん
人見コーディネータから、
「地元で、地域課題をとらえて活動されているお2人に話をいただきます」とのアナウンスを受けて、まずは、黒島さんから。
○「醤油ソムリエ」黒島さん

仲間から「ケリーちゃん」と呼ばれている、黒島さん
黒島さん
小豆島出身です。
「醤油ソムリエ」として、皆さんから声をかけていただいて活動しています。
「醤油ソムリエ」というのは自称です。結構“うさんくさい”肩書きだと思います。
眞鍋さん
“うさんくさい”って、自分で言っちゃった(笑)
〔醤油ソムリエの仕事〕
いきなり、小豆島の仲間、眞鍋さんから突っ込みがはいりました。
そんな黒島さんの仕事は、醤油の「作り手と使い手をつなぐ」こと。
*“情報発信”。旅館や飲食店に醤油をお薦めしたり、もちろん、雑誌やHPでも。
*“醤油ワークショップ”の開催。あちこちへ行って、醤油の選び方、使い方を知ってもらい、自分好みの醤油を探してもらう。
*その他、レシピ開発、メニュー開発などなど。
「作り手と使い手をつなぐためなら、何だってやります」と話される黒島さん、
活動を始められたのは、大学3回生の時だそうです。
〔キッカケは、芸大の卒業制作〕
絵が好きで、芸術系の大学へ進学し、アート漬けの生活を送っていた大学3回生の時、
これから社会へ出るというのに“このままで良いんだろうか”、悩まれたそうです。
~コレを創ったところでどうなるんだろう。社会に影響を与えてる実感がない。
~ただ、やりたいことをやってるだけ、何の価値もないものを創ってるんじゃないか。
そんなむなしさを感じるようになり、
卒業制作では、<社会の役に立つもの>、<私でないとできない作品>を創ろうと決められます。
〔小豆島と向き合う〕
自分が発想できるもの、表現できるもの、培ってきたもの、体験してきたもの…。
それは、私をつくってくれた小豆島。私のDNAとして根付いているだろう小豆島しかない。
それまで、島を出たい、都会へ行きたいと思っていたけど、
生まれてはじめて小豆島と向き合い、
そして、島の、いろんな人の話を聞きにまわり始めます。
〔小豆島、こんなところです〕
小豆島、結構、広いです。簡単にはまわれません。だから、知らないことも多いんです。
小豆島の産業は加工業が盛んです。
そうめんや醤油は400年前から。最近だと、オリーブや佃煮の加工。
農地が少ないし、水も足りないので、大豆や小麦といった素材が豊富なわけではなくて、
海運で運んできて、加工して、出す。そういう島です。
私は、小豆島の片隅、醤油蔵や佃煮屋さんが軒を連ねる「醤の郷」(ひしおのさと)で生まれ育ちました。
電信柱と同じように醤油蔵の桶があって、醤油の香りがしている「醤の郷」。
親戚にもご近所さんにも、醤油屋さんがいっぱいいます。
〔“醤油”でつなぐ〕
半年間、島のいろんな人の話を聞いてまわった。
楽しい。でも、ピンとこない。
そして、最後、
避けていた醤油蔵、親戚や知り合いが多いので避けていた醤油蔵へ向かいます。
小豆島の全蔵をまわった時、「あぁ、これだ」と思ったと話される黒島さん。
“蔵びと”と話しているとワクワクするんです。
今も、「醤油蔵でいる時が、一番元気だね」って言われます。
ネガティブな話も多いですけど、
醤油という産業を未来へつなげていく、作り手と使い手をつないでいく。
これを、一生の仕事にしようと決めました。
醤油を<選んで>使っている人、ほとんどいないと思うんです。
でも、少しでも知ってもらって、使ってもらえれば。
それが、島の子供たちのためにもなる。そんな想いでやっています。
*
プレゼンが終わると、すぐに、講師とのセッションが始まります。
眞鍋さん
前からケリーちゃんに聞きたかったんだけど、
「醤油ソムリエ」って、それまでなかった仕事じゃないですか。
最初、大変だったと思うんだけど、仕事になりだしたキッカケは何だったんですか。
黒島さん
自分でも、よく仕事が続いてると思いますけど(笑)
私、島に戻ってくるまでの6年間も、ずっと醤油の情報を発信してたんです。
学生時代は、「女子大生が“蔵びと”にはまっている」という記事を書き続け、
卒業後、島外で普通に就職してたんですけど、時間をつくって“蔵びと”を訪ね歩いて、毎月、“蔵びと情報”を出し続け、
勝手に「醤の郷のHP」をつくって、商工会へ「公式HPにしてください」ってお願いに行って。
そんなことしてたら、「なんか変な娘がいる」と面白がられるようになって、
“蔵びと取材”の仕事のオファーが来たりするようになって。
会社に勤めてたから、そんな仕事、受けられないんですけど、「戻ってこい」と言われだしたりして。
それで、島に戻ってきたら、「よく戻ってきた」と面白がって仕事をくれる人がいて。
そんな感じなので、キッカケというと、戻ってくるまでの、学生や会社勤めをやってた6年間でしょうか。
私、情報は持ってるけど、どこにも所属してないフリーランスで、商品すら持ってないんですよね。
だから、何にもとらわれずに動ける、個別の醤油をお薦めできる。
だから、素人が今もやれてるんだと思ってます。
尾野さん
「醤油ソムリエ」って、やりたいことを、誰にでも印象づけられるワンフレーズですよね。こういうフレーズ、大事だけど、つくるのはかなり難しいと思うんです。思いついた“いきさつ”を教えてください。
黒島さん
醤油ソムリエって“うさんくさい”でしょ(会場…笑)
自分で考えたんじゃないんです。周囲の人が呼ぶようになったんです。面白がって。
でも、呼ばれるようになっても、自分では名乗りませんでした。だって、あまりにもおこがましいじゃないですか。
もともと、私、ブログとかにも、自分の名前や顔を出してなかったんです。
オモテに出るのは“蔵びと”だけでいいと思っていて。
ところが、島に戻ってくると、名前が知られはじめて。
ちょうど、小豆島で、醤油サミットが開かれて、
全国のお醤油屋さんが集まるというので、行って、交流会に出て、こんなことやってますと自分がやってることを話して、
「まわりからは“醤油ソムリエ”と呼ばれています」と言ったら、
そこにいた全国のお醤油屋さんが「それ、面白い。名乗れ、名乗れ」、「名刺に“醤油ソムリエ”って書いとけ」、「ブログにも顔出せ」って言われて。
あ、はい、わかりましたと、急遽、名刺に書いて、ブログにも顔出して。
~いわゆる“悪のり”ってやつですね。(by尾野さん)
その後も、講師や会場とか質問が相次ぎましたが、省略させていただいて、
○続いて、「MeiPAM」代表 磯田さん

悪そうに見えるけど、見かけで判断しないように、
と、磯田さん
今日の会場、「MeiPAM」という美術館とカフェを、迷路の街「土庄町」でやっています。
MeiPAMのビジョンは「この街ににぎわいを取り戻す」です。
私は、横浜で生まれ・育ち、2013年4月に小豆島へ移住して来ました。
と話し始められました。
〔競争して大企業へ〕
いわゆる団塊ジュニアの世代。
同世代が多いので、大学進学も、就職も、競争が激しかった時代。
そして、大きな会社に入れば良いという時代。
そんな中、大企業に就職され、ロンドンへ留学、帰国後は会社のメイン部署で働き、
30歳前半で大きなプロジェクトを任されます。
〔何とかしようとMBAへ〕
ところが、失敗。会社に大きな損失を与えてしまったそうです。
落ち込んで、改めて社内を見渡すと、同世代はいっぱいいるし、上もいっぱいいる。
こんな中でやっていかないといけないのか。
人間関係でもつまずいて、このまま働いても、難しいかなと思うようになっていた時、
同期がMBAを取ったというのを聞き、自分も取ろうと、週末、大学へ通い始められます。
〔君は、東京ではコモディティだ〕
MBAで、一つの会社だけで働いていること、なんて意味のないことかと知りました。
その会社で偉くなるためのスキルしか学んでない。
財務諸表も読めないのに、プロジェクトリーダーになって意気揚々としてたし、
浅い仕事しかしてないと痛感しました。
そんなある日、出会った教授に言われたそうです。
「君みたいなのは、東京にはイッパイいる。
そういうの、コモディティって言うんだ。君は、東京ではコモディティだよ」
ガクゼンとしたそうです。そりゃそうでしょうね。
その教授は続けて、
「君は、でかい会社ではやっていけないよ。人間関係とか使いこなせないでしょ。
君みたいなピュアなタイプは、地域へ行きなさい」と。
競争に勝とうとMBAの大学へ来てるのに、「君は地域が良いよ」と言われて…。
全く、飲み込めなかったそうです。

〔地域へ〕
でも、東京。確かに、オレみたいなのはイッパイいるんですよ。電車に乗って見渡すだけでもイッパイいる。
コイツらと競争してるのか。
自分の個性を伸ばすとかじゃなく、ただ、勝つために。
でも、それって、何か変じゃないか。
競争に勝つという気持ちでしか仕事ができなくなっている自分に気がついたそうです。
それで、改めて、地域。日本のあるエリアで起きている問題を考えてみると、
その問題は、将来、必ず、日本全国、東京でも起きる問題。
それを、自分の目で、目の当たりに見て、肌で感じる。
それって、最先端じゃないか。
そう気づいた時、自分の中で文脈がバチンと変わったそうです。
地域の方が良い、地域へ行こう。
〔日本のミニチュア、小豆島〕
そして、縁があって、小豆島に来られた磯田さん。
小豆島。さっき、ケリーちゃんも言ってたけど、加工業が盛んだし。
海、山があって、商業があって、街がある。
東京とかの人は、日本の原風景、農村ってイメージなんだろうけど、違う。
農業の島とかでなく、多様性がある島。まさに、日本の超ミニチュア。
ココで何かの問題解決に向かうことは、今後の日本、20年後の東京につながる。
〔軸〕
ケリーちゃんは「醤油、産業で人をつなぐ」という<軸>を見つけているけど、僕は、まだ、模索していて。
最近、3か月ぐらい前、これが軸になるかなと頭に置いてることは、「小豆島に仕事をつくる」ということ。
土庄高校で話をする機会があって、
高校生に、卒業後、どうするのかって聞いたら、9割が島から出ていくという。
驚いた。
人口減少対策だといって、「移住政策」が盛んにいわれてるけど、
移住って、すごいリスクです。そんな簡単にできるのか。
私は移住者だけど、サラリーマンです。
オリーブオイルの会社に勤めていて、仕事でMeiPAMをやってる。
私は、仕事と地域活性が一体化してるという、非常に恵まれた環境にいるけど、こんな人、ほとんどいないと思う。
移住政策よりも、高校生たちが、ここで学んで、ここで働ける。そういうシステムができないか。
MeiPAMがココにあって、空き家再生プロジェクトみたいなのをやっていて、近くに小学校や高校がある。
そういう場で、人がつながったり、感じたりできないか。
そんなことを軸に、5年10年やってみたいと思っています。
*
眞鍋さん
そうなんですよね。小豆島、高校が2つあって、去年だと、卒業生があわせて239人いて、でも、島に残る卒業生は1割もいない。
19歳で移住してくる人、まず、いないから、小豆島、人口3万人だけど、19歳は20人もいない。そんな状況なんですよ。
でも、高校を卒業して出て行くことが、必ずしも悪いことだとは思わないんですよね。
僕は、出て行かないようにしようというのではなく、
出て行くのは自由だけど、戻ってくる選択肢、働き場をつくることが必要なんじゃないかと思ってるんですが。
磯田さん
そのとおりだと思います。
説明不足だったんですが、気になってるのは、ネガティブに出て行く高校生なんです。
「親が言うから(出て行く)」、「どうせ、島ではやることないから(出て行く)」。
そこを何とかしたいと思ってます。
尾野さん
1年半前に移住してこられて、仕事というか“なりわい”としてMeiPAMとかをやってこられて、つい3か月前ぐらい前に、自分がやりたいことに気づいた。(そうです~磯田さん)
その間、どういう想いで暮らしていましたか。
磯田
東京の生活とのギャップは、すぐには埋まらなくて、体と考え方を慣らせるのに、猶予期間が必要でした。
振り返ると、オリーブの会社で仕事をする中で、小さい企業、地域の企業で働くということをゆっくり感じ取っていったんじゃないかと思います。
そして、見えてきた現実、思いと違ってたこととかが明らかになってきて、
それが一つずつ問題意識になって、
自分とからめた時に、どう解決できるのか。
それを、ここ3か月で考え始めた。そんな状況です。
(3)塾の紹介
最後に塾の紹介を。

尾野さんから塾を紹介
<会場>は、コンクリート禁止にしています。今回の蔵、MeiPAMのように、古くて良いモノを活かすということを意識してやっています。
<今年は全国8箇所>で開催します。東北が2箇所、石川県の七尾市、高松市、岡山県が津山市と笠岡市、そして、島根県が江津市と、最初、2011年に始めた雲南市です。
5回シリーズの講座では<毎回、マイプランを考えます>。そして、6回目に最終発表会をします。
マイプランを考えるために、枠がある資料をお配りしますので、枠に沿って、自分が考えていることを書いて埋めていきます。そして、発表してもらいます。
誰でも発表できます。発表できるよう、我々も全力でサポートします。皆さんの良い話を引き出します。
<毎回、前半は>、地域で活動している方のゲストプレゼンを聞きます。
<後半は>、グループワークとして、自分たちが考えているマイプランを話し、聞いてもらいます。
<夜は>、気楽に、話をしあいます。お酒を飲んで遅くまで話し合う地域もあれば、ノンアルコールでやっている地域もあります。
<視察>に行きます。やろうとしてることに参考になる人を紹介しますので、視察に行って視野を広げます。
<一番の特徴>は、塾が終了した後、起業しなくても良いということです。
起業しなくて良いのですが、4年ぐらいやっているので、これまでに<卒業した塾生の状況>がわかってきはじめました。
まず、10人塾生がいると、マイプランをそのまま実践し続ける方は、1人か2人です。
そのまま実践してはいないけど、マイプランを考えた結果、地域づくりにもっと関わっていきたいと、中間支援機関とか、別のカタチで地域づくりに携わる方が、2~3人でしょうか。
そのほかの方は、そのままですが、他の塾生の活動を手伝ったりして、ゆるく、つながっている人もいます。
今回の高松は1期目ですが、できれば、2期、3期と続いて、20~30人のゆるやかなつながりの輪ができていく。そういう場を見届けたいと思っています。
難易度でいうと、収益計算とかもやらない<簡単な入門編>です。
興味があれば、資金計画とかをやるガチンコの塾はたくさんありますので、紹介します。
<塾への参加方法>は、塾生になる以外に、単発で参加する一般聴講でも参加可能です。
お待ちしています。
尾野さんからの紹介後、人見さん、眞鍋さんからもコメントがありました。
人見さん
この講座は、「意味」を考える講座だと思っています。
意味がわかっていないと、カタチにとらわれがちです。カタチを整えようとします。
この場合の「カタチ」とは、法人格とか団体。
しかし、この講座は、意味をとことん考えます。
従って、終了後、そのまま活動している人は1~2割だけれど、残りの人は、中間支援機関に携わったり、ほかの人の活動を助けたり、自分なりに意味のある活動へと展開しているのだと思います。
自分なりの意味をとことん考える、そんな半年間だと思ってください。
眞鍋さん
今回、はじめて副塾長をやるので、ホットながらも、ちょっと客観的に塾の紹介を聞いてました。
創業セミナーってよくありますよね、商工会議所や会計事務所がよくやってるセミナー。
事業計画・モデルや資金計画をつくるのなら、そういうセミナーの方が優れているのかも知れないですけど、
この塾の特徴は、「近さ」なのかも知れないなと感じました。
まあ、講師だといいながら、2人ともハーフパンツを履いている時点で、近いんですけど(笑)
何でも聞けるのが良いんだと思います。
そして、何回も何回もマイプランを練って、プレゼンするっていうのは、各々が舞台に上がって、各々が当事者になるということ。まさに地域づくりと同じですよね。
そういう機会が用意されているのが、この塾の特徴のような気がします。
そういうところに飛び込んでみたい、仲間入りしたいと思う方は、ぜひ、参加されたら良いんじゃないかと思います。

終了後、大人気の眞鍋さん。
磯田さんに写真を撮ってもらってます。
そして、磯田さんに案内いただき、迷路のまち「土庄」の街歩きへ。
子供たちが元気いっぱい でした。


文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
2014年09月06日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」プレセミナー(第1回)
動きだしました、「地域づくりチャレンジ塾」。
「本講座」は2014年10月11日からの半年間・6回ですが、
「本講座」に先立ち、こんなんしますよという、お披露目の「プレセミナー」を2回やる予定になっていて、
今回、8月24日(日)は、その第1回目。
まさに、最初の一歩(半歩?)です。
会場はJR高松駅前。玉藻公園(高松城跡)の被雲閣(ひうんかく)。国の重要文化財。
この日も暑い夏日でしたが、中に入ると風がとおって気持ちいい。
(↑高松市 市民政策局の城下局長も、挨拶でそうおっしゃられていました)

被雲閣の玄関

玄関には会場の案内が
そして、始まるまではひどく暑かったのですが、途中で夕立のような雨が降って、
終了する頃は雨があがって涼しくなって…。
天候にも恵まれました。
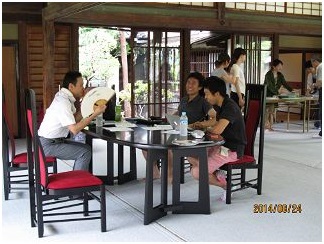
開会前。人見コーディネータ(左)と、<進行役>のお2人、尾野塾長(中)と眞鍋副塾長(右)とが打合せ

冒頭、城下局長からご挨拶を
まず、主催の高松市市民政策局長(城下正寿)より挨拶。
本市は「高松市自治基本条例」に掲げる「市民主体のまちづくり」を図るため、「高松市自治と協働の基本指針」を策定し、それぞれの地域の特性を生かしながら、多様な主体が参画・協働するまちづくりに取り組んでいる。
地域活動の重要性を理解し、地域の課題を解決できる人材の育成が、何より重要。
高松市市民活動センターでまちづくりのリーダー育成に努めるなか、一人でも多くの方が、このチャレンジ塾で学んだことを生かし、地域づくりに向けた、住民自らの実践活動のすそ野が広がっていくことを願っている。
続いて、共催の四国経済産業局産業部長(藤澤清隆)からも挨拶をいただいて。
今回の塾の前身は、島根県雲南市の幸雲南塾。今日、お越しいただいている尾野様が進められ、非常に好評で、全国に広がってきていると聞いている。その一つが高松市。
また、私ども経済産業省が関わっているスタンスは、新しい事業を興す、地域の課題をビジネスの手法で解決するという点。
だけれど、あまりビジネスという出口にとらわれず、気軽に参加いただいて、この塾の特徴、自分が何をやりたいかというところをしっかり固めて欲しい。そして、結果的にビジネスになれば良いし、ならなくても、何らかの気づきになれば、それで十分。
その後、セミナーへ。
まずは進行役のお2人(尾野塾長、眞鍋副塾長)が、ご自身がやられていること、これまでの経緯などを自己紹介。
※お2人のことは、本講座で詳しくご紹介する機会がありますので、今回は、省略(笑)
そして、本日のメイン。
お越しいただいた4人の方々、
地域課題にコミットメントしている皆さん、
無理しない範囲で楽しくやっておられる(と紹介された)4人の方々がご登壇。
ひとことづつ、自己紹介をいただきましたので、そのままご紹介。
~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原さん
~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~ エラリーさん
~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西さん
~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場さん
皆さん、高松市の方なんですが、やってる場所の説明が、
高松、国分寺、香川県、上之町(かみのちょう)と、全員、違ってたりします。

向かって左側が地元の4人、右側が進行役の2人
まず、進行役の方から今日の進め方について、
今日は、10分発表、10分我々(進行役の尾野さん、眞鍋さん)との質疑応答。これを繰り返します。
「本講座」も、こういうやり方です。皆さんに発表してもらい、我々とやりとりする。
これを毎回、繰り返しています。
今日は、「本講座」のグループワークを客席から見てもらえればと思います。
というガイダンスを受けて始まりましたプレセミナー。
ココでは、<お越しいただいた4人の方々のお話>を紹介させていただき、
最後に、尾野塾長が話された<塾の紹介>を書かせていただきます。
では、どうぞ。
<お越しいただいた4人の方々のお話>
(1)トップバッター ~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原あゆみさん。

上原さん。右手に持たれているのが「菓子木型」
〔お父様は「菓子木型」の職人〕
お父様は、「菓子木型」という、和三盆で「お干菓子(おひがし)」をつくる木型づくりの職人さん。四国で1人、全国でも6~7人だそうです。
〔普通に就職〕
でも、そんなことに関係なくすごされ、地元の短大を出て携帯電話会社に就職。当時は、短大→就職→結婚が当たり前だった時代。
その後、ケーキ屋さんで働くものの、お店が廃業。職安で見つけた直島のアートプロジェクトの2日間の仕事へ行き、そのまま、プロジェクトのスタッフに。
〔菓子木型ってスゴイ〕
それまでアートとは無縁だったそうですが、いろんなアート作品を見ているうち、ウチにいっぱいある菓子木型って、かなりアートじゃないか。
と、初めて菓子木型に興味を持ったそうです。
そんな頃、携帯電話のキャラクター「ドコモダケ」のイベントで、お父様がドコモダケの木型を彫って、東京でドコモダケ和三盆を振る舞うことに。
興味を持つようになっていたので、上原さんも一緒に行って…。
そして、菓子木型を使って干菓子をつくるところを、<初めて見た>そうです。
菓子木型はいつも見ていたけど、それを使っているところ、
菓子木型に、和三盆をキュッ、キュッと詰めて、ポンと出す。
キュッ、キュッ、ポン。何これ、スゴイ。感動。
〔これはみんなに知って欲しい〕
家に帰って、自分で菓子木型を使ってお干菓子をつくって、食べてみたら、
口の中でスーっと溶ける。
すごくおいしい。
“できたて”は全然違う。
これはみんなに知って欲しい。
小さい子とか、絶対に喜ぶ。
そして、「そんなん、ムダ」というお父様の反対を押し切って、体験教室を始められたそうです。
〔夢は〕
特に、地元の小学生に、体験して欲しい。知って欲しい。
高松は、お城があるおかげで、工芸品など良いものがいろいろある。
菓子木型を始め、良いものをいっぱい知って、
高松で生まれ育ったことを誇りに思ってもらえるようになって欲しい。そう思ってやっています。
*
と締めくくられた上原さん。
プレゼン後、進行役の方が言われたとおり、「上原さんの原体験、生き方、そして、自分がつくりたい世の中像」までが凝縮された10分間。
お手本のようなお話をいただきました。
(2)お2人目は、~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~
Helary Jean-Christophe さん。フランス出身の方です。

エラリーさん。10分間、正座で話されました。
〔剣道で日本へ〕
パリの近くで生まれたエラリーさん。
大学で出会った「剣道」がとても楽しくて、
剣道やるなら、いつか日本へ行かないといけない。そのためには、日本語を勉強しないと。
専攻を日本語に変えられ(親に内緒だったそう…)、92年、日本に来られました。
〔翻訳業がリーマンショックで、鬱に〕
日本では国際交流の仕事をやられていたそうですが、
組織での仕事がストレスになり、自分のスキルでできる“翻訳業”で独立。
ところが、2008年の秋。
リーマンショックの後、しばらく、仕事が全くなくなった。
子供が3人いるのに、どうしよう。悩んで、鬱病になってしまった そうです…。
〔ライフスタイルを変える〕
翻訳業といっても、下請けの下請けの下請け…。
どこかに頼っていたら振り回される。
自分と全く関係がないところの影響で、自分の仕事が切られて、終わりになる。
そんな生活じゃなく、地元を熱心に見て、その中で自分は何ができるか。
病院の先生に診てもらい、ライフスタイルを変えようと決心されます。
〔クレープ、アート、トラック〕
そして、PTA活動から知り合ったNPOが日曜日にやってる「さぬきマルシェ」に、趣味でクレープ屋さんを出店。
“クレープ”はフランスが発祥。父の出身地、ブルターニュ半島のお菓子。
国分寺の自宅でもクレープ・パーティをやっていた。子供たちとか集まると楽しいでしょ。
自分も子供の頃、人が集まると楽しかったからね。と話すエラリーさん。
次は、地元の国分寺でアート活動がやれないか、考えてるそうです。
高松市の「芸術士がいる保育所」、ああいうの。
お金にならなくても、人の縁が強くなって、そこから何か活動する人がでてきたりということはあるはず。公民館を借りたりしてね。
夢は、トラックの運転手。来月、普通免許を取りに行くことにした。
*
と、流ちょうな日本語で話されるエラリーさん。
「翻訳」と「クレープ」、そして次は、「アート」に「トラック運転手」。
全く違うテーマが出てきたのですが、
「“普段は翻訳、週末はクレープ”。そんな、本業あってのいろいろな週末活動が、これから、地域づくりの一つの主役になるのではないかと感じてます」という進行役の方のコメントに、なるほど。
そして、エラリーさんのクレープ。
お釣りが必要ないようにという、それだけの理由で“500円”。
その代わり500円の価値にするため、材料は香川県産に限定。砂糖は和三盆だし、
果物も自分がおいしいと思う生産者のところへ行って買って、自分でジャムをつくってるそう。
「500円の価値をだそうとしている、立派なビジネスですね」とのコメントが出ると、
「コストも手間もかかる。収入がないと自分が楽しくないので、収入がないならやりたくない。でも、私の中ではビジネスじゃない。趣味」と強調されるエラリーさん。
クレープをやってるのは、自分の原点に戻るため。
剣道も、自分の原点の一つ。
今、45歳になって、自分の子供たちに何を残すか、
地域の人たちに何を残すことができるかをすごく考えている。
ビジネスも考えないといけないけど、ビジネスとして何をするかというよりも、
地元で何ができるかを考えている。
そう語られたエラリーさん でした。
(3)続いては、~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西智都子さん

小西さん。こういう講座、いろいろ受講されたそうです。
〔お父様は郷土出版を〕
実家は印刷会社で、亡くなった父は、鄕土出版をしていた。
“讃岐のため池”とかっていう感じの本。本屋に置かれない本。図書館にしかない本。
子供だった私にとって全く面白くない本ばかりが家にあった。と話される小西さん。
〔地元愛は、全くなかった〕
関西の大学へ進学されますが、当時、地元愛は全くなかったそうで、
関西に残るつもりだったけど、卒業の3日後が、阪神・淡路大震災。
住む家がなくなり、やむなく地元へ戻ってきた。
だけど、落ち着いたら、また、関西へ行くつもりだった。
〔出版社をやりたい…〕
高松では、高松市の女性センターに勤めて、市民活動されてる方と出会ったり、
新聞社で生活情報誌の編集の仕事をしたり。
自分から望んだわけではないけど、地元情報に囲まれて生活。
その後、フリーランスでデザインや編集の仕事をしてる時、
お父様の仕事、“年配の方が自分史を出版する”仕事を手伝うことになります。
月に一回、その年配の方の家へ伺って、半日かけて話を聞き、
帰って原稿にまとめて、翌月、また、話を聞きに伺う、
それを1年やって1冊の本にする。
それまで扱っていた情報と違う、息の長い取材活動。
そういう経験をして、書籍をつくりたい。息長く残っていく書籍づくりをしたい。
そう思うようになったそうです。
でも、香川に、でそういう仕事をくれる出版社はない。
ないなら、自分でそういう出版社をつくりたい…。でも…。
〔できるはずがない〕
出版社に勤めたこともないし、やったこともない。
出版社なんて、できるはずがない。
だから、出版社をやりたいなんて、絶対、クチに出さなかった。
やりたいと思いながら、1人悩んで、今日のような講座に来ていたそうです。
〔やりたいと、人に話した〕
そんな中で出会った講座が転機になります。
その時の、グループ討議のテーマが、<あなたの課題は何ですか?>。
<あなたのやりたいこと>だったら、出版社をやりたいなんて絶対に言わなかったけど、
<あなたの課題>だったので、
「実は…。出版社をしたいんだけど、どうしたらいいかわからないんです」
〔出版社の立ち上げ〕
初めて人に話します。そしたら、一気に加速したそうです。
私、出版社をやりたいと思ってから立ち上げるまで、3~4年かかってるんですが、
人に話したあの講座から、1年足らずで出版社を立ち上げてしまいました。
振り返ったら、いろんな人にキッカケをもらいながらやってきたなぁと思います。
〔大変だけど、楽しい〕
今、「せとうち暮らし」という瀬戸内海の島の雑誌とかをつくってます。
島の取材って、行き来するだけでも時間がかかるし。
全て直販なので、本屋さん、雑貨屋さん、カフェとかへ行って、
こんな本をつくっているんです、置かせてくださいと言って、置かせてもらう。
今回の講座、<気軽に、ムリなく始める>ということですが、私にとっては、気軽じゃないし、ムリしまくり(笑)
でも、楽しいのは間違いないし、やり始めて後悔したことは一度もないですね。
〔目下の夢、宮島~直島をつなぐ〕
そして、お客さんや取材先の方とかが教えてくれるんです。
「せとうち暮らし」。最初は、香川県の有人島24島だけを取材してたんですけど、
しまなみ海道は? 宮島は?
県境なんて関係ないということに気づかせてもらって、取材先を広げはじめてます。
目下の夢は、<広島県の宮島から、香川県の直島までをつなげた観光ルート>をつくれないかということ。
瀬戸内海。全国の人に知って欲しいけど、外国の方にも知って欲しいんです。
まずは、外国の方に人気がある宮島と直島。これを瀬戸内海という海の道でつなぎたい。
すると、その間でいろんなことがおきるんじゃないか。
なぁんてね。たった4年でも、続けていると、こんな次の夢まで見つけてしまうんですね。
*
優しい語り口ですが、強い想いをお話していただいた小西さん。進行役の方から
「フリーペーパーを発行したいという人、結構、多いんですが、
最初、フリーペーパーから入るのでなく、いきなり独立というのはなぜなんですか?」
との質問に、
「亡き父が反面教師になってます」と言われます。
「父は『地元の良いものを残し、人に伝えるべきだ』と言い続けていました。
そして、父の遺言が『間違っても、本を売って儲けようと思うな』(笑)
でも、つくるだけでは届かないんです。
図書館にあっても、本屋とか身近なところになければ人の手に届かない。
届かないと始まらないんです。」
そして、もう一つ、付け加えていただきました。
「売り物にするかしないかで、作り方は大きく違います。
フリーペーパーは主導権が作り手側にあるので、自分たちが伝えたいことをカタチにして、分かってくれる人が分かってくれれば良い。
でも、売り物は主導権が買い手側にあるから、相手を振り向かせなければいけない。
コンテンツにそれだけの魅力が必要。
作り手にそれだけのレベルが必要なんです。
東京の出版社の方と話していると、東京と地方との情報格差って、作り手のレベルの差にもあるという話がよく出ます。
作り手が、せめぎ合いの中でもまれて、成長することが必要なんです。」
また、
「人に話すって大事ですよね。僕のまわりにも、自分1人で考えて、堂々巡りをしてる人は多いです」
とのコメントを受けて。
「本当にそうです。
自分の覚悟ができたし、人や情報は集まりだすし、
話すことで、自分の頭の中が整理できてブラッシュアップする。
逆に、あまりにもリアクションがない時は、練り直さないといけないと気づかせてくれます。
やったことないんだから、材料ないのが当たり前。
材料がないんだから、自分1人で考えていても、しょうがないんですよね。」
と応えていただきました。
(4)最後は、~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場加奈子さん

馬場さん。話すのが苦手と言われてましたが…。
〔陸上、結婚、出産、離婚〕
中学から大学までの10年間、砲丸投げと円盤投げをしていました。
高校3年の国体で優勝、大学では全国大学生選手権で優勝。
インターハイと国体で、香川県の旗手を務めさせていただきました。
これが、人生で最大の自慢。って、これしかないんですけど…。
そして、大学を卒業する時、実業団へは行かず、
<普通の女の子に戻りたい>と、エステで痩身して体重を半分にして。
OLして、結婚して、子供を産んで、離婚して。そして、今に至ります。
~と話し始められた馬場さん。ポツポツと話されますが、すごい です。
〔独立する〕
子供が3人いるので、働かないといけない。
長女が障害を持っているので、シングルマザーでも、自由に動ける状態でないといけない、
そのために、会社経営を学びたい。
そう思って、法人営業の仕事を探し、保険会社で働き始めました。
仕事で会社の社長さんたちに会えるから、会社経営の勉強ができると思って。
そして、給料をもらいながら学ばせてもらって4年経った時、
長女が養護学校へ入学することが決まったので、そろそろ独立しようと思いました。
〔制服のリユース事業〕
簡単にいえば、不要になった制服を買い取り、きれいにして、また、販売する事業。
昔は、隣近所で、お醤油を借り合ったりするのと同じように、制服のやりとりをしていたと思うんです。でも、今は、無くなってきてるんです。
子供の成長は喜ばしいけど、制服や体操着を買い換えると、結構な金額になります。
私、子供を3人抱えて離婚したので、家計のやりくりが大変でした。
当時、リサイクル店ができはじめていた頃だったので、
リサイクル店に、制服を取り扱って欲しいとお願いに行ったんです。
そしたら、良いですねとは言ってくれる。でも、やってくれない。
その翌年、長女が養護学校に入ることになったので、自分でやることにしました。
〔実店舗を持つ〕
最初は店舗を持たずにやってたんですが、利用してくれない。怪しまれたんです。
「学生服の中古品って、何、それ。なんか変なんじゃないか」。
半年たち、これは店舗がないと信用されないと思い、
今の店舗、コトデン「三条駅」の裏に、14坪の小さなお店を開設しました。
そしたら、お母さんの声が「怪しい」から「こんなお店が欲しかった」に変わって。
そして、お母さんの口コミが広がって、メディアの取材も増えて、
「さくらや」という名前が広がりだしました。
〔FCで展開〕
2年目になった時、「かがわ産業支援財団」からビジネスコンペに応募しないかと言われ、応募しました。でも、ビジネスプラン、書いたこともなかったので、1次審査で落ちました。
ところが、その翌年にも声をかけていただいたんです。
今度は、応募用紙に目一杯、思いの丈を書きこんだら、
一次審査どころか、なんと、最優秀賞になり、300万円の賞金をいただくことができたんです。
実は、お金があったら、やりたかったことがあったんです。それは、
<子育てしながら、お母さん1人で仕事ができるシステムをつくって、全国展開すること>。
それで、300万円をもとにPOSレジを開発して。
今年の3月、宇多津に、フランチャイズ1号店ができました。
〔夢〕
制服の洗濯は、クリーニング店だけでなく、障害者施設にも頼んでいます。
体操服のネームの刺繍取りは、地域のおばあちゃんに頼んでいます。
「さくらや」を通じて、地域の高齢者が交流して、お母さんの交流が広がって、
そして、障害者の方ができる仕事を増やしていきたいと思ってやっています。
*
「なんか、聞き入ってしまいました」と、進行役の方。
「“子育てとの両立”で心がけてることってありますか?」の問いかけに、
「店は、週4日、10~15時の短い営業にしています。
これ、子育てと両立してバランスをとるには必要なんです。
『なめとる』と言われることもあるけど、これは変えたくない。
実は、保険会社で法人営業していた時、仕事が楽しくて、夜も遅かったりして、
子育てを放り出してたこともあった。
会社勤めをやめたら、初めて、子供たちがいっぱい話しかけてきて。
その時、こんなに私と関わりたかったんだと気づいたんです。
子育ては限られた年数。これではダメだ。
本当に仕事と子育てが両立できるようにしないといけないと思いました。」
「最後に、これから何かを始めたい人へ、メッセージを。」
「まわりの人に、どんどん聞きに行けばいいと思います。
リユース事業の手続きでは、行政書士に頼むお金がもったいないので、警察の担当の方に何度も相談しましたし、
起業では、帳簿の付け方も何もわからないので、起業してる人にいっぱい聞きに行きました。
今も聞きに行っています。」
「(会場に向かって)今回のプログラムにも、先進事例のインタビューというのがあります。
どんな事業でも、似たような先進事例は必ずあります。聞きに行くことで得るものはたくさんあると思います。」
「そろそろ、休憩しましょう。」
<休 憩>
いやぁ、事務方の身でこんなこと言うのもなんですが、かなり濃い内容でした。
休憩後は、会場を含めた全員でのやりとりもあり、<面白い話>もあったんですが、
そこはちょっとだけの紹介にさせていただき、
最後、進行役、尾野塾長が話された<塾の紹介>を記して終わりにします。
<面白い話>、ちょっとだけの紹介
*尾野さんが、近所の人から夜逃げしてると思われていた話。
*眞鍋さんが、ニューヨークへ行く飛行機が発つ時、なぜか、太平洋沖でカツオ漁船に乗っていた話。
*上原さんの、和三盆がアメリカの税関で麻薬と間違われ、没収された話。
などなど…。
では、塾の紹介を。


<塾の紹介>(尾野塾長から)
仕事と自分がやりたいこと、両方できる 良い時代になってるなぁと思います。
大きな変革をおこすのは大変ですが、今日の皆さんも、小さな変革を確実におこしています。
昔、まちづくりをする人は、政治家、郵便局長、自治会長とかでした。
でも、今は、何でもない個人がスポットライトを浴びるようになっています。
子育てママ、サラリーマン、平日は別のフリーの仕事をしている人、
そんな人が気軽に街に関わる。
そんな人が束になってかかる。
そんな場をつくるのが、今回の塾です。
そして、この塾の最大の特徴は、<起業しなくて良い起業塾>。
半年間受講した後、行動しなくても良いです。
半年間、考えに考え、そして、半年後、“やっぱり違うな”と気づく。
そういう気づきをする人も少なくない。
だから、ムリして行動する必要はないです。
でも、“違うなと気づく”ことで、次のことを考えやすかったりするから、これも大事。
そして、収益計算もしません。
そんな場です。
前身になっている島根県雲南市の塾の卒業生には、郵便局員もいます。
昼間は郵便局員をやっていて、週末、地元の伝統産業を訪ねてつなげ、明宝探訪というスタンプラリーを始めた人もいます。
酒蔵、刃物…。これらの役場の担当は違っていたんですが、彼がスタンプラリーを始めたことで、役場の担当部署の壁がなくなってしまった。
受講している方、雲南市は、平均すると28歳なんですが、学生から58歳までいます。
会社勤め3割、子育てママ2割、仕事探し系・学生2割、後継者や独立・創業希望者2割。
そんな傾向です。
では、お時間がある方、輪になって、交流会にしましょう。


交流会。最初、全員で自己紹介(写真上)、その後は思い思いに(写真下)。
文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
「本講座」は2014年10月11日からの半年間・6回ですが、
「本講座」に先立ち、こんなんしますよという、お披露目の「プレセミナー」を2回やる予定になっていて、
今回、8月24日(日)は、その第1回目。
まさに、最初の一歩(半歩?)です。
会場はJR高松駅前。玉藻公園(高松城跡)の被雲閣(ひうんかく)。国の重要文化財。
この日も暑い夏日でしたが、中に入ると風がとおって気持ちいい。
(↑高松市 市民政策局の城下局長も、挨拶でそうおっしゃられていました)

被雲閣の玄関

玄関には会場の案内が
そして、始まるまではひどく暑かったのですが、途中で夕立のような雨が降って、
終了する頃は雨があがって涼しくなって…。
天候にも恵まれました。
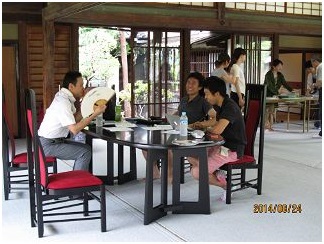
開会前。人見コーディネータ(左)と、<進行役>のお2人、尾野塾長(中)と眞鍋副塾長(右)とが打合せ

冒頭、城下局長からご挨拶を
まず、主催の高松市市民政策局長(城下正寿)より挨拶。
本市は「高松市自治基本条例」に掲げる「市民主体のまちづくり」を図るため、「高松市自治と協働の基本指針」を策定し、それぞれの地域の特性を生かしながら、多様な主体が参画・協働するまちづくりに取り組んでいる。
地域活動の重要性を理解し、地域の課題を解決できる人材の育成が、何より重要。
高松市市民活動センターでまちづくりのリーダー育成に努めるなか、一人でも多くの方が、このチャレンジ塾で学んだことを生かし、地域づくりに向けた、住民自らの実践活動のすそ野が広がっていくことを願っている。
続いて、共催の四国経済産業局産業部長(藤澤清隆)からも挨拶をいただいて。
今回の塾の前身は、島根県雲南市の幸雲南塾。今日、お越しいただいている尾野様が進められ、非常に好評で、全国に広がってきていると聞いている。その一つが高松市。
また、私ども経済産業省が関わっているスタンスは、新しい事業を興す、地域の課題をビジネスの手法で解決するという点。
だけれど、あまりビジネスという出口にとらわれず、気軽に参加いただいて、この塾の特徴、自分が何をやりたいかというところをしっかり固めて欲しい。そして、結果的にビジネスになれば良いし、ならなくても、何らかの気づきになれば、それで十分。
その後、セミナーへ。
まずは進行役のお2人(尾野塾長、眞鍋副塾長)が、ご自身がやられていること、これまでの経緯などを自己紹介。
※お2人のことは、本講座で詳しくご紹介する機会がありますので、今回は、省略(笑)
そして、本日のメイン。
お越しいただいた4人の方々、
地域課題にコミットメントしている皆さん、
無理しない範囲で楽しくやっておられる(と紹介された)4人の方々がご登壇。
ひとことづつ、自己紹介をいただきましたので、そのままご紹介。
~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原さん
~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~ エラリーさん
~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西さん
~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場さん
皆さん、高松市の方なんですが、やってる場所の説明が、
高松、国分寺、香川県、上之町(かみのちょう)と、全員、違ってたりします。

向かって左側が地元の4人、右側が進行役の2人
まず、進行役の方から今日の進め方について、
今日は、10分発表、10分我々(進行役の尾野さん、眞鍋さん)との質疑応答。これを繰り返します。
「本講座」も、こういうやり方です。皆さんに発表してもらい、我々とやりとりする。
これを毎回、繰り返しています。
今日は、「本講座」のグループワークを客席から見てもらえればと思います。
というガイダンスを受けて始まりましたプレセミナー。
ココでは、<お越しいただいた4人の方々のお話>を紹介させていただき、
最後に、尾野塾長が話された<塾の紹介>を書かせていただきます。
では、どうぞ。
<お越しいただいた4人の方々のお話>
(1)トップバッター ~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原あゆみさん。

上原さん。右手に持たれているのが「菓子木型」
〔お父様は「菓子木型」の職人〕
お父様は、「菓子木型」という、和三盆で「お干菓子(おひがし)」をつくる木型づくりの職人さん。四国で1人、全国でも6~7人だそうです。
〔普通に就職〕
でも、そんなことに関係なくすごされ、地元の短大を出て携帯電話会社に就職。当時は、短大→就職→結婚が当たり前だった時代。
その後、ケーキ屋さんで働くものの、お店が廃業。職安で見つけた直島のアートプロジェクトの2日間の仕事へ行き、そのまま、プロジェクトのスタッフに。
〔菓子木型ってスゴイ〕
それまでアートとは無縁だったそうですが、いろんなアート作品を見ているうち、ウチにいっぱいある菓子木型って、かなりアートじゃないか。
と、初めて菓子木型に興味を持ったそうです。
そんな頃、携帯電話のキャラクター「ドコモダケ」のイベントで、お父様がドコモダケの木型を彫って、東京でドコモダケ和三盆を振る舞うことに。
興味を持つようになっていたので、上原さんも一緒に行って…。
そして、菓子木型を使って干菓子をつくるところを、<初めて見た>そうです。
菓子木型はいつも見ていたけど、それを使っているところ、
菓子木型に、和三盆をキュッ、キュッと詰めて、ポンと出す。
キュッ、キュッ、ポン。何これ、スゴイ。感動。
〔これはみんなに知って欲しい〕
家に帰って、自分で菓子木型を使ってお干菓子をつくって、食べてみたら、
口の中でスーっと溶ける。
すごくおいしい。
“できたて”は全然違う。
これはみんなに知って欲しい。
小さい子とか、絶対に喜ぶ。
そして、「そんなん、ムダ」というお父様の反対を押し切って、体験教室を始められたそうです。
〔夢は〕
特に、地元の小学生に、体験して欲しい。知って欲しい。
高松は、お城があるおかげで、工芸品など良いものがいろいろある。
菓子木型を始め、良いものをいっぱい知って、
高松で生まれ育ったことを誇りに思ってもらえるようになって欲しい。そう思ってやっています。
*
と締めくくられた上原さん。
プレゼン後、進行役の方が言われたとおり、「上原さんの原体験、生き方、そして、自分がつくりたい世の中像」までが凝縮された10分間。
お手本のようなお話をいただきました。
(2)お2人目は、~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~
Helary Jean-Christophe さん。フランス出身の方です。

エラリーさん。10分間、正座で話されました。
〔剣道で日本へ〕
パリの近くで生まれたエラリーさん。
大学で出会った「剣道」がとても楽しくて、
剣道やるなら、いつか日本へ行かないといけない。そのためには、日本語を勉強しないと。
専攻を日本語に変えられ(親に内緒だったそう…)、92年、日本に来られました。
〔翻訳業がリーマンショックで、鬱に〕
日本では国際交流の仕事をやられていたそうですが、
組織での仕事がストレスになり、自分のスキルでできる“翻訳業”で独立。
ところが、2008年の秋。
リーマンショックの後、しばらく、仕事が全くなくなった。
子供が3人いるのに、どうしよう。悩んで、鬱病になってしまった そうです…。
〔ライフスタイルを変える〕
翻訳業といっても、下請けの下請けの下請け…。
どこかに頼っていたら振り回される。
自分と全く関係がないところの影響で、自分の仕事が切られて、終わりになる。
そんな生活じゃなく、地元を熱心に見て、その中で自分は何ができるか。
病院の先生に診てもらい、ライフスタイルを変えようと決心されます。
〔クレープ、アート、トラック〕
そして、PTA活動から知り合ったNPOが日曜日にやってる「さぬきマルシェ」に、趣味でクレープ屋さんを出店。
“クレープ”はフランスが発祥。父の出身地、ブルターニュ半島のお菓子。
国分寺の自宅でもクレープ・パーティをやっていた。子供たちとか集まると楽しいでしょ。
自分も子供の頃、人が集まると楽しかったからね。と話すエラリーさん。
次は、地元の国分寺でアート活動がやれないか、考えてるそうです。
高松市の「芸術士がいる保育所」、ああいうの。
お金にならなくても、人の縁が強くなって、そこから何か活動する人がでてきたりということはあるはず。公民館を借りたりしてね。
夢は、トラックの運転手。来月、普通免許を取りに行くことにした。
*
と、流ちょうな日本語で話されるエラリーさん。
「翻訳」と「クレープ」、そして次は、「アート」に「トラック運転手」。
全く違うテーマが出てきたのですが、
「“普段は翻訳、週末はクレープ”。そんな、本業あってのいろいろな週末活動が、これから、地域づくりの一つの主役になるのではないかと感じてます」という進行役の方のコメントに、なるほど。
そして、エラリーさんのクレープ。
お釣りが必要ないようにという、それだけの理由で“500円”。
その代わり500円の価値にするため、材料は香川県産に限定。砂糖は和三盆だし、
果物も自分がおいしいと思う生産者のところへ行って買って、自分でジャムをつくってるそう。
「500円の価値をだそうとしている、立派なビジネスですね」とのコメントが出ると、
「コストも手間もかかる。収入がないと自分が楽しくないので、収入がないならやりたくない。でも、私の中ではビジネスじゃない。趣味」と強調されるエラリーさん。
クレープをやってるのは、自分の原点に戻るため。
剣道も、自分の原点の一つ。
今、45歳になって、自分の子供たちに何を残すか、
地域の人たちに何を残すことができるかをすごく考えている。
ビジネスも考えないといけないけど、ビジネスとして何をするかというよりも、
地元で何ができるかを考えている。
そう語られたエラリーさん でした。
(3)続いては、~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西智都子さん

小西さん。こういう講座、いろいろ受講されたそうです。
〔お父様は郷土出版を〕
実家は印刷会社で、亡くなった父は、鄕土出版をしていた。
“讃岐のため池”とかっていう感じの本。本屋に置かれない本。図書館にしかない本。
子供だった私にとって全く面白くない本ばかりが家にあった。と話される小西さん。
〔地元愛は、全くなかった〕
関西の大学へ進学されますが、当時、地元愛は全くなかったそうで、
関西に残るつもりだったけど、卒業の3日後が、阪神・淡路大震災。
住む家がなくなり、やむなく地元へ戻ってきた。
だけど、落ち着いたら、また、関西へ行くつもりだった。
〔出版社をやりたい…〕
高松では、高松市の女性センターに勤めて、市民活動されてる方と出会ったり、
新聞社で生活情報誌の編集の仕事をしたり。
自分から望んだわけではないけど、地元情報に囲まれて生活。
その後、フリーランスでデザインや編集の仕事をしてる時、
お父様の仕事、“年配の方が自分史を出版する”仕事を手伝うことになります。
月に一回、その年配の方の家へ伺って、半日かけて話を聞き、
帰って原稿にまとめて、翌月、また、話を聞きに伺う、
それを1年やって1冊の本にする。
それまで扱っていた情報と違う、息の長い取材活動。
そういう経験をして、書籍をつくりたい。息長く残っていく書籍づくりをしたい。
そう思うようになったそうです。
でも、香川に、でそういう仕事をくれる出版社はない。
ないなら、自分でそういう出版社をつくりたい…。でも…。
〔できるはずがない〕
出版社に勤めたこともないし、やったこともない。
出版社なんて、できるはずがない。
だから、出版社をやりたいなんて、絶対、クチに出さなかった。
やりたいと思いながら、1人悩んで、今日のような講座に来ていたそうです。
〔やりたいと、人に話した〕
そんな中で出会った講座が転機になります。
その時の、グループ討議のテーマが、<あなたの課題は何ですか?>。
<あなたのやりたいこと>だったら、出版社をやりたいなんて絶対に言わなかったけど、
<あなたの課題>だったので、
「実は…。出版社をしたいんだけど、どうしたらいいかわからないんです」
〔出版社の立ち上げ〕
初めて人に話します。そしたら、一気に加速したそうです。
私、出版社をやりたいと思ってから立ち上げるまで、3~4年かかってるんですが、
人に話したあの講座から、1年足らずで出版社を立ち上げてしまいました。
振り返ったら、いろんな人にキッカケをもらいながらやってきたなぁと思います。
〔大変だけど、楽しい〕
今、「せとうち暮らし」という瀬戸内海の島の雑誌とかをつくってます。
島の取材って、行き来するだけでも時間がかかるし。
全て直販なので、本屋さん、雑貨屋さん、カフェとかへ行って、
こんな本をつくっているんです、置かせてくださいと言って、置かせてもらう。
今回の講座、<気軽に、ムリなく始める>ということですが、私にとっては、気軽じゃないし、ムリしまくり(笑)
でも、楽しいのは間違いないし、やり始めて後悔したことは一度もないですね。
〔目下の夢、宮島~直島をつなぐ〕
そして、お客さんや取材先の方とかが教えてくれるんです。
「せとうち暮らし」。最初は、香川県の有人島24島だけを取材してたんですけど、
しまなみ海道は? 宮島は?
県境なんて関係ないということに気づかせてもらって、取材先を広げはじめてます。
目下の夢は、<広島県の宮島から、香川県の直島までをつなげた観光ルート>をつくれないかということ。
瀬戸内海。全国の人に知って欲しいけど、外国の方にも知って欲しいんです。
まずは、外国の方に人気がある宮島と直島。これを瀬戸内海という海の道でつなぎたい。
すると、その間でいろんなことがおきるんじゃないか。
なぁんてね。たった4年でも、続けていると、こんな次の夢まで見つけてしまうんですね。
*
優しい語り口ですが、強い想いをお話していただいた小西さん。進行役の方から
「フリーペーパーを発行したいという人、結構、多いんですが、
最初、フリーペーパーから入るのでなく、いきなり独立というのはなぜなんですか?」
との質問に、
「亡き父が反面教師になってます」と言われます。
「父は『地元の良いものを残し、人に伝えるべきだ』と言い続けていました。
そして、父の遺言が『間違っても、本を売って儲けようと思うな』(笑)
でも、つくるだけでは届かないんです。
図書館にあっても、本屋とか身近なところになければ人の手に届かない。
届かないと始まらないんです。」
そして、もう一つ、付け加えていただきました。
「売り物にするかしないかで、作り方は大きく違います。
フリーペーパーは主導権が作り手側にあるので、自分たちが伝えたいことをカタチにして、分かってくれる人が分かってくれれば良い。
でも、売り物は主導権が買い手側にあるから、相手を振り向かせなければいけない。
コンテンツにそれだけの魅力が必要。
作り手にそれだけのレベルが必要なんです。
東京の出版社の方と話していると、東京と地方との情報格差って、作り手のレベルの差にもあるという話がよく出ます。
作り手が、せめぎ合いの中でもまれて、成長することが必要なんです。」
また、
「人に話すって大事ですよね。僕のまわりにも、自分1人で考えて、堂々巡りをしてる人は多いです」
とのコメントを受けて。
「本当にそうです。
自分の覚悟ができたし、人や情報は集まりだすし、
話すことで、自分の頭の中が整理できてブラッシュアップする。
逆に、あまりにもリアクションがない時は、練り直さないといけないと気づかせてくれます。
やったことないんだから、材料ないのが当たり前。
材料がないんだから、自分1人で考えていても、しょうがないんですよね。」
と応えていただきました。
(4)最後は、~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場加奈子さん

馬場さん。話すのが苦手と言われてましたが…。
〔陸上、結婚、出産、離婚〕
中学から大学までの10年間、砲丸投げと円盤投げをしていました。
高校3年の国体で優勝、大学では全国大学生選手権で優勝。
インターハイと国体で、香川県の旗手を務めさせていただきました。
これが、人生で最大の自慢。って、これしかないんですけど…。
そして、大学を卒業する時、実業団へは行かず、
<普通の女の子に戻りたい>と、エステで痩身して体重を半分にして。
OLして、結婚して、子供を産んで、離婚して。そして、今に至ります。
~と話し始められた馬場さん。ポツポツと話されますが、すごい です。
〔独立する〕
子供が3人いるので、働かないといけない。
長女が障害を持っているので、シングルマザーでも、自由に動ける状態でないといけない、
そのために、会社経営を学びたい。
そう思って、法人営業の仕事を探し、保険会社で働き始めました。
仕事で会社の社長さんたちに会えるから、会社経営の勉強ができると思って。
そして、給料をもらいながら学ばせてもらって4年経った時、
長女が養護学校へ入学することが決まったので、そろそろ独立しようと思いました。
〔制服のリユース事業〕
簡単にいえば、不要になった制服を買い取り、きれいにして、また、販売する事業。
昔は、隣近所で、お醤油を借り合ったりするのと同じように、制服のやりとりをしていたと思うんです。でも、今は、無くなってきてるんです。
子供の成長は喜ばしいけど、制服や体操着を買い換えると、結構な金額になります。
私、子供を3人抱えて離婚したので、家計のやりくりが大変でした。
当時、リサイクル店ができはじめていた頃だったので、
リサイクル店に、制服を取り扱って欲しいとお願いに行ったんです。
そしたら、良いですねとは言ってくれる。でも、やってくれない。
その翌年、長女が養護学校に入ることになったので、自分でやることにしました。
〔実店舗を持つ〕
最初は店舗を持たずにやってたんですが、利用してくれない。怪しまれたんです。
「学生服の中古品って、何、それ。なんか変なんじゃないか」。
半年たち、これは店舗がないと信用されないと思い、
今の店舗、コトデン「三条駅」の裏に、14坪の小さなお店を開設しました。
そしたら、お母さんの声が「怪しい」から「こんなお店が欲しかった」に変わって。
そして、お母さんの口コミが広がって、メディアの取材も増えて、
「さくらや」という名前が広がりだしました。
〔FCで展開〕
2年目になった時、「かがわ産業支援財団」からビジネスコンペに応募しないかと言われ、応募しました。でも、ビジネスプラン、書いたこともなかったので、1次審査で落ちました。
ところが、その翌年にも声をかけていただいたんです。
今度は、応募用紙に目一杯、思いの丈を書きこんだら、
一次審査どころか、なんと、最優秀賞になり、300万円の賞金をいただくことができたんです。
実は、お金があったら、やりたかったことがあったんです。それは、
<子育てしながら、お母さん1人で仕事ができるシステムをつくって、全国展開すること>。
それで、300万円をもとにPOSレジを開発して。
今年の3月、宇多津に、フランチャイズ1号店ができました。
〔夢〕
制服の洗濯は、クリーニング店だけでなく、障害者施設にも頼んでいます。
体操服のネームの刺繍取りは、地域のおばあちゃんに頼んでいます。
「さくらや」を通じて、地域の高齢者が交流して、お母さんの交流が広がって、
そして、障害者の方ができる仕事を増やしていきたいと思ってやっています。
*
「なんか、聞き入ってしまいました」と、進行役の方。
「“子育てとの両立”で心がけてることってありますか?」の問いかけに、
「店は、週4日、10~15時の短い営業にしています。
これ、子育てと両立してバランスをとるには必要なんです。
『なめとる』と言われることもあるけど、これは変えたくない。
実は、保険会社で法人営業していた時、仕事が楽しくて、夜も遅かったりして、
子育てを放り出してたこともあった。
会社勤めをやめたら、初めて、子供たちがいっぱい話しかけてきて。
その時、こんなに私と関わりたかったんだと気づいたんです。
子育ては限られた年数。これではダメだ。
本当に仕事と子育てが両立できるようにしないといけないと思いました。」
「最後に、これから何かを始めたい人へ、メッセージを。」
「まわりの人に、どんどん聞きに行けばいいと思います。
リユース事業の手続きでは、行政書士に頼むお金がもったいないので、警察の担当の方に何度も相談しましたし、
起業では、帳簿の付け方も何もわからないので、起業してる人にいっぱい聞きに行きました。
今も聞きに行っています。」
「(会場に向かって)今回のプログラムにも、先進事例のインタビューというのがあります。
どんな事業でも、似たような先進事例は必ずあります。聞きに行くことで得るものはたくさんあると思います。」
「そろそろ、休憩しましょう。」
<休 憩>
いやぁ、事務方の身でこんなこと言うのもなんですが、かなり濃い内容でした。
休憩後は、会場を含めた全員でのやりとりもあり、<面白い話>もあったんですが、
そこはちょっとだけの紹介にさせていただき、
最後、進行役、尾野塾長が話された<塾の紹介>を記して終わりにします。
<面白い話>、ちょっとだけの紹介
*尾野さんが、近所の人から夜逃げしてると思われていた話。
*眞鍋さんが、ニューヨークへ行く飛行機が発つ時、なぜか、太平洋沖でカツオ漁船に乗っていた話。
*上原さんの、和三盆がアメリカの税関で麻薬と間違われ、没収された話。
などなど…。
では、塾の紹介を。


<塾の紹介>(尾野塾長から)
仕事と自分がやりたいこと、両方できる 良い時代になってるなぁと思います。
大きな変革をおこすのは大変ですが、今日の皆さんも、小さな変革を確実におこしています。
昔、まちづくりをする人は、政治家、郵便局長、自治会長とかでした。
でも、今は、何でもない個人がスポットライトを浴びるようになっています。
子育てママ、サラリーマン、平日は別のフリーの仕事をしている人、
そんな人が気軽に街に関わる。
そんな人が束になってかかる。
そんな場をつくるのが、今回の塾です。
そして、この塾の最大の特徴は、<起業しなくて良い起業塾>。
半年間受講した後、行動しなくても良いです。
半年間、考えに考え、そして、半年後、“やっぱり違うな”と気づく。
そういう気づきをする人も少なくない。
だから、ムリして行動する必要はないです。
でも、“違うなと気づく”ことで、次のことを考えやすかったりするから、これも大事。
そして、収益計算もしません。
そんな場です。
前身になっている島根県雲南市の塾の卒業生には、郵便局員もいます。
昼間は郵便局員をやっていて、週末、地元の伝統産業を訪ねてつなげ、明宝探訪というスタンプラリーを始めた人もいます。
酒蔵、刃物…。これらの役場の担当は違っていたんですが、彼がスタンプラリーを始めたことで、役場の担当部署の壁がなくなってしまった。
受講している方、雲南市は、平均すると28歳なんですが、学生から58歳までいます。
会社勤め3割、子育てママ2割、仕事探し系・学生2割、後継者や独立・創業希望者2割。
そんな傾向です。
では、お時間がある方、輪になって、交流会にしましょう。


交流会。最初、全員で自己紹介(写真上)、その後は思い思いに(写真下)。
文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)




