2017年03月21日
高松市まちづくり学校実行委員会 みんなの学縁祭
日時:平成29年3月18日(土)
場所:市民交流プラザIKODE瓦町アートステーション
市民活動センター(瓦町FLAG8階)
今回の学縁祭のスタートはアドバンスコースからの発表でした。コメンテータに松岡敬三氏(高松青年会議所)正岡利朗氏(高松大学経営学部)瑞田信仁氏(四国若者会議)を迎え、一般の聴講生は45名もの人が参加されました。
大勢の人の熱気と緊張感が漂っている中で最終報告会は開催され、コメンテータの方と塾生の質疑応答はまさに 上達コース ならではのものでした。
発表者、テーマは以下の通りです(番号は発表順)。↓↓
1.ぬくぬくママSUN’Sさん
『地域と子育て世代をつなぐ子育てエンターテインメント~ぬくぬくママSUN’S ~』
2.片山哲也さん 『まちの魅力を伝える「不動産屋」さんに』
3.地域の家ココカラハウスさん
『大学生が動く~夢と遊び心をトッピング★地域の居場所づくり~』
4.さをり織工房咲く屋さん 『新たなステージへ』
4団体の発表が終了後、参加していた全員が投票し発表者の方全員に修了証をお渡しした後、企画賞が発表され ぬくぬくママSUN‘S が受賞されました。



超少子高齢化を目前に、地域コミュニティ、市民活動、企業、組織の担い手不足の危機が迫っています。次世代にバトンを渡す方法を考える、世代を超えた対話の場を開催しました。約40名の参加があり、世代を超えた4グループに分かれ発表してもらいました。短時間で意見をまとめて発表までしてもらいましたが、各グループの発表に塾長は「こんな短時間で皆さんすごいです!!」と感嘆されていました。


高松市のコミュニティ事業、活動中のチャレンジ塾OBチーム、近県姉妹塾の取り組みを紹介しました。それぞれの活動を知り、関わる人に会いたくなる!それこそ地域活動のの第一歩です。アートステーションのギャラリーでは高松市の各コミュニティ協議会の展示があり16もの協議会に参加していただきました。御厩焼や各協議会の色とりどりのパネル展示に皆さん立ち止まって見入っておられました。アートステーション多目的スタジオでは、県外の須崎市・西条市から出張展示もあり、地域の家ココカラハウス・ぬくぬくママSUN’S・さくらや・さをり織工房 咲く屋などの地域づくりチャレンジ塾OBチームなど10団体が参加し活動を報告していました。


ワールドカフェの後はいよいよビギナーコースの報告会です。
発表者の皆さんからは一様に緊張感が伝わってきます。ビギナーコースはテーマもバラエティに富んでおり、個性が光るプレゼンが繰り広げられました。
それぞれの発表の後、コメンテーターや塾長からコメントがあり、そこで塾生と少しやりとりがあるのですが、「ビギナーのレベルで、塾生からここまで言葉が出てくるのは珍しい。しかも全員。今回は本当にレベルが高いです。」と塾長。そのなかでも、「今回のプレゼンは神が降りてきた!!」と塾長が唸った川原千鶴さんが、みごと企画賞を受賞されました。
聴講の方々もとても真剣に、熱心に耳を傾けられていて、会場が熱くひとつになった報告会でした。
発表者、テーマは以下の通りです(番号は発表順)。↓↓
1.石塚めぐみ 『困っている人を見かけたら、自然と手を差しのべれる人が増える社会を目指したい』
2.福井瑞穂 『LGBT』
3.松本武司 『年齢を重ねることが楽しみになる 新しいセルフケアのご提案』
4.山本龍太郎 『エンタメ×ワークショップ=「夢中」』
5.上原千鶴 『お片付けでまるごとつなぐ プロジェクト』
6.斉藤 修 『海プロジェクトin高松』
報告会の後、塾生一人ひとりに塾長より修了証が手渡され、皆さん達成感いっぱいの表情で受け取っていらっしゃいました。そして最後に、塾生の皆さんからサプライズで塾長へ花束が‼



ビギナーコース報告会の後は、市民活動センター会議室に場所を移して、さぬき映画祭2017優秀企画上映作品である映画「Lemon&Letter」の上映会です。
舞台となった男木島の美しさに何度もはっとさせられた映画でした。上映終了後のアフタートークには、企画・脚本・監督を手掛けた梅木佳子さんと、出演された女優の木内晶子さん、子役の大林 嵩季くん、小林 碧さんも登場してくださり、オーディションについてやロケの苦労話などいろいろな裏話を聞くことができました。


その後、ふたたびアートステーション多目的スタジオに移っての交流会です。
学縁祭のスタートからかなり長い時間が経っていましたが、出席された皆さんはまだまだ熱く語り合っていらっしゃいました。


場所:市民交流プラザIKODE瓦町アートステーション
市民活動センター(瓦町FLAG8階)
《最終報告会》地域づくりチャレンジ塾2016 アドバンスコース
今回の学縁祭のスタートはアドバンスコースからの発表でした。コメンテータに松岡敬三氏(高松青年会議所)正岡利朗氏(高松大学経営学部)瑞田信仁氏(四国若者会議)を迎え、一般の聴講生は45名もの人が参加されました。
大勢の人の熱気と緊張感が漂っている中で最終報告会は開催され、コメンテータの方と塾生の質疑応答はまさに 上達コース ならではのものでした。
発表者、テーマは以下の通りです(番号は発表順)。↓↓
1.ぬくぬくママSUN’Sさん
『地域と子育て世代をつなぐ子育てエンターテインメント~ぬくぬくママSUN’S ~』
2.片山哲也さん 『まちの魅力を伝える「不動産屋」さんに』
3.地域の家ココカラハウスさん
『大学生が動く~夢と遊び心をトッピング★地域の居場所づくり~』
4.さをり織工房咲く屋さん 『新たなステージへ』
4団体の発表が終了後、参加していた全員が投票し発表者の方全員に修了証をお渡しした後、企画賞が発表され ぬくぬくママSUN‘S が受賞されました。
《ワールドカフェ》テーマ『次世代担い手にバトンをつなぐ方法!』
超少子高齢化を目前に、地域コミュニティ、市民活動、企業、組織の担い手不足の危機が迫っています。次世代にバトンを渡す方法を考える、世代を超えた対話の場を開催しました。約40名の参加があり、世代を超えた4グループに分かれ発表してもらいました。短時間で意見をまとめて発表までしてもらいましたが、各グループの発表に塾長は「こんな短時間で皆さんすごいです!!」と感嘆されていました。
《地域活動パネル展示》
高松市のコミュニティ事業、活動中のチャレンジ塾OBチーム、近県姉妹塾の取り組みを紹介しました。それぞれの活動を知り、関わる人に会いたくなる!それこそ地域活動のの第一歩です。アートステーションのギャラリーでは高松市の各コミュニティ協議会の展示があり16もの協議会に参加していただきました。御厩焼や各協議会の色とりどりのパネル展示に皆さん立ち止まって見入っておられました。アートステーション多目的スタジオでは、県外の須崎市・西条市から出張展示もあり、地域の家ココカラハウス・ぬくぬくママSUN’S・さくらや・さをり織工房 咲く屋などの地域づくりチャレンジ塾OBチームなど10団体が参加し活動を報告していました。
《最終報告会》地域づくりチャレンジ塾2016 ビギナーコース
ワールドカフェの後はいよいよビギナーコースの報告会です。
発表者の皆さんからは一様に緊張感が伝わってきます。ビギナーコースはテーマもバラエティに富んでおり、個性が光るプレゼンが繰り広げられました。
それぞれの発表の後、コメンテーターや塾長からコメントがあり、そこで塾生と少しやりとりがあるのですが、「ビギナーのレベルで、塾生からここまで言葉が出てくるのは珍しい。しかも全員。今回は本当にレベルが高いです。」と塾長。そのなかでも、「今回のプレゼンは神が降りてきた!!」と塾長が唸った川原千鶴さんが、みごと企画賞を受賞されました。
聴講の方々もとても真剣に、熱心に耳を傾けられていて、会場が熱くひとつになった報告会でした。
発表者、テーマは以下の通りです(番号は発表順)。↓↓
1.石塚めぐみ 『困っている人を見かけたら、自然と手を差しのべれる人が増える社会を目指したい』
2.福井瑞穂 『LGBT』
3.松本武司 『年齢を重ねることが楽しみになる 新しいセルフケアのご提案』
4.山本龍太郎 『エンタメ×ワークショップ=「夢中」』
5.上原千鶴 『お片付けでまるごとつなぐ プロジェクト』
6.斉藤 修 『海プロジェクトin高松』
報告会の後、塾生一人ひとりに塾長より修了証が手渡され、皆さん達成感いっぱいの表情で受け取っていらっしゃいました。そして最後に、塾生の皆さんからサプライズで塾長へ花束が‼
≪映画 Lemon&Letter 上映会≫
ビギナーコース報告会の後は、市民活動センター会議室に場所を移して、さぬき映画祭2017優秀企画上映作品である映画「Lemon&Letter」の上映会です。
舞台となった男木島の美しさに何度もはっとさせられた映画でした。上映終了後のアフタートークには、企画・脚本・監督を手掛けた梅木佳子さんと、出演された女優の木内晶子さん、子役の大林 嵩季くん、小林 碧さんも登場してくださり、オーディションについてやロケの苦労話などいろいろな裏話を聞くことができました。
≪交流会≫
その後、ふたたびアートステーション多目的スタジオに移っての交流会です。
学縁祭のスタートからかなり長い時間が経っていましたが、出席された皆さんはまだまだ熱く語り合っていらっしゃいました。
2017年02月19日
高松市まちづくり学校『地域づくりチャレンジ塾2016』講座⑤
日時:平成29年2月18日(土)
【ビギナーコース】 13:30~17:00
会場:高松市市民活動センター会議室
塾長:尾野寛明氏
〔ケーススタディ〕
塾長:尾野寛明さん(有限会社エコカレッジ代表取締役・NPO法人てごねっと石見副理事長)
ケーススタディの尾野塾長から、「地域の困っている事を聞くと自分達のやるべき方向性がみつかり、やがて仕事となり地域資源の発見となる」との想いを伝えられ、広い視野で物事を意識することを教わりました。
今回はビギナーコースでしたが、アドバンスの塾生の参加があり、アドバンスコースのさをり織り工房 咲く屋さんからのスタートでした。内容の充実度と完成度の高さにどよめきがおきていました。ビギナーコースのプレゼンは自身の思いがカタチになり成熟度が前にも増していて、尾野塾長の「いいね!」が何度も聞かれました。

日時:平成29年3月18日(土)
場所:市民交流プラザIKODE瓦町
アートステーション・市民活動センター(瓦町FLAG8階)
《最終報告会》
『地域づくりチャレンジ塾2016』
【ビギナーコース】報告会&表彰式
【アドバンスコース】報告会
《ワールドカフェ》
テーマ『次世代担い手にバトンをつなぐ方法!』
世代を超えた対話の場を開催します。
《地域活動パネル展示》
【協力団体】
高松市の各コミュニティ協議会・地域づくりチャレンジ塾OBチーム
地域の家ココカラハウス・ぬくぬくママSUN’S
さくらや・さをり織り工房 咲く屋
《Lemon&Letter》 ~さぬき映画祭2017優秀企画上映作品~
【無料上映】
瀬戸内海に浮かぶ島~美しい男木島を舞台にした、ちいさな恋の物語です。男木島を中心に高松市内・丸亀市など香川県内で撮影を行い、島の活性化を目指した自主制作映画に触れてください。
【ビギナーコース】 13:30~17:00
会場:高松市市民活動センター会議室
塾長:尾野寛明氏
〔ケーススタディ〕
塾長:尾野寛明さん(有限会社エコカレッジ代表取締役・NPO法人てごねっと石見副理事長)
ケーススタディの尾野塾長から、「地域の困っている事を聞くと自分達のやるべき方向性がみつかり、やがて仕事となり地域資源の発見となる」との想いを伝えられ、広い視野で物事を意識することを教わりました。
今回はビギナーコースでしたが、アドバンスの塾生の参加があり、アドバンスコースのさをり織り工房 咲く屋さんからのスタートでした。内容の充実度と完成度の高さにどよめきがおきていました。ビギナーコースのプレゼンは自身の思いがカタチになり成熟度が前にも増していて、尾野塾長の「いいね!」が何度も聞かれました。

☆次回は高松市まちづくり学校実行委員会 みんなの学縁祭です☆
日時:平成29年3月18日(土)
場所:市民交流プラザIKODE瓦町
アートステーション・市民活動センター(瓦町FLAG8階)
《最終報告会》
『地域づくりチャレンジ塾2016』
【ビギナーコース】報告会&表彰式
【アドバンスコース】報告会
《ワールドカフェ》
テーマ『次世代担い手にバトンをつなぐ方法!』
世代を超えた対話の場を開催します。
《地域活動パネル展示》
【協力団体】
高松市の各コミュニティ協議会・地域づくりチャレンジ塾OBチーム
地域の家ココカラハウス・ぬくぬくママSUN’S
さくらや・さをり織り工房 咲く屋
《Lemon&Letter》 ~さぬき映画祭2017優秀企画上映作品~
【無料上映】
瀬戸内海に浮かぶ島~美しい男木島を舞台にした、ちいさな恋の物語です。男木島を中心に高松市内・丸亀市など香川県内で撮影を行い、島の活性化を目指した自主制作映画に触れてください。
お申込みは不要です。皆様のお越しをお待ちしております。
2017年01月29日
高松市まちづくり学校『地域づくりチャレンジ塾2016』講座④
日時:平成29年1月28日(土)
【アドバンスコース】 10:15~12:15 【ビギナーコース】 13:30~17:00
会場:高松市市民活動センター会議室
塾長:尾野寛明氏
【アドバンスコース:マイプランの可能性を探る(プレゼン大会)】
アドバンスコースとしては3回目となる今回の講座では、プレゼン内容が非常に洗練され、事業内容や課題についての説明もより詳細なものになっています。これまでの実績に関する具体的な数字(データ)を基に説明がなされ、聞く側も引き込まれていました。
今後の事業展開に対する尾野塾長からの助言に加え、コラボレーションを前提とした塾生同士の意見交換は、濃厚で中身の詰まった聞き応えのあるものでした。

【ビギナーコース:マイプランを鍛える】
〔ケーススタディ〕
プレゼンター: 地域イベントプロデューサー 桑村美奈子さん
ケーススタディでは、東京都出身で、香川県に移住し“地域イベントプロデューサー”として活躍されている、桑村美奈子さんにお話を伺いました。
ビギナーコース受講者のマイプランはバラエティに富んでいて、それぞれの方向性や段階に沿ってアドバイスされるのが特徴ですが、今回は更に、ローカルな視点から課題が拾い上げられていました。桑村さんからも“地域性を考慮した活動方針”にフォーカスした指摘がなされていたのが非常に興味深く、印象的でした。「高松だからこそできること」その可能性が、塾生の皆さんの中でより広がったのではないでしょうか。

今回の講座では、新たな活動の一歩を踏み出した塾生からの報告もあり、メンター制度を含め、関係者間のたくさんの交流が実を結んでいるのを感じました。
☆次回、2月18日(土)は、【ビギナーコース:マイプランを磨く】のみ行われます。
※【アドバンスコース】の報告&交流会は、3月18日(土)に開催されます。
 聴講のお申込みは随時受け付けています。興味のある方は是非ご参加ください↓↓
聴講のお申込みは随時受け付けています。興味のある方は是非ご参加ください↓↓2016年12月26日
高松市まちづくり学校地域づくりチャレンジ塾2016 オプション企画「地域のフィールドを周る」
~テーマ:地域で活躍する人と接点を持つ~
十河コミュニティの取り組み見学ミニツアー
◆日時:平成28年12月23日(金・祝)10:20~12:00
◆会場:十河コミュニティセンター(十川西町579−1)
◆講師:十河校区コミュニティ協議会事務局 﨑山 美幸氏

「たかまつ・つなぎ手・ソウゾウ講座」初のオリジナル企画。十河校区コミュニティ協議会事務局の﨑山さんを迎え、十河コミュニティならではの”地域のまちづくりの取り組み“についてお話しいただきました。事例「あいさつレンジャー」は、スペシャルに塾生のハートをとらえたようで、塾長も塾生も心よりこの見学ミニツアーを楽しんだようで。地域に活きるプランづくりに役立つ話に、塾生も「活動を起こしたい」気持ちをますます高めていったことと思います。
十河コミュニティの取り組み見学ミニツアー
◆日時:平成28年12月23日(金・祝)10:20~12:00
◆会場:十河コミュニティセンター(十川西町579−1)
◆講師:十河校区コミュニティ協議会事務局 﨑山 美幸氏
「たかまつ・つなぎ手・ソウゾウ講座」初のオリジナル企画。十河校区コミュニティ協議会事務局の﨑山さんを迎え、十河コミュニティならではの”地域のまちづくりの取り組み“についてお話しいただきました。事例「あいさつレンジャー」は、スペシャルに塾生のハートをとらえたようで、塾長も塾生も心よりこの見学ミニツアーを楽しんだようで。地域に活きるプランづくりに役立つ話に、塾生も「活動を起こしたい」気持ちをますます高めていったことと思います。
2016年12月26日
高松市まちづくり学校地域づくりチャレンジ塾2016 ビギナーコース講座③
◆日 時:平成28年12月23日(金・祝) 13:30~17:00
◆会 場:高松私立おやこ小学校(仏生山町乙43-5)
◆ケーススタディ:「ゲストハウス若葉屋」オーナー 若宮 武 氏

【講座③マイプランを描く】
ゲストハウス若葉屋オーナー若宮さんの講演「ハチマキ締めずに、ゲストハウス」からスタート。続いて、仏生山まちプランニングルームの藤澤さんから、高松私立おやこ小学校について。会場が温もったところで、マイプラン発表へ。前講座にはなかった「私のすきなこと・できること・求められていること」シートがプラスされ、マイプランの骨子が見えて来ました。塾長から、次のステップに進むヒントが一人ひとりに飛んでいました。
◆会 場:高松私立おやこ小学校(仏生山町乙43-5)
◆ケーススタディ:「ゲストハウス若葉屋」オーナー 若宮 武 氏
【講座③マイプランを描く】
ゲストハウス若葉屋オーナー若宮さんの講演「ハチマキ締めずに、ゲストハウス」からスタート。続いて、仏生山まちプランニングルームの藤澤さんから、高松私立おやこ小学校について。会場が温もったところで、マイプラン発表へ。前講座にはなかった「私のすきなこと・できること・求められていること」シートがプラスされ、マイプランの骨子が見えて来ました。塾長から、次のステップに進むヒントが一人ひとりに飛んでいました。
2016年11月07日
高松市まちづくり学校『地域づくりチャレンジ塾2016』講座②
11月6日(日)に、『地域づくりチャレンジ塾2016』第2回講座が行われました。
会場:高松市市民活動センター会議室
塾長:尾野寛明氏
【アドバンスコース】 10:15~12:15
『見せ方、伝え方を高める(申請書等の書き方)』
アドバンスコースでは、チームプレゼン形式で各グループがそれぞれの課題をより具体的に発表しました。
初回に比べると皆さんリラックスした様子で、笑いが起こったり声を掛け合ったりと、チーム同士の距離も縮まってきたようです。プレゼンの中で前回他のチームが自己紹介した内容に言及し、相手チームを引き込む、といった一幕もあり、お互いのプレゼンを聞き、意見を出し合う “聞き方=聞く力” が、早くも『見せ方・伝え方』に活かされているように感じました。

【ビギナーコース】 13:30~17:00
『マイプランを浮かべる・地域課題を考える』
午後からのビギナーコースは、ケーススタディから始まりました。今回のプレゼンターは、高松市まちづくり学校実行委員会の古竹委員長です。
有志の呼びかけから始まり広がってきた、地域密着のメセナ活動でもある「UDON楽カウントダウン高松コンサート」について、その発起人である古竹さん自らが語ってくれました。
さらに、前回同様、車座になって行われた全体セッションでは、尾野塾長が取り組む活動事例の紹介もありました。
これから地域課題に向き合っていこうとする皆さんにとって、より身近で具体的なヒントになったのではないでしょうか。
また、今期の新たな試みとして「メンター制度」が採り入れられることになりました。
次回、12月23日(金・祝)は、【ビギナーコース第3回講座】のみ行われます。
テーマは『マイプランを描く』です。
※【アドバンスコース第3回講座】は、2017年1月28日(土)に開催されます。
★聴講のお申込みは随時受け付けていますので、興味のある方は是非ご参加ください↓↓
2016年09月27日
高松市まちづくり学校『地域づくりチャレンジ塾2016』
アドバンスコース 講座①「次の一手 踏み出し方を考える」
日時:9月24日(土) 10:15~12:15
会場:高松市市民活動センター会議室
参加者:受講生9名、聴講参加者3名
塾長:尾野寛明氏
〔ケーススタディ〕
日時:9月24日(土) 10:15~12:15
会場:高松市市民活動センター会議室
参加者:受講生9名、聴講参加者3名
塾長:尾野寛明氏
〔ケーススタディ〕
プレゼンター:竹田美保子さん

いよいよ始まりました『地域づくりチャレンジ塾2016』!
今期は「ビギナーコース」と「アドバンスコース」の2コースに分かれ、それぞれの段階に合わせた内容に取り組みます。
まずは、午前に行われたアドバンスコースからスタート。
アドバンスコースは“すでに市民活動等で動き出している方”を対象とし、発展的な活動・継続の具体的なノウハウを経営者や組織の運営者から学ぶ内容となっています。

いよいよ始まりました『地域づくりチャレンジ塾2016』!
今期は「ビギナーコース」と「アドバンスコース」の2コースに分かれ、それぞれの段階に合わせた内容に取り組みます。
まずは、午前に行われたアドバンスコースからスタート。
アドバンスコースは“すでに市民活動等で動き出している方”を対象とし、発展的な活動・継続の具体的なノウハウを経営者や組織の運営者から学ぶ内容となっています。
そのため、組織としての課題をお持ちの方々が受講生として集まりました。
初回ということで、はじめに塾長、高松市まちづくり学校実行委員の自己紹介があり、いよいよ講座開始!
今回は地域で活躍されている方のケーススタディを伺います。
初回ということで、はじめに塾長、高松市まちづくり学校実行委員の自己紹介があり、いよいよ講座開始!
今回は地域で活躍されている方のケーススタディを伺います。
プレゼンターは、実行委員でもある竹田美保子さん。若い世代の居場所である「地域の家ココカラハウス」の立ち上げの頃のエピソードや現在の活動について、興味深いお話をして下さいました。
続いて、塾生の皆さんが事前課題のシートをもとに自己紹介。
団体の活動内容と組織の課題について発表し、それぞれの課題に対して塾長からアドバイスをもらいました。
初日ということもあり、皆さんの集中力がビシビシと伝わってくるような雰囲気でしたが、発表の合間に笑いや拍手が起こることもあって、次第に打ち解けた空気に。
ビギナーコース開始までの間に行われたランチ交流会は、とても賑やかで皆さん本当に楽しそうなご様子でした。
アドバンスコースは全4回。
次回、第2回の内容は「見せ方、伝え方を高める(申請書等の書き方)」です。
★聴講のお申込みは随時受け付けていますので、興味のある方は是非ご参加ください↓↓
http://www.flat-takamatsu.net/bcs/info3166.html
続いて、塾生の皆さんが事前課題のシートをもとに自己紹介。
団体の活動内容と組織の課題について発表し、それぞれの課題に対して塾長からアドバイスをもらいました。
初日ということもあり、皆さんの集中力がビシビシと伝わってくるような雰囲気でしたが、発表の合間に笑いや拍手が起こることもあって、次第に打ち解けた空気に。
ビギナーコース開始までの間に行われたランチ交流会は、とても賑やかで皆さん本当に楽しそうなご様子でした。
アドバンスコースは全4回。
次回、第2回の内容は「見せ方、伝え方を高める(申請書等の書き方)」です。
★聴講のお申込みは随時受け付けていますので、興味のある方は是非ご参加ください↓↓
http://www.flat-takamatsu.net/bcs/info3166.html
2015年07月03日
平成27年度高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾2015」受講生募集!
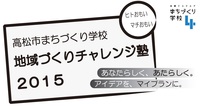
“高松でこんなことできないかな”
“あんな街みたいに変えられなかな”
地域で自分たちの課題に自主的に取り組む人たちが増えています。このチャレンジ塾は、活躍中の地域のリーダーからアドバイスを受けながら、年齢を問わず、自分らしく実践的な活動プランを作る学び合いの場です。
昨年度の地域づくりチャレンジ塾では、塾生それぞれが多様なマイプランを完成させ、すでに各自実践に移っています。
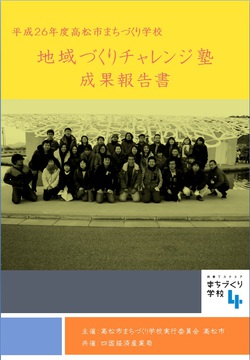
2015年度は、9月27日(日)から翌年3月20日(日)までの期間で、全6回の講座を開催し、新たな受講生を限定10名で募集します。
まずは講座の内容をお伝えするプレセミナーを、2015年8月22日(土)に開催しますので、ぜひご参加ください。
詳しくは、高松市市民活動センターホームページで。
2015年04月04日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」最終回
いよいよ最終回、塾生各自のマイプラン発表会です。
場所は、第1回目と同じ仏生山。
第1回はお寺でしたが、今回は、電車。
コトデン仏生山駅、3番ホームに停車中の電車の中が会場です。

右側の電車が本日の会場。

会場入口。

眞鍋さん、そして、尾野さんのお話から。

尾野さん、電車のマイクを持って、見るからにうれしそうですねえ。
かなりの鉄道ファンだそうで、この日は北陸新幹線の開業日だったけど、
コッチに来てよかった とかも言われてました。

そして円陣を組んで、プレゼンがスタート。
皆さん笑顔ですが、
昨夜、遅くまで尾野塾長の添削を受けて、
当日の朝、プレゼン資料をつくった方も、何人かいらっしゃいます。
プランの一覧は、こちら。

途中、聴講生が塾生1人1人を囲んで、グループワーク。


全てのプレゼンが終了し、
コメンテイターの方からコメントをいただいて、
尾野塾長、眞鍋副塾長もコメントして、終了。
のはずが、塾生の大美さんから「ちょっと待ったぁ!」
塾生の皆さまから、尾野塾長、眞鍋副塾長、そして、人見&川井コーディネータに、記念品の贈呈。
完全にサプライズで、驚きました。

そして、7番ホームのレトロ電車(大正15年製!) へ移動し、電車の中で交流会。


みなさん、いい笑顔ですねぇ。
これからもよろしくお願いします。

文:川井(四国経済産業局)
場所は、第1回目と同じ仏生山。
第1回はお寺でしたが、今回は、電車。
コトデン仏生山駅、3番ホームに停車中の電車の中が会場です。

右側の電車が本日の会場。

会場入口。

眞鍋さん、そして、尾野さんのお話から。

尾野さん、電車のマイクを持って、見るからにうれしそうですねえ。
かなりの鉄道ファンだそうで、この日は北陸新幹線の開業日だったけど、
コッチに来てよかった とかも言われてました。

そして円陣を組んで、プレゼンがスタート。
皆さん笑顔ですが、
昨夜、遅くまで尾野塾長の添削を受けて、
当日の朝、プレゼン資料をつくった方も、何人かいらっしゃいます。
プランの一覧は、こちら。

途中、聴講生が塾生1人1人を囲んで、グループワーク。


全てのプレゼンが終了し、
コメンテイターの方からコメントをいただいて、
尾野塾長、眞鍋副塾長もコメントして、終了。
のはずが、塾生の大美さんから「ちょっと待ったぁ!」
塾生の皆さまから、尾野塾長、眞鍋副塾長、そして、人見&川井コーディネータに、記念品の贈呈。
完全にサプライズで、驚きました。

そして、7番ホームのレトロ電車(大正15年製!) へ移動し、電車の中で交流会。


みなさん、いい笑顔ですねぇ。
これからもよろしくお願いします。

文:川井(四国経済産業局)
2015年04月04日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」講座5
第5回講座は、高松市の東、旧:庵治町にある「純愛の聖地 庵治・観光交流館」。
映画「世界の中心で、愛をさけぶ」のロケ地です。
聴講に来られた方の中には、
早めに来て、自転車でロケ地巡りをされた方もいらっしゃったようです。

****************
今回が第5回目ですが、次回はもう最終回で「プラン発表」。
講座としては、実質的に最後 です。
まずは、尾野塾長からのプレゼンテーション。


ご自身がやられてるネット古書店「(有)エコカレッジ」の話、
首都圏から島根県川本町へ移住した話、
これまで関わられてきた街の活動の話、
そして、まちの活動、そう簡単にいかないこと、
その中で、副理事長として関わっている「NPO法人てごねっと石見」と江津市の活動の話。
いやぁ、濃厚でした。
中でも、「何かを変えるには蓄積が必要」として示された、島根県江津市と、某○町の活動状況の俯瞰図。
そうだよなぁ、何か一つやったからってどうなるものでもないんだよなぁ と、唸ってしまいました。


****************
そして、塾生のワークへ。
これまでは2~3のグループに分かれてやっていたんですが、
今回は最後だし、グループ分けをせず、みんなでやろう と。
写真は、
「里山で、子どもたちが学ぶ場」をつくりはじめられている方。
塾生や聴講生の子どもさんが来ていたので、プレゼン後、子どもたちを相手に実演してもらいました。
すばらしかったです。
****************
そして、塾生のワークへ。
これまでは2~3のグループに分かれてやっていたんですが、
今回は最後だし、グループ分けをせず、みんなでやろう と。
写真は、
「里山で、子どもたちが学ぶ場」をつくりはじめられている方。
塾生や聴講生の子どもさんが来ていたので、プレゼン後、子どもたちを相手に実演してもらいました。
すばらしかったです。

最後に、集合写真を。

****************
と、本来、ここで終わりなんですが、
その後、塾生の発案で、最終発表会までに自主トレをしよう と。
別の塾生の方が、地域の家「ココカラ★ハウス」を始めてるので、
「ココカラ★ハウス」を借りて、集まって、
プレゼンの練習とプレゼンデータの作成をしよう。
そんな呼びかけがあって、何度か集まりました。

「ココカラ★ハウス」、大学生とかが集まる場になっていて、
子ども連れでも練習に集中できました。
ありがとう!


最後の写真は、最終プレゼンの前日、
3月13日の23時すぎ。
お疲れさまでした。
さっ、最終プレゼンへ。
文:川井(四国経済産業局)
映画「世界の中心で、愛をさけぶ」のロケ地です。
聴講に来られた方の中には、
早めに来て、自転車でロケ地巡りをされた方もいらっしゃったようです。

****************
今回が第5回目ですが、次回はもう最終回で「プラン発表」。
講座としては、実質的に最後 です。
まずは、尾野塾長からのプレゼンテーション。


ご自身がやられてるネット古書店「(有)エコカレッジ」の話、
首都圏から島根県川本町へ移住した話、
これまで関わられてきた街の活動の話、
そして、まちの活動、そう簡単にいかないこと、
その中で、副理事長として関わっている「NPO法人てごねっと石見」と江津市の活動の話。
いやぁ、濃厚でした。
中でも、「何かを変えるには蓄積が必要」として示された、島根県江津市と、某○町の活動状況の俯瞰図。
そうだよなぁ、何か一つやったからってどうなるものでもないんだよなぁ と、唸ってしまいました。


****************
そして、塾生のワークへ。
これまでは2~3のグループに分かれてやっていたんですが、
今回は最後だし、グループ分けをせず、みんなでやろう と。
写真は、
「里山で、子どもたちが学ぶ場」をつくりはじめられている方。
塾生や聴講生の子どもさんが来ていたので、プレゼン後、子どもたちを相手に実演してもらいました。
すばらしかったです。
****************
そして、塾生のワークへ。
これまでは2~3のグループに分かれてやっていたんですが、
今回は最後だし、グループ分けをせず、みんなでやろう と。
写真は、
「里山で、子どもたちが学ぶ場」をつくりはじめられている方。
塾生や聴講生の子どもさんが来ていたので、プレゼン後、子どもたちを相手に実演してもらいました。
すばらしかったです。

最後に、集合写真を。

****************
と、本来、ここで終わりなんですが、
その後、塾生の発案で、最終発表会までに自主トレをしよう と。
別の塾生の方が、地域の家「ココカラ★ハウス」を始めてるので、
「ココカラ★ハウス」を借りて、集まって、
プレゼンの練習とプレゼンデータの作成をしよう。
そんな呼びかけがあって、何度か集まりました。

「ココカラ★ハウス」、大学生とかが集まる場になっていて、
子ども連れでも練習に集中できました。
ありがとう!


最後の写真は、最終プレゼンの前日、
3月13日の23時すぎ。
お疲れさまでした。
さっ、最終プレゼンへ。
文:川井(四国経済産業局)
2015年01月29日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」講座4
第4回講座は、高松港から8km北にある「男木島」(おぎしま)で開催されました。
会場は、「男木島の魂」(ジャウメ・プレンサ作)。
フェリーのキップ売り場で、待合室で、交流の場。
そんな瀬戸内国際芸術祭の作品が会場です。

写真だと良い天気のように見えますが、この日は寒い日で、風も強く、フェリーは大揺れ。
島根県在住の尾野塾長、「隠岐汽船なみの揺れ」と言われましたが、
これが序の口だったというのが、最後に判明。でも、それは最後の最後(苦笑

まだ高松港を出港したばかりですが、この波。
フェリーが遅れて到着したので、すぐに開始。
男木島に関わって活動している方が、次々と登場されました。
****************
*まずは、「男木地区コミュニティ協議会」の大石さんが、男木島を紹介。

男木島の人口は、男性87人、女性99人の186人。平均年齢は65.6歳(2014年12月)。
1年前、2013年の平均年齢は69歳。
小中学生や幼児が増えて、平均年齢が下がってきてるそうです。
そんな大石さんの“マイプラン”は、「男木島ミュージックフェス2015(仮)」の開催。
フェリー「めおん」での船上ライブ、港での野外ライブ、島内散策、バザー、男木特産品販売などで、男木島を一人でも多くの人に知って貰うこと。
そして、男木島の魅力を発見してもらい、男木島のファン、リピーターになってもらい、移住者につなげたい。そんなプランです。
*続いて、「オンバ・ファクトリー」の大島さんと奥さま。

オンバ・ファクトリー。
坂道や細い路地が多い男木島で使われている「オンバ」(乳母車)に
カラフルなペイントを施し、島の風景を賑やかに彩る。
そんな、瀬戸内国際芸術祭の活動です。
2010年の瀬戸国際内芸術祭をキッカケに男木島に関わることになった大島さんご夫婦。
関わり始めた当時の男木島は、住民の過半数が75歳以上で、釣り人しか来ない島。
“孤島”だと感じられたそうです。
そんな男木島が芸術祭の会場になり、
大島さんのようなアーティストが来られ、多くの方が作品制作や運営で関わり、
そして、会期中、実に大勢の方が島に来られました。
そんな、2010年の芸術祭が終わった、交流会での、島民の一言。
「あんたらぁも、もう、来んようになるんか。」
その5か月後の2011年3月には、最後の中学生が卒業し、「男木小・中学校」は休校に。
男木島が無人島にならないようにしよう。
ご夫婦で、「10年後の学校再開」を目標にされ、島民になられたそうです。
まず、人として信頼してもらうことが大事。
島で生活していると、“それ、おかしいやろ”と思うこと、溢れるようにあるけど、
まずは従う。自分流ではなく、島流を大切にする。
島流に従ってやってから、“こうしたらどうやろ”と提案すると、驚くほどあっさりと受け止めてくれる。
そして、「男木deあそび隊」を結成。
観光客に来てもらうのではなく、男木島が好きな人たちが集まって男木島で遊ぶ。
そんなワークショップとかのイベントを開催。
島の人には、“何もないことはすばらしいこと”を伝えることを意識して実施。
提案した民泊も開業。
そして、2014年4月、「男木小・中学校」が再開。
UIターンも、2014年は19人に。
「若い人が住み出したら、お年寄りが安心してるのがわかる」
「“新しいものをつくる”のは難しいけど、
“昔、つくっていたものを、カタチを変えて復活する”ことはできる」と大島さん。
現在は、週の3日は高松で講師、週の4日は男木島で、オンバをつくったり、ワクワクしながら島の活動を手伝われているそうです。
*男木島チームの最後は、IUターンの「福井さんご夫婦」と「橋本さん」。

右端で座られているのが福井さん。
その左が橋本さん、福井さん奥さん。
福井さんは、男木島のご出身。
高校進学で男木島を離れ、大阪で働かれていた福井さん。
2013年の芸術祭で男木島へ戻ってきた時、小・中学校が休校になっていることを知ります。
「いつかそうなるだろうとは思っていたけど、目の当たりにしたら、ショックで。」
このままでは島が消滅すると思った福井さんの仕事はデザイン。奥さまの仕事はIT系。
パソコンがあれば仕事ができると、男木島と大阪との2拠点生活をおくられます。
そして、学校再開に向けて雇用を産み出せないかと、特産品づくりに着手。
「昔の男木島は底引き網漁が盛んだった。値段は付かなかったけど、エビが大量にとれていた。これをなんとかできないか」と。無添加の干しエビを商品化。
これが好評で、現在は品切れ状態。2015年には、1人雇用できるかも知れないそうです。
一方の橋本さんは、2013年の芸術祭で「男気プロジェクト」の作品をつくられた「TEAM 男気」(ちーむ おぎ)の作家さん。
芸術祭をキッカケに男木島に移住して、現在は“漁師の見習い中”だそうで、
なんか、皆さん、スゴイです。
****************
男木島チームの話をうかがっての、尾野塾長、眞鍋副塾長のコメント。
○200人弱の島で、移住者が1年で19人って、スゴイですねぇ。
島はもう高齢化してるから、これから若返っていく可能性がありますよね。
○移住は、年に1~2回来るファンが100~200人に増えてくると、1人移住する。
そんな傾向だと感じてるんですが、ファンづくりがすごいですね。
○チーム戦ですね。人がつながり、みんなが自然と助け合ってる“チーム感”が良いですね。

皆さんのお話を伺っているうちに、天気が良くなってきました。
そして、今日のプレゼン、もう1人は眞鍋副塾長です。
****************
東京で勤められていた眞鍋さん。
リーマンショックで会社が倒産・失業した後、渡米されるのですが、
渡米の前の数ヶ月、十数年ぶりに実家で生活されたそうです。その時、
「あれ? マスコミは、地方は疲弊してると言ってるけど、
地方の方が生き生きしてるじゃない。笑顔が多いじゃない。」
と感じられたそうです。
「都会は、全体としては人口も多いし、GDPも多い。でも、人は眉間にシワを寄せてる。」
地方や女性の時代だと思い、渡米後、東京で地元発信をされます。
そして、農家の作り手さんと出会います。
「使命感があるし、熱い想いがある。カッコいい。」
そして、<地元に戻る>、<地域おこしをなりわいにしよう>と決められたそうです。

今回は、時間が短かったので、要点をかいつまんでお話いただきました。
以下、そのエッセンスを。
【6次産業化】
よく6次産業化っていいますけど、家族経営の農家さんが2次、3次もやるって難しいんじゃないかと思うんです。
農家さんには1次、作り手に専念してもらって、自分が2次、3次を担当する。
そして、<チームで6次産業化>すれば良いと思ってやってます。
【田舎には仕事がない?】
仕事っていうのは、<困りごとの解決>です。
田舎には<困りごと>がいっぱいあります。だから仕事はいっぱいある。
ただ、都会とは構造が違うんです。
都会は、<困りごとがタテに集積>しています。だから<職になる>んです。
例えば、東京の駅。大きな駅には必ず“靴の修理屋さん”があります。
あれ、駅の階段とかでハイヒールが折れてしまう人が大勢いるから修理してるんです。
だから、駅で靴の修理をするだけで職になるんです。
でもこれ、田舎では成り立ちません。
田舎では、<いろんなことをやる>ことが必要なんです。
1つのビジネスプラン、職じゃなく、いろんなことをやって<何屋かわからない>。
そして、必ずしも<お金>になるとは限らない。
<ミカン>になるかも知れないし、<1週間後、軒先に大根>が置かれてるかも知れない。
これでOKなんです。
【地域おこし協力隊へ言っていること】
地域おこし協力隊に何か言ってくれという機会があって、その時、話したこと。
「世の中に“答え”はない。
“答え”はつくるもの。
それを“答え”と認めてもらうよう、努力する。」
小豆島に移住する時、東京の仲間は、みんな反対してました。
でも、今、みんなに“いいね”と言われます。
僕は手に職がありません。
資金調達や仲間づくりをしようと思って動いたこともありません。
ただ、<話して>、<旗を立てて>、<動く>。
すると、仲間が集まってきます。
「最後にマジックワードを。<人生は祭り>だ。」
****************
実は、もっと具体的なキーワードもご紹介いただいたんですが、省略させていただきます。(ごめんなさい)
そして、グループワークへ。
塾生のプランに、大島さんからもコメントをいただきました。

ところで、全国8箇所で塾をやられている尾野塾長、「4回目ぐらいが一番キツイ」と言われてました。
実際、今回に向けて悩まれた塾生の方、少なくなかったようですが、
そこを乗り越えて、吹っ切れた(昇華した)方、多くいらっしゃったようです。
****************
そして交流会。
ですが、ココは男木島。
交流会に参加する方は、交流会の後、チャーターした海上タクシーで帰りますが、
まず、交流会に参加できない方が帰られる、フェリーの最終便をお見送り。

島で最終便の船を見送る。なかなかレアな体験。
そして、交流会場の「島テーブル」へ。

まず、捌いてくれているイノシシの肉を自分たちで切って、
大きな生け簀に入っているタイ、サヨリ、牡蠣などなどを焼いてのバーベキュー。

コレ、塾生の波多さんにお願いして実現した、
「男木地区コミュニティ協議会プロデュース」のバーベキュー。
これもレアな体験。
大感謝 です!
会場は、「男木島の魂」(ジャウメ・プレンサ作)。
フェリーのキップ売り場で、待合室で、交流の場。
そんな瀬戸内国際芸術祭の作品が会場です。

写真だと良い天気のように見えますが、この日は寒い日で、風も強く、フェリーは大揺れ。
島根県在住の尾野塾長、「隠岐汽船なみの揺れ」と言われましたが、
これが序の口だったというのが、最後に判明。でも、それは最後の最後(苦笑

まだ高松港を出港したばかりですが、この波。
フェリーが遅れて到着したので、すぐに開始。
男木島に関わって活動している方が、次々と登場されました。
****************
*まずは、「男木地区コミュニティ協議会」の大石さんが、男木島を紹介。

男木島の人口は、男性87人、女性99人の186人。平均年齢は65.6歳(2014年12月)。
1年前、2013年の平均年齢は69歳。
小中学生や幼児が増えて、平均年齢が下がってきてるそうです。
そんな大石さんの“マイプラン”は、「男木島ミュージックフェス2015(仮)」の開催。
フェリー「めおん」での船上ライブ、港での野外ライブ、島内散策、バザー、男木特産品販売などで、男木島を一人でも多くの人に知って貰うこと。
そして、男木島の魅力を発見してもらい、男木島のファン、リピーターになってもらい、移住者につなげたい。そんなプランです。
*続いて、「オンバ・ファクトリー」の大島さんと奥さま。
オンバ・ファクトリー。
坂道や細い路地が多い男木島で使われている「オンバ」(乳母車)に
カラフルなペイントを施し、島の風景を賑やかに彩る。
そんな、瀬戸内国際芸術祭の活動です。
2010年の瀬戸国際内芸術祭をキッカケに男木島に関わることになった大島さんご夫婦。
関わり始めた当時の男木島は、住民の過半数が75歳以上で、釣り人しか来ない島。
“孤島”だと感じられたそうです。
そんな男木島が芸術祭の会場になり、
大島さんのようなアーティストが来られ、多くの方が作品制作や運営で関わり、
そして、会期中、実に大勢の方が島に来られました。
そんな、2010年の芸術祭が終わった、交流会での、島民の一言。
「あんたらぁも、もう、来んようになるんか。」
その5か月後の2011年3月には、最後の中学生が卒業し、「男木小・中学校」は休校に。
男木島が無人島にならないようにしよう。
ご夫婦で、「10年後の学校再開」を目標にされ、島民になられたそうです。
まず、人として信頼してもらうことが大事。
島で生活していると、“それ、おかしいやろ”と思うこと、溢れるようにあるけど、
まずは従う。自分流ではなく、島流を大切にする。
島流に従ってやってから、“こうしたらどうやろ”と提案すると、驚くほどあっさりと受け止めてくれる。
そして、「男木deあそび隊」を結成。
観光客に来てもらうのではなく、男木島が好きな人たちが集まって男木島で遊ぶ。
そんなワークショップとかのイベントを開催。
島の人には、“何もないことはすばらしいこと”を伝えることを意識して実施。
提案した民泊も開業。
そして、2014年4月、「男木小・中学校」が再開。
UIターンも、2014年は19人に。
「若い人が住み出したら、お年寄りが安心してるのがわかる」
「“新しいものをつくる”のは難しいけど、
“昔、つくっていたものを、カタチを変えて復活する”ことはできる」と大島さん。
現在は、週の3日は高松で講師、週の4日は男木島で、オンバをつくったり、ワクワクしながら島の活動を手伝われているそうです。
*男木島チームの最後は、IUターンの「福井さんご夫婦」と「橋本さん」。
右端で座られているのが福井さん。
その左が橋本さん、福井さん奥さん。
福井さんは、男木島のご出身。
高校進学で男木島を離れ、大阪で働かれていた福井さん。
2013年の芸術祭で男木島へ戻ってきた時、小・中学校が休校になっていることを知ります。
「いつかそうなるだろうとは思っていたけど、目の当たりにしたら、ショックで。」
このままでは島が消滅すると思った福井さんの仕事はデザイン。奥さまの仕事はIT系。
パソコンがあれば仕事ができると、男木島と大阪との2拠点生活をおくられます。
そして、学校再開に向けて雇用を産み出せないかと、特産品づくりに着手。
「昔の男木島は底引き網漁が盛んだった。値段は付かなかったけど、エビが大量にとれていた。これをなんとかできないか」と。無添加の干しエビを商品化。
これが好評で、現在は品切れ状態。2015年には、1人雇用できるかも知れないそうです。
一方の橋本さんは、2013年の芸術祭で「男気プロジェクト」の作品をつくられた「TEAM 男気」(ちーむ おぎ)の作家さん。
芸術祭をキッカケに男木島に移住して、現在は“漁師の見習い中”だそうで、
なんか、皆さん、スゴイです。
****************
男木島チームの話をうかがっての、尾野塾長、眞鍋副塾長のコメント。
○200人弱の島で、移住者が1年で19人って、スゴイですねぇ。
島はもう高齢化してるから、これから若返っていく可能性がありますよね。
○移住は、年に1~2回来るファンが100~200人に増えてくると、1人移住する。
そんな傾向だと感じてるんですが、ファンづくりがすごいですね。
○チーム戦ですね。人がつながり、みんなが自然と助け合ってる“チーム感”が良いですね。

皆さんのお話を伺っているうちに、天気が良くなってきました。
そして、今日のプレゼン、もう1人は眞鍋副塾長です。
****************
東京で勤められていた眞鍋さん。
リーマンショックで会社が倒産・失業した後、渡米されるのですが、
渡米の前の数ヶ月、十数年ぶりに実家で生活されたそうです。その時、
「あれ? マスコミは、地方は疲弊してると言ってるけど、
地方の方が生き生きしてるじゃない。笑顔が多いじゃない。」
と感じられたそうです。
「都会は、全体としては人口も多いし、GDPも多い。でも、人は眉間にシワを寄せてる。」
地方や女性の時代だと思い、渡米後、東京で地元発信をされます。
そして、農家の作り手さんと出会います。
「使命感があるし、熱い想いがある。カッコいい。」
そして、<地元に戻る>、<地域おこしをなりわいにしよう>と決められたそうです。

今回は、時間が短かったので、要点をかいつまんでお話いただきました。
以下、そのエッセンスを。
【6次産業化】
よく6次産業化っていいますけど、家族経営の農家さんが2次、3次もやるって難しいんじゃないかと思うんです。
農家さんには1次、作り手に専念してもらって、自分が2次、3次を担当する。
そして、<チームで6次産業化>すれば良いと思ってやってます。
【田舎には仕事がない?】
仕事っていうのは、<困りごとの解決>です。
田舎には<困りごと>がいっぱいあります。だから仕事はいっぱいある。
ただ、都会とは構造が違うんです。
都会は、<困りごとがタテに集積>しています。だから<職になる>んです。
例えば、東京の駅。大きな駅には必ず“靴の修理屋さん”があります。
あれ、駅の階段とかでハイヒールが折れてしまう人が大勢いるから修理してるんです。
だから、駅で靴の修理をするだけで職になるんです。
でもこれ、田舎では成り立ちません。
田舎では、<いろんなことをやる>ことが必要なんです。
1つのビジネスプラン、職じゃなく、いろんなことをやって<何屋かわからない>。
そして、必ずしも<お金>になるとは限らない。
<ミカン>になるかも知れないし、<1週間後、軒先に大根>が置かれてるかも知れない。
これでOKなんです。
【地域おこし協力隊へ言っていること】
地域おこし協力隊に何か言ってくれという機会があって、その時、話したこと。
「世の中に“答え”はない。
“答え”はつくるもの。
それを“答え”と認めてもらうよう、努力する。」
小豆島に移住する時、東京の仲間は、みんな反対してました。
でも、今、みんなに“いいね”と言われます。
僕は手に職がありません。
資金調達や仲間づくりをしようと思って動いたこともありません。
ただ、<話して>、<旗を立てて>、<動く>。
すると、仲間が集まってきます。
「最後にマジックワードを。<人生は祭り>だ。」
****************
実は、もっと具体的なキーワードもご紹介いただいたんですが、省略させていただきます。(ごめんなさい)
そして、グループワークへ。
塾生のプランに、大島さんからもコメントをいただきました。

ところで、全国8箇所で塾をやられている尾野塾長、「4回目ぐらいが一番キツイ」と言われてました。
実際、今回に向けて悩まれた塾生の方、少なくなかったようですが、
そこを乗り越えて、吹っ切れた(昇華した)方、多くいらっしゃったようです。
****************
そして交流会。
ですが、ココは男木島。
交流会に参加する方は、交流会の後、チャーターした海上タクシーで帰りますが、
まず、交流会に参加できない方が帰られる、フェリーの最終便をお見送り。

島で最終便の船を見送る。なかなかレアな体験。
そして、交流会場の「島テーブル」へ。

まず、捌いてくれているイノシシの肉を自分たちで切って、
大きな生け簀に入っているタイ、サヨリ、牡蠣などなどを焼いてのバーベキュー。

コレ、塾生の波多さんにお願いして実現した、
「男木地区コミュニティ協議会プロデュース」のバーベキュー。
これもレアな体験。
大感謝 です!
2014年12月19日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」講座3
「地域づくりチャレンジ塾」、12月13日(土)に、第3回講座が終了しました。
全6回の講座ですが、最終回は発表会ですから、今回、早くも折り返し点を迎えたことになります。早いなぁ。
第3回の会場は「四国村、久米通賢先生旧宅」。


四国村の正式名称は「四国民家博物館」。
四国各地から古い民家を移築復原した野外博物館。
体験学習の場であり、大人の観光スポットとご紹介いただきました。

四国村を運営している「公益財団法人 四国民家博物館」の門脇さん。
民間施設だということに、驚きの声も。
さて、本日のゲストは「矢田明子」さん。通称、矢田ママ。
「NPO法人おっちラボ」(島根県雲南市)の代表理事であり、
病院の保健師さんであり、
3人の子どもを持つお母さん。
今回の「地域づくりチャレンジ塾」の先駆けとなっているのは、島根県雲南市の「幸雲南塾」ですが、矢田ママは、幸雲南塾の第1期生(2011年)であり、受講をキッカケに、「おっちラボ」を立ち上げ、若者のチャレンジを応援しつつ、幸雲南塾では第3期から事務局を担い(それまでの事務局は雲南市役所)、第4期は塾長も務めている。
そんな方。
我々の塾の先進であるとともに、塾生を含めた我々全員の先輩です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
矢田 明子さん<特定非営利活動法人おっちラボ 代表理事>
「おっちラボ」のことと、「矢田ママ」ご自身のことについて、お話しいただきました。

矢田ママ、新婚旅行で四国に来られたそうで、旦那さんが大のうどん好き。
香川に滞在した数日間に、何十軒ものうどん屋へ行っていて、
もちろん、四国村のわら家へも来られているそう。
~おっちラボのこと~
島根県雲南市で開催されている幸雲南塾のOBらを中心に、若者チャレンジをサポートする組織として立ち上げ。
現在は、幸雲南塾の運営や、塾生OBらの地域づくりに携わる活動の支援を実施。
ということですが、雲南市の人口(約4万人)に対して塾生OBは63人と、まだまだ力不足だそうで(←63人の集団が生まれてるってスゴイと思いますが…)、地域の人たちをいかに巻き込んでいくかが課題。
塾生OBと地域とのマッチング、特に、市内に43ある地域自治組織とのマッチングを行っているそうで、例えば、鳥獣害対策支援の経験を活かそうと受講し、「ケモノにまけんもの」というマイプランをつくった専業主婦の方と、鍋山地区という地域自治組織とをマッチング。その専業主婦の方が、地域のお母さんには、家庭菜園に柵をつけるといったワークショップを行い、地域のお父さんには、狩猟を教えているそうです。
~矢田ママのこと~
3児の子育てをしながら大学に通い、看護学、中でも予防学を学んでいたとき、地域の人の生涯現役活動を応援したいなぁと思い、幸雲南塾に入塾。
コアには、小さな一対一のコミュニティを大切にしたい、元気にしたいという思いがある。
幸雲南塾での、矢田ママのマイプランは「イイトコ発見プロジェクト」。
地域の人が、それぞれ得意なことを楽しくやって元気に長く暮らせるようにしたい、と、おじいちゃん・障がい者・小学生が協働して畑づくりをするなどのイベントを開催。
このプランは現在でも塾生らに引き継がれているそうです。
~高松・塾生からの質問~
Q:おっちラボではどんな勤務体系ですか?
A:矢田ママご自身は「週3日が病院で保健師、その他の日が“おっちラボ”」。
スタッフは、約半数がこのスタイルで、残りの半数(4人)がフルタイムで勤務。
人件費は助成金を活用しているそうです。
Q:財源はどうしているんですか? ~やっぱり一番気になりますよね~
A:県や市からの受託事業のほかに、今、売り出しているのが、大学生の受入研修。
大学生が“おっちラボ”の活動に参加できるプログラムを提示し、大学に予算をつけてもらってます。
具体的には、東京大学や東京薬科大学などの大学生が、地域住民の家に泊まって、日常の活動に密着した研究を行ってもらうようなこと。
また、雲南市でやっている医療の視点の地域マネジメントも、パッケージとしていろいろな地域に売れるようになればいいなと思っています。
~最後に~
とにかく、迷走したり悩んだりしたら、是非、相談してください。
いろんな経験・専門のある人がいるので、解決する方法はきっとあります!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
という、力強いメッセージを受けて、グループワークへ。

聴講に来られた方も、熱心にメモをとられています。
ところで、今回の場所は「久米通賢先生旧宅」。
久米通賢先生(1780-1841)は多才な方ですが、最も有名なのは、塩を、香川県の代表的な産業へと育てられたことでしょうか。
財政難に陥っていた高松藩主(松平頼恕)から財政再建策を頼られ、現在の坂出市の浜に塩田を開発。坂出市の街の基礎を築かれた方。
ということで、坂出商工会議所の吉田さんにお越しいただきました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
吉田 浩城さん<坂出商工会議所 経営指導員>
ターニングポイントは、4年前の「飲み会」。
若い経営者の飲み会で、<駅前で朝市をやったらどうか>という話が出て、やろう、やろうということに。
ところが時期は2月。予算が全くないので、完全な手づくりでやるしかなく、出展や集客の呼びかけも、口コミとユーストリームの配信ぐらいしかできなかった。
ところが、当時、ユーストリーム自体がまだ珍しく、しかも、商工会議所がやってるというので、マスコミが面白がって紹介してくれて。
それで、だんだん広がっていって。
関わってる経営者の店の売上が上がってると、NHKまでやってきて。
4年間やってたら、出展者も41店舗になって、気がついたら186回ユーストリームを配信してるんです。

また、朝市をやり出していた頃、坂出商工会議所が補助金で、“地域資源を使って何かできないか”と調査をやって、塩業で発展した街を学ぼうと、平成24年4月、街歩き「坂出あまからめぐり」がスタート。
朝市をやっていた関係で、若い経営者がガイドしています。
経営者なので、受付とか事務をする人がいないなぁと思っていたら、坂出市の観光協会が事務局を名乗り出てくれて、もう、大感謝。
毎月第3土曜日、1,500円もらってやってるんですが、3年やってると、商店主さんが自分の店を説明してくれるようになったり、街歩きのマップを持って、自分でレンタサイクルを借りてまわってる人を見かけるようになったり。
坂出市、行政以外のイベントは、ほとんどなかったんですが、街歩きも31回やってきてます。
「久米通賢先生旧宅で話す機会をいただいて光栄」
「商工会議所がこんなことやってるなんて、変わってるでしょ」と言われましたが、いやもう。
何もないところから始めて、ユーストリーム配信186回とか、街歩きは、申し込みが0人の時もあるけど、めげずに続けてるとか、ムリにお願いしないようにしてる。断られた時に凹むからとか、ノウハウが凝縮されてます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて、これで第3回目のプログラムは終了したんですが、実は、ココからまさかのヒートアップがおこります。
その火付け役は、講座の最後を締めた眞鍋副塾長の言葉。
「今回、すばらしかったのはNさん。前回、“やってみる”と言ってたことを実行されてます。
みんな“迷走してる”と言ってるけど、誰も迷走なんかしてません。
“迷走してる”と言って、やらない言い訳をつくってるだけです。
やりましょう。小さくて良いから、とにかく、やりましょう。」
この日は寒波に襲われた寒い日だったんですが、眞鍋さんのエールを受けて、女性陣が肩を組んで円陣をつくり「オー」とやりだしたり、
(↑写真がないのが残念…)
不思議な熱気に包まれ、会場の古民家、温度が上がった気がします。
そして、懇親会場の「やしま第一健康ランド」へ。

中央左が、やしま第一健康ランドを運営されている株式会社オアシスの巴山(はやま)社長。
その隣、中央右が矢田ママ。
おいしい料理やお菓子を食べて、飲みながら、尾野塾長と矢田ママが塾生の話を個別に聞いて、グループワークが続きます。
懇親会の途中で、1人1人がコメントしたのですが、ここでの矢田ママのコメント。
「皆さん、恥ずかしがらずにやりましょう。“こころのパンツ”を脱ぎましょう!」
これを受けて、「私、こころのパンツを脱ぐ」、「私もパンツ脱ぐ」と大騒ぎに。
懇親会の出席者、ほとんどが30歳代の女性なんですが、“こころのパンツを脱ぐ”で大ヒートアップ。
後日、矢田ママに「こころのパンツ」解説を書いてもらった塾生がいますので、ご紹介。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先日の懇親会で話題になった、「こころのパンツ」
矢田ママにお願いして、解説文書いてもらっちゃいました
そりゃ、また聞きより、矢田ママの言葉をダイレクトに受け取りたいでしょ?
以下、原文です。
「頭で考えすぎたり、うまくやろうとするんじゃなくて
子どもみたいに、まっすぐに、ひたむきに楽しんで、そして一生懸命に、やる
大人はこれを忘れがちですが、ようは、自分がこの大人特有の着物を脱ぎ捨てられるか、
カッコ悪いのが、実は一番かっこいい
になれるかどうか
こころのパンツを脱げるかどうか
が、道が開けるかと大きく関係してます」
お忙しいところ、依頼してすぐに返信をくださった矢田ママに感謝です。
ありがとうございます❤︎
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
矢田ママ、本当にありがとうございます。
そして最後、塾生の方のコメントを紹介させていただき、終わりにします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
塾ではポンさんに諭され、怖がらず行動に出んとあかんな!と。
親睦会では矢田ママに、さくらも使ったらええし、パクったらええんや!
最初はそんなんでかまわん。なるようになるって背中を押してもらい、
マジでパンツ脱いで頑張ろうと思いました!
まずはやってみることが大事なんですよね!
最初から完璧なものをしようと思わなくても、結果はその後についてくるし、
それをベースに修正して理想に近付けていけばいいんですよね!
年下なのに、矢田ママに思わずおかん!と呼びたくなるくらい(笑)、心強かったです!
人見さん、色々お世話になります!よろしくお願いしますm(_ _)m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

文:本山&川井(四国経済産業局)と、塾生の皆さま
全6回の講座ですが、最終回は発表会ですから、今回、早くも折り返し点を迎えたことになります。早いなぁ。
第3回の会場は「四国村、久米通賢先生旧宅」。


四国村の正式名称は「四国民家博物館」。
四国各地から古い民家を移築復原した野外博物館。
体験学習の場であり、大人の観光スポットとご紹介いただきました。

四国村を運営している「公益財団法人 四国民家博物館」の門脇さん。
民間施設だということに、驚きの声も。
さて、本日のゲストは「矢田明子」さん。通称、矢田ママ。
「NPO法人おっちラボ」(島根県雲南市)の代表理事であり、
病院の保健師さんであり、
3人の子どもを持つお母さん。
今回の「地域づくりチャレンジ塾」の先駆けとなっているのは、島根県雲南市の「幸雲南塾」ですが、矢田ママは、幸雲南塾の第1期生(2011年)であり、受講をキッカケに、「おっちラボ」を立ち上げ、若者のチャレンジを応援しつつ、幸雲南塾では第3期から事務局を担い(それまでの事務局は雲南市役所)、第4期は塾長も務めている。
そんな方。
我々の塾の先進であるとともに、塾生を含めた我々全員の先輩です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
矢田 明子さん<特定非営利活動法人おっちラボ 代表理事>
「おっちラボ」のことと、「矢田ママ」ご自身のことについて、お話しいただきました。

矢田ママ、新婚旅行で四国に来られたそうで、旦那さんが大のうどん好き。
香川に滞在した数日間に、何十軒ものうどん屋へ行っていて、
もちろん、四国村のわら家へも来られているそう。
~おっちラボのこと~
島根県雲南市で開催されている幸雲南塾のOBらを中心に、若者チャレンジをサポートする組織として立ち上げ。
現在は、幸雲南塾の運営や、塾生OBらの地域づくりに携わる活動の支援を実施。
ということですが、雲南市の人口(約4万人)に対して塾生OBは63人と、まだまだ力不足だそうで(←63人の集団が生まれてるってスゴイと思いますが…)、地域の人たちをいかに巻き込んでいくかが課題。
塾生OBと地域とのマッチング、特に、市内に43ある地域自治組織とのマッチングを行っているそうで、例えば、鳥獣害対策支援の経験を活かそうと受講し、「ケモノにまけんもの」というマイプランをつくった専業主婦の方と、鍋山地区という地域自治組織とをマッチング。その専業主婦の方が、地域のお母さんには、家庭菜園に柵をつけるといったワークショップを行い、地域のお父さんには、狩猟を教えているそうです。
~矢田ママのこと~
3児の子育てをしながら大学に通い、看護学、中でも予防学を学んでいたとき、地域の人の生涯現役活動を応援したいなぁと思い、幸雲南塾に入塾。
コアには、小さな一対一のコミュニティを大切にしたい、元気にしたいという思いがある。
幸雲南塾での、矢田ママのマイプランは「イイトコ発見プロジェクト」。
地域の人が、それぞれ得意なことを楽しくやって元気に長く暮らせるようにしたい、と、おじいちゃん・障がい者・小学生が協働して畑づくりをするなどのイベントを開催。
このプランは現在でも塾生らに引き継がれているそうです。
~高松・塾生からの質問~
Q:おっちラボではどんな勤務体系ですか?
A:矢田ママご自身は「週3日が病院で保健師、その他の日が“おっちラボ”」。
スタッフは、約半数がこのスタイルで、残りの半数(4人)がフルタイムで勤務。
人件費は助成金を活用しているそうです。
Q:財源はどうしているんですか? ~やっぱり一番気になりますよね~
A:県や市からの受託事業のほかに、今、売り出しているのが、大学生の受入研修。
大学生が“おっちラボ”の活動に参加できるプログラムを提示し、大学に予算をつけてもらってます。
具体的には、東京大学や東京薬科大学などの大学生が、地域住民の家に泊まって、日常の活動に密着した研究を行ってもらうようなこと。
また、雲南市でやっている医療の視点の地域マネジメントも、パッケージとしていろいろな地域に売れるようになればいいなと思っています。
~最後に~
とにかく、迷走したり悩んだりしたら、是非、相談してください。
いろんな経験・専門のある人がいるので、解決する方法はきっとあります!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
という、力強いメッセージを受けて、グループワークへ。

聴講に来られた方も、熱心にメモをとられています。
ところで、今回の場所は「久米通賢先生旧宅」。
久米通賢先生(1780-1841)は多才な方ですが、最も有名なのは、塩を、香川県の代表的な産業へと育てられたことでしょうか。
財政難に陥っていた高松藩主(松平頼恕)から財政再建策を頼られ、現在の坂出市の浜に塩田を開発。坂出市の街の基礎を築かれた方。
ということで、坂出商工会議所の吉田さんにお越しいただきました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
吉田 浩城さん<坂出商工会議所 経営指導員>
ターニングポイントは、4年前の「飲み会」。
若い経営者の飲み会で、<駅前で朝市をやったらどうか>という話が出て、やろう、やろうということに。
ところが時期は2月。予算が全くないので、完全な手づくりでやるしかなく、出展や集客の呼びかけも、口コミとユーストリームの配信ぐらいしかできなかった。
ところが、当時、ユーストリーム自体がまだ珍しく、しかも、商工会議所がやってるというので、マスコミが面白がって紹介してくれて。
それで、だんだん広がっていって。
関わってる経営者の店の売上が上がってると、NHKまでやってきて。
4年間やってたら、出展者も41店舗になって、気がついたら186回ユーストリームを配信してるんです。

また、朝市をやり出していた頃、坂出商工会議所が補助金で、“地域資源を使って何かできないか”と調査をやって、塩業で発展した街を学ぼうと、平成24年4月、街歩き「坂出あまからめぐり」がスタート。
朝市をやっていた関係で、若い経営者がガイドしています。
経営者なので、受付とか事務をする人がいないなぁと思っていたら、坂出市の観光協会が事務局を名乗り出てくれて、もう、大感謝。
毎月第3土曜日、1,500円もらってやってるんですが、3年やってると、商店主さんが自分の店を説明してくれるようになったり、街歩きのマップを持って、自分でレンタサイクルを借りてまわってる人を見かけるようになったり。
坂出市、行政以外のイベントは、ほとんどなかったんですが、街歩きも31回やってきてます。
「久米通賢先生旧宅で話す機会をいただいて光栄」
「商工会議所がこんなことやってるなんて、変わってるでしょ」と言われましたが、いやもう。
何もないところから始めて、ユーストリーム配信186回とか、街歩きは、申し込みが0人の時もあるけど、めげずに続けてるとか、ムリにお願いしないようにしてる。断られた時に凹むからとか、ノウハウが凝縮されてます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて、これで第3回目のプログラムは終了したんですが、実は、ココからまさかのヒートアップがおこります。
その火付け役は、講座の最後を締めた眞鍋副塾長の言葉。
「今回、すばらしかったのはNさん。前回、“やってみる”と言ってたことを実行されてます。
みんな“迷走してる”と言ってるけど、誰も迷走なんかしてません。
“迷走してる”と言って、やらない言い訳をつくってるだけです。
やりましょう。小さくて良いから、とにかく、やりましょう。」
この日は寒波に襲われた寒い日だったんですが、眞鍋さんのエールを受けて、女性陣が肩を組んで円陣をつくり「オー」とやりだしたり、
(↑写真がないのが残念…)
不思議な熱気に包まれ、会場の古民家、温度が上がった気がします。
そして、懇親会場の「やしま第一健康ランド」へ。

中央左が、やしま第一健康ランドを運営されている株式会社オアシスの巴山(はやま)社長。
その隣、中央右が矢田ママ。
おいしい料理やお菓子を食べて、飲みながら、尾野塾長と矢田ママが塾生の話を個別に聞いて、グループワークが続きます。
懇親会の途中で、1人1人がコメントしたのですが、ここでの矢田ママのコメント。
「皆さん、恥ずかしがらずにやりましょう。“こころのパンツ”を脱ぎましょう!」
これを受けて、「私、こころのパンツを脱ぐ」、「私もパンツ脱ぐ」と大騒ぎに。
懇親会の出席者、ほとんどが30歳代の女性なんですが、“こころのパンツを脱ぐ”で大ヒートアップ。
後日、矢田ママに「こころのパンツ」解説を書いてもらった塾生がいますので、ご紹介。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先日の懇親会で話題になった、「こころのパンツ」
矢田ママにお願いして、解説文書いてもらっちゃいました
そりゃ、また聞きより、矢田ママの言葉をダイレクトに受け取りたいでしょ?
以下、原文です。
「頭で考えすぎたり、うまくやろうとするんじゃなくて
子どもみたいに、まっすぐに、ひたむきに楽しんで、そして一生懸命に、やる
大人はこれを忘れがちですが、ようは、自分がこの大人特有の着物を脱ぎ捨てられるか、
カッコ悪いのが、実は一番かっこいい
になれるかどうか
こころのパンツを脱げるかどうか
が、道が開けるかと大きく関係してます」
お忙しいところ、依頼してすぐに返信をくださった矢田ママに感謝です。
ありがとうございます❤︎
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
矢田ママ、本当にありがとうございます。
そして最後、塾生の方のコメントを紹介させていただき、終わりにします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
塾ではポンさんに諭され、怖がらず行動に出んとあかんな!と。
親睦会では矢田ママに、さくらも使ったらええし、パクったらええんや!
最初はそんなんでかまわん。なるようになるって背中を押してもらい、
マジでパンツ脱いで頑張ろうと思いました!
まずはやってみることが大事なんですよね!
最初から完璧なものをしようと思わなくても、結果はその後についてくるし、
それをベースに修正して理想に近付けていけばいいんですよね!
年下なのに、矢田ママに思わずおかん!と呼びたくなるくらい(笑)、心強かったです!
人見さん、色々お世話になります!よろしくお願いしますm(_ _)m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
文:本山&川井(四国経済産業局)と、塾生の皆さま
2014年11月20日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」講座2
平成27年3月までの半年間、毎月開催していく高松「地域づくりチャレンジ塾」。
11月15日(土)に、第2回講座が終了しました。
第2回の会場は「相撲場」。
私、高松に相撲場があること自体、知りませんでした。
場所は、香川県営野球場(レクザムスタジアム)がある「香川県総合運動公園」(生島町)の中。
公園とかに時々ある、吹きさらしの土俵をイメージして、
ここ数日、寒い日が続いていたし、寒いだろうな~と思いつつ、着いたら、こんな場所。

屋根と壁がある!
こんな立派な場所だとは思いませんでした(スミマセン…)。
※受講生の中には「国技館」をイメージしていた方がいたらしいです(笑
さて、前回(第1回)は、「My Plan Me!編」ということで、
自分の過去・履歴などを振り返りつつ、「自分はどうしてコレをやりたいのか」を考えました。
今回、第2回は、5W1H。
「なぜ」(自分が行う原動力)、「なに」(を自分はしたいのか)…
という視点で、自分の考えを整理していくことになりました。

左から、尾野塾長、眞鍋副塾長、
地元プレゼンターの「久保 月」さん、
岡山県矢掛町からお越しいただいたプレゼンターの「室 貴由輝」さん、
そして人見コーディネータ。
皆さん、裸足になるか足袋に履きかえられて、土俵に降りられています。

「今日は“どすこい”でいきましょう」と眞鍋副塾長
では当日の模様をご紹介します。
いつものように、内外の方からケーススタディを伺って、それから、グループワークです。
まずは、高松市花園町でセレクトショップ「イクナスギャラリー」をやられている「久保 月」さんから。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
久保 月さん<株式会社tao.(IKUNAS主宰)>
「イクナス」(IKUNAS)というロゴは、逆から読むと「さぬき」(SANUKI)。
地元、讃岐を、「見方を変えたら面白いことになるだろう」というのを核にして、“ずんやり”やってます。
~“ずんやり”(←方言)がわからない方は検索を~
2002年にUターンで帰ってきて、グラフィックデザイン、中でも編集デザインをしていて、
2006年に、自分目線で発信する冊子「イクナス」というリトルプレスをつくったのが発端。
「イクナス」で、面白そう、紹介したいなぁと思って発信したのが、たまたま伝統工芸で。
そしたら、香川って、伝統工芸がいっぱいあって。
また、リトルプレスを見た人が、どこに行けば見られるの? って、問い合わせてくれるので、
「イクナスギャラリー」というセレクトショップを、デザイン事務所の横のスペースに持つことにして。
そしたら、お客さんの“こんなの欲しい”って言う声が聞こえてくるので、
なんとなく、職人さんとお客さんとの間に立つようになって。
<自分たちが考えて、職人さんにつくってもらって、自分たちが売る>という立場になりました。
伝統工芸品、「高い」とか「使い難い」とかって言われるじゃないですか。
じゃあ、実際に使ってもらおうと、
“こんな使い方どうですか”と提案するワークショップとかやるようになって。
そうすると職人さんと連帯関係が生まれてきて、
今は、職人さん、5者が毎月集まる「さぬきざんまい」という寄り合いをやったり、
自分たちイクナスとだけじゃなく、
アイディアを持っているクリエイターと職人さんをつなげる「SANUKISAN(讃岐産)」というマッチング事業もやるようになって。
まぁ、そんなことをやってきてます。

1人では話しにくいからと、人見さんとの対話形式で進行。
人見さん
デザイナーの仕事、お客さんの御用に応えるのが普通だと思いますが、
久保さんは、自分たちが欲しいものを提案して、つくってもらって、世に出している。
これって、大変な苦労があるんじゃないかと思うんですが。
久保さん
私、思考直結型で、スタッフからも「苦労を苦労と思わない」と言われてるんです。“何とかなるやろ”と思って、すぐにやろうとしちゃう。
でも、<目指すところと、自分ができるボーダーとの位置関係>によって、<誰とやるか>というセレクトが必要になるんです。
ココを間違うと面倒なことになる。
自分でやるだけなら、誰でもできるんです。やろうとさえすれば。
そう。皆さん、マンガの「ワンピース」って、ご存じですか?(笑)
最近、はまって、大人買いしちゃったんですけど、
主人公の「ルフィ」、自分勝手で、もう、メチャクチャ。
でも、仲間が多くて、自分ができないことは、できる仲間に任せる、頼る。
ルフィ、すごいっ。私、ルフィになろうと(笑)
よく、<何かをやる時は、人を巻き込もうよ>っていいますけど、
それは、できる人を得ることで、できないことができるようになる、
できるボーダーが上がるということなんですよね。
だから、私、頼れそうな人のアンテナはすっごい張ってます。
眞鍋さん
今後の展開をご紹介ください。
久保さん
未来って、自分一人ではつくれないし、誰にもわからないけど、
自分がやれることを楽しんでやる、そうやって仕掛けることはできますよね。
今、リトルプレスのイクナスは休刊していますけど、
流通がキチッと機能しないと、ものづくりの現場はうまくいかないので、
十年やってきたことを踏まえて、新たに情報発信媒体をつくろうとしています。
眞鍋さん
「作り手」、「使い手」がいるとすれば、「伝え手」ですね。
作り手の後継者不足の課題って、経済的な課題とともに、社会的評価が課題になってると思うんです。「漆器つくってる、カッコいい」っていうような評価。
それは「伝え手」の役割かもしれない。
久保さん
まさにそうです。私は「にぎやかし」と言ってますけど、今、「にぎやかし」の人間が頑張らないといけないと思ってます。
尾野さん
久保さんの立ち位置を考えると、まず「デザイナー」。その中でもニッチな「編集デザイン」。そして、「香川の伝統工芸ものづくりのプロデュース」をやっている。
こういう<3階層>になっているので、とても明確ですね。
私ですと、「古本屋」、その中でも「専門書が専門の古本屋」、そして、「島根の過疎地」でやっているという3階層。
こういう立ち位置、領域になるまで、どのぐらい期間がかかってますか。
久保さん
う~ん、10年ですかねぇ。
私、スタッフのデザイナーには、自分を出したがるなと言ってるんです。
良い場合もあるんですが、自分の引き出しを自分で決めて、可能性を消してしまってるかも知れない。
自分で決めずに、人から“あなたは○○だよね”っていう蓄積をもらいなさい、と言ってます。それを自分に当てはめると、10年ぐらいかかってますね。
~私も10年ですね、と、尾野さん。
思考直結型ですけど、意外と慎重派なんです(笑)
室さん
すごく計画的にやられてると感じました。
それは性格なんでしょうか、それとも、スケジュールとか緻密にたててやられてるんでしょうか。
久保さん
計画性はないです。面白いと思ったことをやってます。
ただ、俯瞰して見るクセはあります。
全体の動きを見て、見てる中に自分もいて、自分の立ち位置を見て確認しています。
今も、話をしながら、皆さんの反応を見て、話を軌道修正しています。
と、淡々と話される久保さん。
ほかにも、受講生から、子育てと仕事の両立など、質問が相次ぎました。
~「淡々とした語り口がツボ」。これは、尾野塾長からの感想です。
続いて、岡山県矢掛町からお越しいただいた室先生。
体育の先生ですが、環境教育、地元の「やかげ学」などをやられていて、
姉妹講座になる岡山県いかさ地域の「いかさ田舎カレッジ」にも関わられています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
室 貴由輝さん(岡山県矢掛町・矢掛中学校主幹教諭)
キッカケは、矢掛商業高校に勤務されていた平成11年。
目を輝かせて川の中の魚を見ている生徒を見た時だそうです。学校では見たことない表情。
それを見て、川を教材にしようとされます。
まず、蛍を養殖し、せっかく育てたんだからと学校で飛ばして、それを鑑賞会にしたら近所の人が大勢来られて。
蛍の養殖では、川の中で育っているところが見えないから、魚の繁殖をやり始めたら、町のポケット水族館とのコラボも始まって。
そしたら、生徒が変わってきているのを実感されていたそうです。
そんな活動をされていた平成16年、高校再編の準備が始まります。
その時、学校独自の教科を設けないかという話が県からあり、
川の教材が良かったから、それなら、社会や理科などいろいろな要素が関係する「環境」を学校設定教科にしようと提案され、そして、実際にやることになります。
ところが、誰もやったことがないので、カリキュラムがない。どう教えたら良いのかわからない。教科書もない。
困って、岡山大学の小野教授にスーパーバイザーをお願いし、教えてもらうことになります。
そこで、教えていただいた一つが、「ESD」。
※ESD:持続発展教育(Education for Sustainable Development)
ESDには、食料問題、環境問題、人権問題、宗教問題などいろいろありますが、
再編後の矢掛高校では、<環境教育を入り口にしたESD>、
持続可能な社会をつくるためにどうしたらいいのか、ということを、環境面から考えるというプログラムを始められます。

具体的には、生徒と視察へ行ったり、フィールドワークを行ったり。
例えば、無人島へ行くと、人がいないのにゴミがいっぱいある。このゴミはどこから来たんだろうと考えるプログラム。
年に一回、どぶ掃除をやって、そして、祭りが行われる。清掃と伝統行事とがセットになっていることを体験するプログラム。
そして、平成22年、環境教育から、地域連携の部分を発展させた「やかげ学」が始まります。
矢掛高校。平成18年に矢掛商業高校と合併して生まれましたが、合併したため、いろんな生徒がいるんです。
卒業して国公立大学に入学する生徒もいれば、就職する生徒もいる。
学力に大きな差があり、学校の目標が定まらず、両方から敬遠されるようになってきました。
生徒も、目的意識が希薄な生徒が多かった。
高校再編で新しく誕生したとはいえ、過疎地の高校です。周囲には、総社市や井原市など大きな町がある。いつまでも存続できるとは限らない。
生徒が、町のことを知り、学校外の人と触れあうことで、目標を持てるようになるのではないかと考えたんです。
「やかげ学」は、高校2年生から始まります。
まず、2年生の1学期は、町役場の方から、町のことを学びます。
そして2学期から1年間、地域の施設で実習し、
3年生の12月に、発表します。
実習は、週に2時間。幼稚園や小学校、高齢者施設、農業体験施設などの施設で働きます。
実際に働きながら、自分たちに何ができるかを考えます。
教師は、手分けして、実習先をまわっています。
先輩から後輩へ受け継がれていくので、受け入れ先には、高校生が、毎週、途切れることなく来ることで、喜ばれて、
生徒も、喜ばれることでやる気が出ているようです。
実際に、問題児がチームの中心になって活動したり、
大学卒業後、町に戻ってくる生徒があらわれたりしています。
戻ってきた生徒の中には、「やかげ学」を体験した町外出身の生徒もいます。
町の人たちも、子どもたちが町へ出て行くので、“しがらみ”が出てこない。
大人を巻き込んだまちづくりが、学校とともに生まれはじめていて、
今、矢掛町に、<町の未来を考える場>が生まれつつあると感じているところです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
冒頭、「矢掛でやってきたことは“わらしべ長者”のようなもので、計画性がない」と言われていましたが、なんのなんの。“進化のさま”がすごいです。
尾野さん
ものすごく緻密なプログラムだけど、プランが進化するとシンプルになりますね。
眞鍋さん
まちづくりは人づくりというけど、まさに、人づくりですね。
ところで、どうして、今、中学校の先生なんですか?
(→異動に従っているだけで、どうしてなのかは、室先生も、わからないそうです)
以上、今回も、濃厚なケーススタディを2例、伺わせていただきました。
あとで伺ったら、受講生の皆さんも、かなり刺激を受けられたそうです。
そんな状態で、室先生を含めた3班に分かれてグループワーク。

最後、感想をいただきました。
眞鍋さん
具体化できてる人、結構、いらっしゃいます。
できてる人は、考えるよりも、小さなコトからやってしまいましょう。
室先生
まだ2回目なのに、実現できるプランが多いですね。
やりながら修正していけば良いと思います。



文:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
11月15日(土)に、第2回講座が終了しました。
第2回の会場は「相撲場」。
私、高松に相撲場があること自体、知りませんでした。
場所は、香川県営野球場(レクザムスタジアム)がある「香川県総合運動公園」(生島町)の中。
公園とかに時々ある、吹きさらしの土俵をイメージして、
ここ数日、寒い日が続いていたし、寒いだろうな~と思いつつ、着いたら、こんな場所。

屋根と壁がある!
こんな立派な場所だとは思いませんでした(スミマセン…)。
※受講生の中には「国技館」をイメージしていた方がいたらしいです(笑
さて、前回(第1回)は、「My Plan Me!編」ということで、
自分の過去・履歴などを振り返りつつ、「自分はどうしてコレをやりたいのか」を考えました。
今回、第2回は、5W1H。
「なぜ」(自分が行う原動力)、「なに」(を自分はしたいのか)…
という視点で、自分の考えを整理していくことになりました。

左から、尾野塾長、眞鍋副塾長、
地元プレゼンターの「久保 月」さん、
岡山県矢掛町からお越しいただいたプレゼンターの「室 貴由輝」さん、
そして人見コーディネータ。
皆さん、裸足になるか足袋に履きかえられて、土俵に降りられています。

「今日は“どすこい”でいきましょう」と眞鍋副塾長
では当日の模様をご紹介します。
いつものように、内外の方からケーススタディを伺って、それから、グループワークです。
まずは、高松市花園町でセレクトショップ「イクナスギャラリー」をやられている「久保 月」さんから。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
久保 月さん<株式会社tao.(IKUNAS主宰)>
「イクナス」(IKUNAS)というロゴは、逆から読むと「さぬき」(SANUKI)。
地元、讃岐を、「見方を変えたら面白いことになるだろう」というのを核にして、“ずんやり”やってます。
~“ずんやり”(←方言)がわからない方は検索を~
2002年にUターンで帰ってきて、グラフィックデザイン、中でも編集デザインをしていて、
2006年に、自分目線で発信する冊子「イクナス」というリトルプレスをつくったのが発端。
「イクナス」で、面白そう、紹介したいなぁと思って発信したのが、たまたま伝統工芸で。
そしたら、香川って、伝統工芸がいっぱいあって。
また、リトルプレスを見た人が、どこに行けば見られるの? って、問い合わせてくれるので、
「イクナスギャラリー」というセレクトショップを、デザイン事務所の横のスペースに持つことにして。
そしたら、お客さんの“こんなの欲しい”って言う声が聞こえてくるので、
なんとなく、職人さんとお客さんとの間に立つようになって。
<自分たちが考えて、職人さんにつくってもらって、自分たちが売る>という立場になりました。
伝統工芸品、「高い」とか「使い難い」とかって言われるじゃないですか。
じゃあ、実際に使ってもらおうと、
“こんな使い方どうですか”と提案するワークショップとかやるようになって。
そうすると職人さんと連帯関係が生まれてきて、
今は、職人さん、5者が毎月集まる「さぬきざんまい」という寄り合いをやったり、
自分たちイクナスとだけじゃなく、
アイディアを持っているクリエイターと職人さんをつなげる「SANUKISAN(讃岐産)」というマッチング事業もやるようになって。
まぁ、そんなことをやってきてます。

1人では話しにくいからと、人見さんとの対話形式で進行。
人見さん
デザイナーの仕事、お客さんの御用に応えるのが普通だと思いますが、
久保さんは、自分たちが欲しいものを提案して、つくってもらって、世に出している。
これって、大変な苦労があるんじゃないかと思うんですが。
久保さん
私、思考直結型で、スタッフからも「苦労を苦労と思わない」と言われてるんです。“何とかなるやろ”と思って、すぐにやろうとしちゃう。
でも、<目指すところと、自分ができるボーダーとの位置関係>によって、<誰とやるか>というセレクトが必要になるんです。
ココを間違うと面倒なことになる。
自分でやるだけなら、誰でもできるんです。やろうとさえすれば。
そう。皆さん、マンガの「ワンピース」って、ご存じですか?(笑)
最近、はまって、大人買いしちゃったんですけど、
主人公の「ルフィ」、自分勝手で、もう、メチャクチャ。
でも、仲間が多くて、自分ができないことは、できる仲間に任せる、頼る。
ルフィ、すごいっ。私、ルフィになろうと(笑)
よく、<何かをやる時は、人を巻き込もうよ>っていいますけど、
それは、できる人を得ることで、できないことができるようになる、
できるボーダーが上がるということなんですよね。
だから、私、頼れそうな人のアンテナはすっごい張ってます。
眞鍋さん
今後の展開をご紹介ください。
久保さん
未来って、自分一人ではつくれないし、誰にもわからないけど、
自分がやれることを楽しんでやる、そうやって仕掛けることはできますよね。
今、リトルプレスのイクナスは休刊していますけど、
流通がキチッと機能しないと、ものづくりの現場はうまくいかないので、
十年やってきたことを踏まえて、新たに情報発信媒体をつくろうとしています。
眞鍋さん
「作り手」、「使い手」がいるとすれば、「伝え手」ですね。
作り手の後継者不足の課題って、経済的な課題とともに、社会的評価が課題になってると思うんです。「漆器つくってる、カッコいい」っていうような評価。
それは「伝え手」の役割かもしれない。
久保さん
まさにそうです。私は「にぎやかし」と言ってますけど、今、「にぎやかし」の人間が頑張らないといけないと思ってます。
尾野さん
久保さんの立ち位置を考えると、まず「デザイナー」。その中でもニッチな「編集デザイン」。そして、「香川の伝統工芸ものづくりのプロデュース」をやっている。
こういう<3階層>になっているので、とても明確ですね。
私ですと、「古本屋」、その中でも「専門書が専門の古本屋」、そして、「島根の過疎地」でやっているという3階層。
こういう立ち位置、領域になるまで、どのぐらい期間がかかってますか。
久保さん
う~ん、10年ですかねぇ。
私、スタッフのデザイナーには、自分を出したがるなと言ってるんです。
良い場合もあるんですが、自分の引き出しを自分で決めて、可能性を消してしまってるかも知れない。
自分で決めずに、人から“あなたは○○だよね”っていう蓄積をもらいなさい、と言ってます。それを自分に当てはめると、10年ぐらいかかってますね。
~私も10年ですね、と、尾野さん。
思考直結型ですけど、意外と慎重派なんです(笑)
室さん
すごく計画的にやられてると感じました。
それは性格なんでしょうか、それとも、スケジュールとか緻密にたててやられてるんでしょうか。
久保さん
計画性はないです。面白いと思ったことをやってます。
ただ、俯瞰して見るクセはあります。
全体の動きを見て、見てる中に自分もいて、自分の立ち位置を見て確認しています。
今も、話をしながら、皆さんの反応を見て、話を軌道修正しています。
と、淡々と話される久保さん。
ほかにも、受講生から、子育てと仕事の両立など、質問が相次ぎました。
~「淡々とした語り口がツボ」。これは、尾野塾長からの感想です。
続いて、岡山県矢掛町からお越しいただいた室先生。
体育の先生ですが、環境教育、地元の「やかげ学」などをやられていて、
姉妹講座になる岡山県いかさ地域の「いかさ田舎カレッジ」にも関わられています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
室 貴由輝さん(岡山県矢掛町・矢掛中学校主幹教諭)
キッカケは、矢掛商業高校に勤務されていた平成11年。
目を輝かせて川の中の魚を見ている生徒を見た時だそうです。学校では見たことない表情。
それを見て、川を教材にしようとされます。
まず、蛍を養殖し、せっかく育てたんだからと学校で飛ばして、それを鑑賞会にしたら近所の人が大勢来られて。
蛍の養殖では、川の中で育っているところが見えないから、魚の繁殖をやり始めたら、町のポケット水族館とのコラボも始まって。
そしたら、生徒が変わってきているのを実感されていたそうです。
そんな活動をされていた平成16年、高校再編の準備が始まります。
その時、学校独自の教科を設けないかという話が県からあり、
川の教材が良かったから、それなら、社会や理科などいろいろな要素が関係する「環境」を学校設定教科にしようと提案され、そして、実際にやることになります。
ところが、誰もやったことがないので、カリキュラムがない。どう教えたら良いのかわからない。教科書もない。
困って、岡山大学の小野教授にスーパーバイザーをお願いし、教えてもらうことになります。
そこで、教えていただいた一つが、「ESD」。
※ESD:持続発展教育(Education for Sustainable Development)
ESDには、食料問題、環境問題、人権問題、宗教問題などいろいろありますが、
再編後の矢掛高校では、<環境教育を入り口にしたESD>、
持続可能な社会をつくるためにどうしたらいいのか、ということを、環境面から考えるというプログラムを始められます。

具体的には、生徒と視察へ行ったり、フィールドワークを行ったり。
例えば、無人島へ行くと、人がいないのにゴミがいっぱいある。このゴミはどこから来たんだろうと考えるプログラム。
年に一回、どぶ掃除をやって、そして、祭りが行われる。清掃と伝統行事とがセットになっていることを体験するプログラム。
そして、平成22年、環境教育から、地域連携の部分を発展させた「やかげ学」が始まります。
矢掛高校。平成18年に矢掛商業高校と合併して生まれましたが、合併したため、いろんな生徒がいるんです。
卒業して国公立大学に入学する生徒もいれば、就職する生徒もいる。
学力に大きな差があり、学校の目標が定まらず、両方から敬遠されるようになってきました。
生徒も、目的意識が希薄な生徒が多かった。
高校再編で新しく誕生したとはいえ、過疎地の高校です。周囲には、総社市や井原市など大きな町がある。いつまでも存続できるとは限らない。
生徒が、町のことを知り、学校外の人と触れあうことで、目標を持てるようになるのではないかと考えたんです。
「やかげ学」は、高校2年生から始まります。
まず、2年生の1学期は、町役場の方から、町のことを学びます。
そして2学期から1年間、地域の施設で実習し、
3年生の12月に、発表します。
実習は、週に2時間。幼稚園や小学校、高齢者施設、農業体験施設などの施設で働きます。
実際に働きながら、自分たちに何ができるかを考えます。
教師は、手分けして、実習先をまわっています。
先輩から後輩へ受け継がれていくので、受け入れ先には、高校生が、毎週、途切れることなく来ることで、喜ばれて、
生徒も、喜ばれることでやる気が出ているようです。
実際に、問題児がチームの中心になって活動したり、
大学卒業後、町に戻ってくる生徒があらわれたりしています。
戻ってきた生徒の中には、「やかげ学」を体験した町外出身の生徒もいます。
町の人たちも、子どもたちが町へ出て行くので、“しがらみ”が出てこない。
大人を巻き込んだまちづくりが、学校とともに生まれはじめていて、
今、矢掛町に、<町の未来を考える場>が生まれつつあると感じているところです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
冒頭、「矢掛でやってきたことは“わらしべ長者”のようなもので、計画性がない」と言われていましたが、なんのなんの。“進化のさま”がすごいです。
尾野さん
ものすごく緻密なプログラムだけど、プランが進化するとシンプルになりますね。
眞鍋さん
まちづくりは人づくりというけど、まさに、人づくりですね。
ところで、どうして、今、中学校の先生なんですか?
(→異動に従っているだけで、どうしてなのかは、室先生も、わからないそうです)
以上、今回も、濃厚なケーススタディを2例、伺わせていただきました。
あとで伺ったら、受講生の皆さんも、かなり刺激を受けられたそうです。
そんな状態で、室先生を含めた3班に分かれてグループワーク。

最後、感想をいただきました。
眞鍋さん
具体化できてる人、結構、いらっしゃいます。
できてる人は、考えるよりも、小さなコトからやってしまいましょう。
室先生
まだ2回目なのに、実現できるプランが多いですね。
やりながら修正していけば良いと思います。



文:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
2014年11月04日
地域づくりチャレンジ塾(講座1)に参加して
今回初めて地域づくり塾に参加しました。自分の地域活性化のプランを発表する場という事で、貴重な機会に感謝するとともに、とても緊張して臨んだのが本音です。(笑)
社会人の方々の前で発表することだけでも緊張しますが、自分の想いを発表するとなると不安はさらに広がります。自分の想いに対して自信を持てないからです。
実際のチャレンジ塾の場に参加してみると不思議と、怖じける想いよりチャレンジしてみよう!というやる気が勝りました。お寺の中という、開放的な空間も一因だったと思います。でもそれ以上に、参加者全員が共通意識として持っていた、「やってみよう!」のチャレンジ精神が場を包み込んでいて、それに自分の背中を押してもらえたのが大きかったと思います。自分のプランが否定されない空気があったからこそ、慣れない自分でも意見を熱く語ることが出来ました。発表し終わった後の清涼感と、自分の想いの熱さを感じられた経験は大きかったです。
これからの地域チャレンジ塾で、自分のプランがどこまで形作られていくのか、すごく楽しみです。

(文 松本 康作)
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」について

社会人の方々の前で発表することだけでも緊張しますが、自分の想いを発表するとなると不安はさらに広がります。自分の想いに対して自信を持てないからです。
実際のチャレンジ塾の場に参加してみると不思議と、怖じける想いよりチャレンジしてみよう!というやる気が勝りました。お寺の中という、開放的な空間も一因だったと思います。でもそれ以上に、参加者全員が共通意識として持っていた、「やってみよう!」のチャレンジ精神が場を包み込んでいて、それに自分の背中を押してもらえたのが大きかったと思います。自分のプランが否定されない空気があったからこそ、慣れない自分でも意見を熱く語ることが出来ました。発表し終わった後の清涼感と、自分の想いの熱さを感じられた経験は大きかったです。
これからの地域チャレンジ塾で、自分のプランがどこまで形作られていくのか、すごく楽しみです。

(文 松本 康作)
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」について

2014年10月24日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」講座1 イントロダクション
2回のプレセミナーを経て始まりました、地域づくりチャレンジ塾。
10月11日(土)が、その1回目でした。
ことのはじまりは、島根県雲南市が2011年から開催している
地域プロデューサー養成講座『幸雲南塾』。
これが徐々に広がり、2014年度は全国8箇所で開催することに。
高松市も、その1箇所として開催することになりました。
ご応募いただいた塾生は、13人(12組)。
19歳の大学生から57歳の会社員の方まで。平均年齢が37歳。
約半数の方が、働く女性。
そういう皆さんと、これから半年間、自分なりのマイプランを考えていきます。

全国8箇所の塾をやっている尾野塾長(右)と、
地元側(小豆島在住)の眞鍋副塾長(左)
それにしても背景が荘厳。会場のご紹介は後ほど。

第1回のプレゼンターは、写真中央で椅子に座られている3人の方。
左から、地元「仏生山まちプランニングルーム」の“倉橋直嗣さん”と“片山哲也さん”、
そして、高知県室戸市から「(一社)うみ路」の“蜂谷潤さん”にお越しいただきました。
当日のお話、模様をご紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<仏生山まちプランニングルーム>
地元仏生山のプレゼンターは、カフェ経営などを行われている倉橋さんと、IT系の会社にお勤めの片山さんのお2人。
2013年9月、仏生山コミュニティ協議会が、住民から幅広いアイディアを出し合う場をつくった。
仏生山に愛着を持っている人、積極的に発言する人が多いなか、
アイディアを出し合うだけじゃなく、実際にやろう、
役場に頼るんじゃなく自分たちで実現しよう、ということに。
そこで、6人のスタッフによる「仏生山まちプランニングルーム」を立ち上げ、
内外の関心ある人を募って4回のワークショップ(WS)を開催し、
2014年8月に「高松市ゆめづくり推進事業」への応募原案を取りまとめた。
今後の展開として、例えば家具屋さんや大工さんなど町の人に協力いただいて、
みんなで町のベンチづくりをするというWSの企画を進めている。
これからも、楽しみながら町の課題解決をしていきたい。
ということを話されましたが、いきなり、質問が相次ぎます。
Q:立ち上げるの、かなり大変だったと思うんですが、どうやって集めたんですか?
A:カフェに来てた人に声をかけたり、来てくれた元気な人に個別に声をかけて。
Q:6人のスタッフはどんな方がいらっしゃるんですか?
A:金融機関の方、公務員の方、民間企業の方。(皆さん、聴講に来られてました)
Q:巻き込み方、WSのやり方とか、うまいですねぇ。
やってる時、意識してることがあれば教えてください。(by尾野さん)
A:自分が楽しむこと、みんなに楽しんでもらうことでしょうか。
連合自治会単位の活動が重要だと思うんですが、高松市が合併で大きくなり、小回りがききにくくなってるので、こういう活動が必要だと感じてるんです。
Q:そもそも、コミュニティ協議会とか、連合自治会とか、あまり知らないんですけど。
はい、東原次長、出番です。
聴講に来られて、後ろの方で聞かれていた「高松市役所の東原次長さん」へマイクが。

高松市 市民政策局 東原利則次長。予定にないご登壇です。
高松市のコミュニティ制度についてと、地域提案型の補助事業「ゆめづくり推進事業」について説明。

続けて、高松市市民活動センターの吉田センター長が、関連する助成制度を補足紹介すると、
思わぬところから反響が。
「これはスゴイ。小豆島では使えないですか」(小豆島を拠点とする眞鍋副塾長から)
~小豆島を含む高松広域都市圏を対象とする制度もあるそうです。
「高松に拠点がないと使えないんでしょうか」(立て続けに、高知県室戸市を拠点とするプレゼンター蜂谷さんからも 笑)
~こっちは、サスガに難しそう でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<一般社団法人 うみ路>

続いて、室戸市からお越しいただいた、蜂谷潤さん。
岡山市のご出身で、海が好き。海洋研究をやっていて地元に近い高知大学へ進学。
実際に、海に研究フィールドを持つ研究室に入ったら、
そのフィールドが室戸市で、海洋深層水を使ったアワビや海藻養殖の研究をやることになります。
室戸へ通って研究していた蜂谷さん、
考えていたアワビの研究をビジネスプランにまとめ、学生コンテストに応募したら、全国大会で文部科学大臣賞を受賞。
メディアに報道され、地元の人たちの目が、“室戸に来てるよく分かんない大学生”から“室戸のために頑張ってる子”に変わって、気づけば室戸へ移住。
移住後は、地元の人から具体的な課題が聞けるようになり、
大量に捕れるけど鮮度低下が早くて捨てている「ソウダガツオ(メジカ)」をなんとかできないか、と。
地元だけで考えていてもダメだと、室戸外から、料理人、デザイナー、若手社会人を呼んで、漁協の漁師さんと交流したり、
東京の飲食店で、料理してもらったりして、コンフィという調理法と出会い、
ホテルの厨房を借りて、地元のお母さんたちとメジカのコンフィをつくっているそうです。
使ってくれてる料理店へ行って、お客さんが食べてるのを見ると、お母さん、すごい喜んでくれる。
たいしたお金になってないんですけど、目指すところは、売り上げよりも<最大のHAPPY>。
そして、自分のエネルギーは<ワクワクし続ける>こと。
これに<必要とされる>ことが加わって、エネルギーが持続できてるんです。
「地域の課題解決」っていうと、重いじゃないですか。
答えを狙うんじゃなく、自然に生まれてくる<自分やみんなが“ワクワク”すること>をやっています。
と話してくれた蜂谷さん、ほかにも自然発生で、いろいろな事業が動きだしているそうです。
「アワビや海藻の事業化、メジカの利用、お母さんの出番づくりとか、いくつものマイプランのカタマリですね」と、尾野塾長のコメントです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、第1回の会場、高松藩松平家の菩提寺、「法然寺」の本堂をお借りしました。


この後、住職さんにもお話いただき、

後半は、2つのグループに分かれて、グループワーク。
各塾生がマイプランをプレゼンし、グループ毎にディスカッション。

そんな皆さんを見守る、本堂の「葵のご紋」の灯り。
そして交流会へ向かいます。

本堂を出てすぐの交流会場。コチラもお寺の施設をお借りしました。
眞鍋副塾長(右)、人見コーディネータ(左)、大人気。

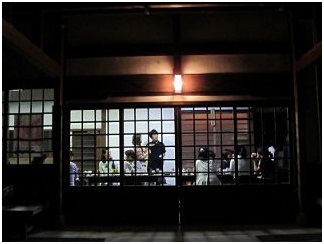
さて、次回(第2回)は11月15日(土)、
5W1Hを意識してマイプランを考えることになりました。
尾野塾長が、次回の案内の時に言われていましたが、
仏生山の皆さんも、室戸の蜂谷さんも同じようなことを言われたように思います。
「地域で何かする」のでなく、「話して反応した人と楽しくやる」(=輪が広がっていく)
でやっていきましょう♪
川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)

10月11日(土)が、その1回目でした。
ことのはじまりは、島根県雲南市が2011年から開催している
地域プロデューサー養成講座『幸雲南塾』。
これが徐々に広がり、2014年度は全国8箇所で開催することに。
高松市も、その1箇所として開催することになりました。
ご応募いただいた塾生は、13人(12組)。
19歳の大学生から57歳の会社員の方まで。平均年齢が37歳。
約半数の方が、働く女性。
そういう皆さんと、これから半年間、自分なりのマイプランを考えていきます。

全国8箇所の塾をやっている尾野塾長(右)と、
地元側(小豆島在住)の眞鍋副塾長(左)
それにしても背景が荘厳。会場のご紹介は後ほど。

第1回のプレゼンターは、写真中央で椅子に座られている3人の方。
左から、地元「仏生山まちプランニングルーム」の“倉橋直嗣さん”と“片山哲也さん”、
そして、高知県室戸市から「(一社)うみ路」の“蜂谷潤さん”にお越しいただきました。
当日のお話、模様をご紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<仏生山まちプランニングルーム>
地元仏生山のプレゼンターは、カフェ経営などを行われている倉橋さんと、IT系の会社にお勤めの片山さんのお2人。
2013年9月、仏生山コミュニティ協議会が、住民から幅広いアイディアを出し合う場をつくった。
仏生山に愛着を持っている人、積極的に発言する人が多いなか、
アイディアを出し合うだけじゃなく、実際にやろう、
役場に頼るんじゃなく自分たちで実現しよう、ということに。
そこで、6人のスタッフによる「仏生山まちプランニングルーム」を立ち上げ、
内外の関心ある人を募って4回のワークショップ(WS)を開催し、
2014年8月に「高松市ゆめづくり推進事業」への応募原案を取りまとめた。
今後の展開として、例えば家具屋さんや大工さんなど町の人に協力いただいて、
みんなで町のベンチづくりをするというWSの企画を進めている。
これからも、楽しみながら町の課題解決をしていきたい。
ということを話されましたが、いきなり、質問が相次ぎます。
Q:立ち上げるの、かなり大変だったと思うんですが、どうやって集めたんですか?
A:カフェに来てた人に声をかけたり、来てくれた元気な人に個別に声をかけて。
Q:6人のスタッフはどんな方がいらっしゃるんですか?
A:金融機関の方、公務員の方、民間企業の方。(皆さん、聴講に来られてました)
Q:巻き込み方、WSのやり方とか、うまいですねぇ。
やってる時、意識してることがあれば教えてください。(by尾野さん)
A:自分が楽しむこと、みんなに楽しんでもらうことでしょうか。
連合自治会単位の活動が重要だと思うんですが、高松市が合併で大きくなり、小回りがききにくくなってるので、こういう活動が必要だと感じてるんです。
Q:そもそも、コミュニティ協議会とか、連合自治会とか、あまり知らないんですけど。
はい、東原次長、出番です。
聴講に来られて、後ろの方で聞かれていた「高松市役所の東原次長さん」へマイクが。

高松市 市民政策局 東原利則次長。予定にないご登壇です。
高松市のコミュニティ制度についてと、地域提案型の補助事業「ゆめづくり推進事業」について説明。

続けて、高松市市民活動センターの吉田センター長が、関連する助成制度を補足紹介すると、
思わぬところから反響が。
「これはスゴイ。小豆島では使えないですか」(小豆島を拠点とする眞鍋副塾長から)
~小豆島を含む高松広域都市圏を対象とする制度もあるそうです。
「高松に拠点がないと使えないんでしょうか」(立て続けに、高知県室戸市を拠点とするプレゼンター蜂谷さんからも 笑)
~こっちは、サスガに難しそう でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<一般社団法人 うみ路>

続いて、室戸市からお越しいただいた、蜂谷潤さん。
岡山市のご出身で、海が好き。海洋研究をやっていて地元に近い高知大学へ進学。
実際に、海に研究フィールドを持つ研究室に入ったら、
そのフィールドが室戸市で、海洋深層水を使ったアワビや海藻養殖の研究をやることになります。
室戸へ通って研究していた蜂谷さん、
考えていたアワビの研究をビジネスプランにまとめ、学生コンテストに応募したら、全国大会で文部科学大臣賞を受賞。
メディアに報道され、地元の人たちの目が、“室戸に来てるよく分かんない大学生”から“室戸のために頑張ってる子”に変わって、気づけば室戸へ移住。
移住後は、地元の人から具体的な課題が聞けるようになり、
大量に捕れるけど鮮度低下が早くて捨てている「ソウダガツオ(メジカ)」をなんとかできないか、と。
地元だけで考えていてもダメだと、室戸外から、料理人、デザイナー、若手社会人を呼んで、漁協の漁師さんと交流したり、
東京の飲食店で、料理してもらったりして、コンフィという調理法と出会い、
ホテルの厨房を借りて、地元のお母さんたちとメジカのコンフィをつくっているそうです。
使ってくれてる料理店へ行って、お客さんが食べてるのを見ると、お母さん、すごい喜んでくれる。
たいしたお金になってないんですけど、目指すところは、売り上げよりも<最大のHAPPY>。
そして、自分のエネルギーは<ワクワクし続ける>こと。
これに<必要とされる>ことが加わって、エネルギーが持続できてるんです。
「地域の課題解決」っていうと、重いじゃないですか。
答えを狙うんじゃなく、自然に生まれてくる<自分やみんなが“ワクワク”すること>をやっています。
と話してくれた蜂谷さん、ほかにも自然発生で、いろいろな事業が動きだしているそうです。
「アワビや海藻の事業化、メジカの利用、お母さんの出番づくりとか、いくつものマイプランのカタマリですね」と、尾野塾長のコメントです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、第1回の会場、高松藩松平家の菩提寺、「法然寺」の本堂をお借りしました。


この後、住職さんにもお話いただき、

後半は、2つのグループに分かれて、グループワーク。
各塾生がマイプランをプレゼンし、グループ毎にディスカッション。

そんな皆さんを見守る、本堂の「葵のご紋」の灯り。
そして交流会へ向かいます。

本堂を出てすぐの交流会場。コチラもお寺の施設をお借りしました。
眞鍋副塾長(右)、人見コーディネータ(左)、大人気。

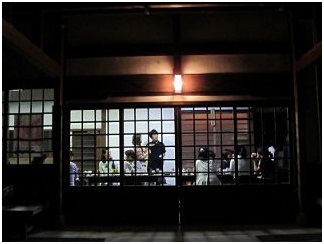
さて、次回(第2回)は11月15日(土)、
5W1Hを意識してマイプランを考えることになりました。
尾野塾長が、次回の案内の時に言われていましたが、
仏生山の皆さんも、室戸の蜂谷さんも同じようなことを言われたように思います。
「地域で何かする」のでなく、「話して反応した人と楽しくやる」(=輪が広がっていく)
でやっていきましょう♪
川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)

2014年09月24日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」プレセミナー(第2回)
「プレセミナー(第2回)」が終了しました。
前回の開催場所は、高松港に近い高松城趾(玉藻公園被雲閣)、
今回の開催場所は、高松港から船に乗って小豆島へ。
高松港のフェリー乗り場に集まり、参加者の皆さんと土庄までフェリーで1時間。
そして、土庄港から一緒に歩いて会場へ。
この日、9月15日(月・祝)は、秋空でしたが日差しが強かった。
でも、会場はリノベーションされた、明治時代の「蔵」。涼しくて快適でした!

会場のMeiPAM(メイパム)
Meiro Performance Art Marche

人見コーディネータの進行で始まりました
では、当日の様子、
(1)講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
(2)プレゼンター(2人)のお話と、講師・会場とのセッション
(3)塾の紹介
の3つにわけてレポートします。
(1) 講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
尾野さん
埼玉県出身です。通販の古本屋をやっています。
2006年、人口3,700人の島根県のまちへ、本社をまるごと移転して活動しています。
この塾は、移住・定住とか、起業とか、そういうのにとらわれないで、いろんな立場の人が気軽に地域にたずさわる。
そんな方法があってもいいんじゃないかと始めた取り組みです。
今日はプレセミナーです。塾でどんなことをやるのか、少しでも感じ取ってもらえればと思います。
*
眞鍋さん
高松市出身です。高校を出て東京でいて、2年半前、「地域おこしを“なりわい”にしよう」と、Uターンじゃなく、ここ、小豆島へ移住しました。
地域資源を使って、何か新しいモノができないか。
ないものねだりではなく、あるもの探しをする。あるものを違うカタチで世に出して、収益が生まれるようにする。そういうことを、常日頃、考えています。
地域づくり。一歩、踏み出したいと思っている人、多いと思います。
その時、ハードルになっているのが、<1人じゃやり方がわからない>と<1人じゃ恥ずかしい>の二つだと感じています。
この塾で、仲間づくりができる。いろんなアイディアが出る中で、自分に近いモノを見つけていける。そんな場ができるよう、お手伝いできればと思っています。
*
眞鍋さん、「もっとしゃべりたいの、グッとガマンした」と笑われていましたが、
お2人には、かなり短時間でお話いただきました。
講師お2人の自己紹介、第1回プレセミナーのレポートでは省略してしまいましたので(~ごめんなさい)、今回、ほぼそのまま、紹介させていただきました。
(2)プレゼンター(2人)のお話
さて、本日のメイン、プレゼンターの登場です。
今回は、このお2人。
*小豆島出身、「醤油ソムリエ」* 黒島慶子さん
*横浜出身、本日の会場「MeiPAM」代表* 磯田周佑さん
人見コーディネータから、
「地元で、地域課題をとらえて活動されているお2人に話をいただきます」とのアナウンスを受けて、まずは、黒島さんから。
○「醤油ソムリエ」黒島さん

仲間から「ケリーちゃん」と呼ばれている、黒島さん
黒島さん
小豆島出身です。
「醤油ソムリエ」として、皆さんから声をかけていただいて活動しています。
「醤油ソムリエ」というのは自称です。結構“うさんくさい”肩書きだと思います。
眞鍋さん
“うさんくさい”って、自分で言っちゃった(笑)
〔醤油ソムリエの仕事〕
いきなり、小豆島の仲間、眞鍋さんから突っ込みがはいりました。
そんな黒島さんの仕事は、醤油の「作り手と使い手をつなぐ」こと。
*“情報発信”。旅館や飲食店に醤油をお薦めしたり、もちろん、雑誌やHPでも。
*“醤油ワークショップ”の開催。あちこちへ行って、醤油の選び方、使い方を知ってもらい、自分好みの醤油を探してもらう。
*その他、レシピ開発、メニュー開発などなど。
「作り手と使い手をつなぐためなら、何だってやります」と話される黒島さん、
活動を始められたのは、大学3回生の時だそうです。
〔キッカケは、芸大の卒業制作〕
絵が好きで、芸術系の大学へ進学し、アート漬けの生活を送っていた大学3回生の時、
これから社会へ出るというのに“このままで良いんだろうか”、悩まれたそうです。
~コレを創ったところでどうなるんだろう。社会に影響を与えてる実感がない。
~ただ、やりたいことをやってるだけ、何の価値もないものを創ってるんじゃないか。
そんなむなしさを感じるようになり、
卒業制作では、<社会の役に立つもの>、<私でないとできない作品>を創ろうと決められます。
〔小豆島と向き合う〕
自分が発想できるもの、表現できるもの、培ってきたもの、体験してきたもの…。
それは、私をつくってくれた小豆島。私のDNAとして根付いているだろう小豆島しかない。
それまで、島を出たい、都会へ行きたいと思っていたけど、
生まれてはじめて小豆島と向き合い、
そして、島の、いろんな人の話を聞きにまわり始めます。
〔小豆島、こんなところです〕
小豆島、結構、広いです。簡単にはまわれません。だから、知らないことも多いんです。
小豆島の産業は加工業が盛んです。
そうめんや醤油は400年前から。最近だと、オリーブや佃煮の加工。
農地が少ないし、水も足りないので、大豆や小麦といった素材が豊富なわけではなくて、
海運で運んできて、加工して、出す。そういう島です。
私は、小豆島の片隅、醤油蔵や佃煮屋さんが軒を連ねる「醤の郷」(ひしおのさと)で生まれ育ちました。
電信柱と同じように醤油蔵の桶があって、醤油の香りがしている「醤の郷」。
親戚にもご近所さんにも、醤油屋さんがいっぱいいます。
〔“醤油”でつなぐ〕
半年間、島のいろんな人の話を聞いてまわった。
楽しい。でも、ピンとこない。
そして、最後、
避けていた醤油蔵、親戚や知り合いが多いので避けていた醤油蔵へ向かいます。
小豆島の全蔵をまわった時、「あぁ、これだ」と思ったと話される黒島さん。
“蔵びと”と話しているとワクワクするんです。
今も、「醤油蔵でいる時が、一番元気だね」って言われます。
ネガティブな話も多いですけど、
醤油という産業を未来へつなげていく、作り手と使い手をつないでいく。
これを、一生の仕事にしようと決めました。
醤油を<選んで>使っている人、ほとんどいないと思うんです。
でも、少しでも知ってもらって、使ってもらえれば。
それが、島の子供たちのためにもなる。そんな想いでやっています。
*
プレゼンが終わると、すぐに、講師とのセッションが始まります。
眞鍋さん
前からケリーちゃんに聞きたかったんだけど、
「醤油ソムリエ」って、それまでなかった仕事じゃないですか。
最初、大変だったと思うんだけど、仕事になりだしたキッカケは何だったんですか。
黒島さん
自分でも、よく仕事が続いてると思いますけど(笑)
私、島に戻ってくるまでの6年間も、ずっと醤油の情報を発信してたんです。
学生時代は、「女子大生が“蔵びと”にはまっている」という記事を書き続け、
卒業後、島外で普通に就職してたんですけど、時間をつくって“蔵びと”を訪ね歩いて、毎月、“蔵びと情報”を出し続け、
勝手に「醤の郷のHP」をつくって、商工会へ「公式HPにしてください」ってお願いに行って。
そんなことしてたら、「なんか変な娘がいる」と面白がられるようになって、
“蔵びと取材”の仕事のオファーが来たりするようになって。
会社に勤めてたから、そんな仕事、受けられないんですけど、「戻ってこい」と言われだしたりして。
それで、島に戻ってきたら、「よく戻ってきた」と面白がって仕事をくれる人がいて。
そんな感じなので、キッカケというと、戻ってくるまでの、学生や会社勤めをやってた6年間でしょうか。
私、情報は持ってるけど、どこにも所属してないフリーランスで、商品すら持ってないんですよね。
だから、何にもとらわれずに動ける、個別の醤油をお薦めできる。
だから、素人が今もやれてるんだと思ってます。
尾野さん
「醤油ソムリエ」って、やりたいことを、誰にでも印象づけられるワンフレーズですよね。こういうフレーズ、大事だけど、つくるのはかなり難しいと思うんです。思いついた“いきさつ”を教えてください。
黒島さん
醤油ソムリエって“うさんくさい”でしょ(会場…笑)
自分で考えたんじゃないんです。周囲の人が呼ぶようになったんです。面白がって。
でも、呼ばれるようになっても、自分では名乗りませんでした。だって、あまりにもおこがましいじゃないですか。
もともと、私、ブログとかにも、自分の名前や顔を出してなかったんです。
オモテに出るのは“蔵びと”だけでいいと思っていて。
ところが、島に戻ってくると、名前が知られはじめて。
ちょうど、小豆島で、醤油サミットが開かれて、
全国のお醤油屋さんが集まるというので、行って、交流会に出て、こんなことやってますと自分がやってることを話して、
「まわりからは“醤油ソムリエ”と呼ばれています」と言ったら、
そこにいた全国のお醤油屋さんが「それ、面白い。名乗れ、名乗れ」、「名刺に“醤油ソムリエ”って書いとけ」、「ブログにも顔出せ」って言われて。
あ、はい、わかりましたと、急遽、名刺に書いて、ブログにも顔出して。
~いわゆる“悪のり”ってやつですね。(by尾野さん)
その後も、講師や会場とか質問が相次ぎましたが、省略させていただいて、
○続いて、「MeiPAM」代表 磯田さん

悪そうに見えるけど、見かけで判断しないように、
と、磯田さん
今日の会場、「MeiPAM」という美術館とカフェを、迷路の街「土庄町」でやっています。
MeiPAMのビジョンは「この街ににぎわいを取り戻す」です。
私は、横浜で生まれ・育ち、2013年4月に小豆島へ移住して来ました。
と話し始められました。
〔競争して大企業へ〕
いわゆる団塊ジュニアの世代。
同世代が多いので、大学進学も、就職も、競争が激しかった時代。
そして、大きな会社に入れば良いという時代。
そんな中、大企業に就職され、ロンドンへ留学、帰国後は会社のメイン部署で働き、
30歳前半で大きなプロジェクトを任されます。
〔何とかしようとMBAへ〕
ところが、失敗。会社に大きな損失を与えてしまったそうです。
落ち込んで、改めて社内を見渡すと、同世代はいっぱいいるし、上もいっぱいいる。
こんな中でやっていかないといけないのか。
人間関係でもつまずいて、このまま働いても、難しいかなと思うようになっていた時、
同期がMBAを取ったというのを聞き、自分も取ろうと、週末、大学へ通い始められます。
〔君は、東京ではコモディティだ〕
MBAで、一つの会社だけで働いていること、なんて意味のないことかと知りました。
その会社で偉くなるためのスキルしか学んでない。
財務諸表も読めないのに、プロジェクトリーダーになって意気揚々としてたし、
浅い仕事しかしてないと痛感しました。
そんなある日、出会った教授に言われたそうです。
「君みたいなのは、東京にはイッパイいる。
そういうの、コモディティって言うんだ。君は、東京ではコモディティだよ」
ガクゼンとしたそうです。そりゃそうでしょうね。
その教授は続けて、
「君は、でかい会社ではやっていけないよ。人間関係とか使いこなせないでしょ。
君みたいなピュアなタイプは、地域へ行きなさい」と。
競争に勝とうとMBAの大学へ来てるのに、「君は地域が良いよ」と言われて…。
全く、飲み込めなかったそうです。

〔地域へ〕
でも、東京。確かに、オレみたいなのはイッパイいるんですよ。電車に乗って見渡すだけでもイッパイいる。
コイツらと競争してるのか。
自分の個性を伸ばすとかじゃなく、ただ、勝つために。
でも、それって、何か変じゃないか。
競争に勝つという気持ちでしか仕事ができなくなっている自分に気がついたそうです。
それで、改めて、地域。日本のあるエリアで起きている問題を考えてみると、
その問題は、将来、必ず、日本全国、東京でも起きる問題。
それを、自分の目で、目の当たりに見て、肌で感じる。
それって、最先端じゃないか。
そう気づいた時、自分の中で文脈がバチンと変わったそうです。
地域の方が良い、地域へ行こう。
〔日本のミニチュア、小豆島〕
そして、縁があって、小豆島に来られた磯田さん。
小豆島。さっき、ケリーちゃんも言ってたけど、加工業が盛んだし。
海、山があって、商業があって、街がある。
東京とかの人は、日本の原風景、農村ってイメージなんだろうけど、違う。
農業の島とかでなく、多様性がある島。まさに、日本の超ミニチュア。
ココで何かの問題解決に向かうことは、今後の日本、20年後の東京につながる。
〔軸〕
ケリーちゃんは「醤油、産業で人をつなぐ」という<軸>を見つけているけど、僕は、まだ、模索していて。
最近、3か月ぐらい前、これが軸になるかなと頭に置いてることは、「小豆島に仕事をつくる」ということ。
土庄高校で話をする機会があって、
高校生に、卒業後、どうするのかって聞いたら、9割が島から出ていくという。
驚いた。
人口減少対策だといって、「移住政策」が盛んにいわれてるけど、
移住って、すごいリスクです。そんな簡単にできるのか。
私は移住者だけど、サラリーマンです。
オリーブオイルの会社に勤めていて、仕事でMeiPAMをやってる。
私は、仕事と地域活性が一体化してるという、非常に恵まれた環境にいるけど、こんな人、ほとんどいないと思う。
移住政策よりも、高校生たちが、ここで学んで、ここで働ける。そういうシステムができないか。
MeiPAMがココにあって、空き家再生プロジェクトみたいなのをやっていて、近くに小学校や高校がある。
そういう場で、人がつながったり、感じたりできないか。
そんなことを軸に、5年10年やってみたいと思っています。
*
眞鍋さん
そうなんですよね。小豆島、高校が2つあって、去年だと、卒業生があわせて239人いて、でも、島に残る卒業生は1割もいない。
19歳で移住してくる人、まず、いないから、小豆島、人口3万人だけど、19歳は20人もいない。そんな状況なんですよ。
でも、高校を卒業して出て行くことが、必ずしも悪いことだとは思わないんですよね。
僕は、出て行かないようにしようというのではなく、
出て行くのは自由だけど、戻ってくる選択肢、働き場をつくることが必要なんじゃないかと思ってるんですが。
磯田さん
そのとおりだと思います。
説明不足だったんですが、気になってるのは、ネガティブに出て行く高校生なんです。
「親が言うから(出て行く)」、「どうせ、島ではやることないから(出て行く)」。
そこを何とかしたいと思ってます。
尾野さん
1年半前に移住してこられて、仕事というか“なりわい”としてMeiPAMとかをやってこられて、つい3か月前ぐらい前に、自分がやりたいことに気づいた。(そうです~磯田さん)
その間、どういう想いで暮らしていましたか。
磯田
東京の生活とのギャップは、すぐには埋まらなくて、体と考え方を慣らせるのに、猶予期間が必要でした。
振り返ると、オリーブの会社で仕事をする中で、小さい企業、地域の企業で働くということをゆっくり感じ取っていったんじゃないかと思います。
そして、見えてきた現実、思いと違ってたこととかが明らかになってきて、
それが一つずつ問題意識になって、
自分とからめた時に、どう解決できるのか。
それを、ここ3か月で考え始めた。そんな状況です。
(3)塾の紹介
最後に塾の紹介を。

尾野さんから塾を紹介
<会場>は、コンクリート禁止にしています。今回の蔵、MeiPAMのように、古くて良いモノを活かすということを意識してやっています。
<今年は全国8箇所>で開催します。東北が2箇所、石川県の七尾市、高松市、岡山県が津山市と笠岡市、そして、島根県が江津市と、最初、2011年に始めた雲南市です。
5回シリーズの講座では<毎回、マイプランを考えます>。そして、6回目に最終発表会をします。
マイプランを考えるために、枠がある資料をお配りしますので、枠に沿って、自分が考えていることを書いて埋めていきます。そして、発表してもらいます。
誰でも発表できます。発表できるよう、我々も全力でサポートします。皆さんの良い話を引き出します。
<毎回、前半は>、地域で活動している方のゲストプレゼンを聞きます。
<後半は>、グループワークとして、自分たちが考えているマイプランを話し、聞いてもらいます。
<夜は>、気楽に、話をしあいます。お酒を飲んで遅くまで話し合う地域もあれば、ノンアルコールでやっている地域もあります。
<視察>に行きます。やろうとしてることに参考になる人を紹介しますので、視察に行って視野を広げます。
<一番の特徴>は、塾が終了した後、起業しなくても良いということです。
起業しなくて良いのですが、4年ぐらいやっているので、これまでに<卒業した塾生の状況>がわかってきはじめました。
まず、10人塾生がいると、マイプランをそのまま実践し続ける方は、1人か2人です。
そのまま実践してはいないけど、マイプランを考えた結果、地域づくりにもっと関わっていきたいと、中間支援機関とか、別のカタチで地域づくりに携わる方が、2~3人でしょうか。
そのほかの方は、そのままですが、他の塾生の活動を手伝ったりして、ゆるく、つながっている人もいます。
今回の高松は1期目ですが、できれば、2期、3期と続いて、20~30人のゆるやかなつながりの輪ができていく。そういう場を見届けたいと思っています。
難易度でいうと、収益計算とかもやらない<簡単な入門編>です。
興味があれば、資金計画とかをやるガチンコの塾はたくさんありますので、紹介します。
<塾への参加方法>は、塾生になる以外に、単発で参加する一般聴講でも参加可能です。
お待ちしています。
尾野さんからの紹介後、人見さん、眞鍋さんからもコメントがありました。
人見さん
この講座は、「意味」を考える講座だと思っています。
意味がわかっていないと、カタチにとらわれがちです。カタチを整えようとします。
この場合の「カタチ」とは、法人格とか団体。
しかし、この講座は、意味をとことん考えます。
従って、終了後、そのまま活動している人は1~2割だけれど、残りの人は、中間支援機関に携わったり、ほかの人の活動を助けたり、自分なりに意味のある活動へと展開しているのだと思います。
自分なりの意味をとことん考える、そんな半年間だと思ってください。
眞鍋さん
今回、はじめて副塾長をやるので、ホットながらも、ちょっと客観的に塾の紹介を聞いてました。
創業セミナーってよくありますよね、商工会議所や会計事務所がよくやってるセミナー。
事業計画・モデルや資金計画をつくるのなら、そういうセミナーの方が優れているのかも知れないですけど、
この塾の特徴は、「近さ」なのかも知れないなと感じました。
まあ、講師だといいながら、2人ともハーフパンツを履いている時点で、近いんですけど(笑)
何でも聞けるのが良いんだと思います。
そして、何回も何回もマイプランを練って、プレゼンするっていうのは、各々が舞台に上がって、各々が当事者になるということ。まさに地域づくりと同じですよね。
そういう機会が用意されているのが、この塾の特徴のような気がします。
そういうところに飛び込んでみたい、仲間入りしたいと思う方は、ぜひ、参加されたら良いんじゃないかと思います。

終了後、大人気の眞鍋さん。
磯田さんに写真を撮ってもらってます。
そして、磯田さんに案内いただき、迷路のまち「土庄」の街歩きへ。
子供たちが元気いっぱい でした。


文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
前回の開催場所は、高松港に近い高松城趾(玉藻公園被雲閣)、
今回の開催場所は、高松港から船に乗って小豆島へ。
高松港のフェリー乗り場に集まり、参加者の皆さんと土庄までフェリーで1時間。
そして、土庄港から一緒に歩いて会場へ。
この日、9月15日(月・祝)は、秋空でしたが日差しが強かった。
でも、会場はリノベーションされた、明治時代の「蔵」。涼しくて快適でした!

会場のMeiPAM(メイパム)
Meiro Performance Art Marche

人見コーディネータの進行で始まりました
では、当日の様子、
(1)講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
(2)プレゼンター(2人)のお話と、講師・会場とのセッション
(3)塾の紹介
の3つにわけてレポートします。
(1) 講師(尾野さん、眞鍋さん)の自己紹介
尾野さん
埼玉県出身です。通販の古本屋をやっています。
2006年、人口3,700人の島根県のまちへ、本社をまるごと移転して活動しています。
この塾は、移住・定住とか、起業とか、そういうのにとらわれないで、いろんな立場の人が気軽に地域にたずさわる。
そんな方法があってもいいんじゃないかと始めた取り組みです。
今日はプレセミナーです。塾でどんなことをやるのか、少しでも感じ取ってもらえればと思います。
*
眞鍋さん
高松市出身です。高校を出て東京でいて、2年半前、「地域おこしを“なりわい”にしよう」と、Uターンじゃなく、ここ、小豆島へ移住しました。
地域資源を使って、何か新しいモノができないか。
ないものねだりではなく、あるもの探しをする。あるものを違うカタチで世に出して、収益が生まれるようにする。そういうことを、常日頃、考えています。
地域づくり。一歩、踏み出したいと思っている人、多いと思います。
その時、ハードルになっているのが、<1人じゃやり方がわからない>と<1人じゃ恥ずかしい>の二つだと感じています。
この塾で、仲間づくりができる。いろんなアイディアが出る中で、自分に近いモノを見つけていける。そんな場ができるよう、お手伝いできればと思っています。
*
眞鍋さん、「もっとしゃべりたいの、グッとガマンした」と笑われていましたが、
お2人には、かなり短時間でお話いただきました。
講師お2人の自己紹介、第1回プレセミナーのレポートでは省略してしまいましたので(~ごめんなさい)、今回、ほぼそのまま、紹介させていただきました。
(2)プレゼンター(2人)のお話
さて、本日のメイン、プレゼンターの登場です。
今回は、このお2人。
*小豆島出身、「醤油ソムリエ」* 黒島慶子さん
*横浜出身、本日の会場「MeiPAM」代表* 磯田周佑さん
人見コーディネータから、
「地元で、地域課題をとらえて活動されているお2人に話をいただきます」とのアナウンスを受けて、まずは、黒島さんから。
○「醤油ソムリエ」黒島さん

仲間から「ケリーちゃん」と呼ばれている、黒島さん
黒島さん
小豆島出身です。
「醤油ソムリエ」として、皆さんから声をかけていただいて活動しています。
「醤油ソムリエ」というのは自称です。結構“うさんくさい”肩書きだと思います。
眞鍋さん
“うさんくさい”って、自分で言っちゃった(笑)
〔醤油ソムリエの仕事〕
いきなり、小豆島の仲間、眞鍋さんから突っ込みがはいりました。
そんな黒島さんの仕事は、醤油の「作り手と使い手をつなぐ」こと。
*“情報発信”。旅館や飲食店に醤油をお薦めしたり、もちろん、雑誌やHPでも。
*“醤油ワークショップ”の開催。あちこちへ行って、醤油の選び方、使い方を知ってもらい、自分好みの醤油を探してもらう。
*その他、レシピ開発、メニュー開発などなど。
「作り手と使い手をつなぐためなら、何だってやります」と話される黒島さん、
活動を始められたのは、大学3回生の時だそうです。
〔キッカケは、芸大の卒業制作〕
絵が好きで、芸術系の大学へ進学し、アート漬けの生活を送っていた大学3回生の時、
これから社会へ出るというのに“このままで良いんだろうか”、悩まれたそうです。
~コレを創ったところでどうなるんだろう。社会に影響を与えてる実感がない。
~ただ、やりたいことをやってるだけ、何の価値もないものを創ってるんじゃないか。
そんなむなしさを感じるようになり、
卒業制作では、<社会の役に立つもの>、<私でないとできない作品>を創ろうと決められます。
〔小豆島と向き合う〕
自分が発想できるもの、表現できるもの、培ってきたもの、体験してきたもの…。
それは、私をつくってくれた小豆島。私のDNAとして根付いているだろう小豆島しかない。
それまで、島を出たい、都会へ行きたいと思っていたけど、
生まれてはじめて小豆島と向き合い、
そして、島の、いろんな人の話を聞きにまわり始めます。
〔小豆島、こんなところです〕
小豆島、結構、広いです。簡単にはまわれません。だから、知らないことも多いんです。
小豆島の産業は加工業が盛んです。
そうめんや醤油は400年前から。最近だと、オリーブや佃煮の加工。
農地が少ないし、水も足りないので、大豆や小麦といった素材が豊富なわけではなくて、
海運で運んできて、加工して、出す。そういう島です。
私は、小豆島の片隅、醤油蔵や佃煮屋さんが軒を連ねる「醤の郷」(ひしおのさと)で生まれ育ちました。
電信柱と同じように醤油蔵の桶があって、醤油の香りがしている「醤の郷」。
親戚にもご近所さんにも、醤油屋さんがいっぱいいます。
〔“醤油”でつなぐ〕
半年間、島のいろんな人の話を聞いてまわった。
楽しい。でも、ピンとこない。
そして、最後、
避けていた醤油蔵、親戚や知り合いが多いので避けていた醤油蔵へ向かいます。
小豆島の全蔵をまわった時、「あぁ、これだ」と思ったと話される黒島さん。
“蔵びと”と話しているとワクワクするんです。
今も、「醤油蔵でいる時が、一番元気だね」って言われます。
ネガティブな話も多いですけど、
醤油という産業を未来へつなげていく、作り手と使い手をつないでいく。
これを、一生の仕事にしようと決めました。
醤油を<選んで>使っている人、ほとんどいないと思うんです。
でも、少しでも知ってもらって、使ってもらえれば。
それが、島の子供たちのためにもなる。そんな想いでやっています。
*
プレゼンが終わると、すぐに、講師とのセッションが始まります。
眞鍋さん
前からケリーちゃんに聞きたかったんだけど、
「醤油ソムリエ」って、それまでなかった仕事じゃないですか。
最初、大変だったと思うんだけど、仕事になりだしたキッカケは何だったんですか。
黒島さん
自分でも、よく仕事が続いてると思いますけど(笑)
私、島に戻ってくるまでの6年間も、ずっと醤油の情報を発信してたんです。
学生時代は、「女子大生が“蔵びと”にはまっている」という記事を書き続け、
卒業後、島外で普通に就職してたんですけど、時間をつくって“蔵びと”を訪ね歩いて、毎月、“蔵びと情報”を出し続け、
勝手に「醤の郷のHP」をつくって、商工会へ「公式HPにしてください」ってお願いに行って。
そんなことしてたら、「なんか変な娘がいる」と面白がられるようになって、
“蔵びと取材”の仕事のオファーが来たりするようになって。
会社に勤めてたから、そんな仕事、受けられないんですけど、「戻ってこい」と言われだしたりして。
それで、島に戻ってきたら、「よく戻ってきた」と面白がって仕事をくれる人がいて。
そんな感じなので、キッカケというと、戻ってくるまでの、学生や会社勤めをやってた6年間でしょうか。
私、情報は持ってるけど、どこにも所属してないフリーランスで、商品すら持ってないんですよね。
だから、何にもとらわれずに動ける、個別の醤油をお薦めできる。
だから、素人が今もやれてるんだと思ってます。
尾野さん
「醤油ソムリエ」って、やりたいことを、誰にでも印象づけられるワンフレーズですよね。こういうフレーズ、大事だけど、つくるのはかなり難しいと思うんです。思いついた“いきさつ”を教えてください。
黒島さん
醤油ソムリエって“うさんくさい”でしょ(会場…笑)
自分で考えたんじゃないんです。周囲の人が呼ぶようになったんです。面白がって。
でも、呼ばれるようになっても、自分では名乗りませんでした。だって、あまりにもおこがましいじゃないですか。
もともと、私、ブログとかにも、自分の名前や顔を出してなかったんです。
オモテに出るのは“蔵びと”だけでいいと思っていて。
ところが、島に戻ってくると、名前が知られはじめて。
ちょうど、小豆島で、醤油サミットが開かれて、
全国のお醤油屋さんが集まるというので、行って、交流会に出て、こんなことやってますと自分がやってることを話して、
「まわりからは“醤油ソムリエ”と呼ばれています」と言ったら、
そこにいた全国のお醤油屋さんが「それ、面白い。名乗れ、名乗れ」、「名刺に“醤油ソムリエ”って書いとけ」、「ブログにも顔出せ」って言われて。
あ、はい、わかりましたと、急遽、名刺に書いて、ブログにも顔出して。
~いわゆる“悪のり”ってやつですね。(by尾野さん)
その後も、講師や会場とか質問が相次ぎましたが、省略させていただいて、
○続いて、「MeiPAM」代表 磯田さん

悪そうに見えるけど、見かけで判断しないように、
と、磯田さん
今日の会場、「MeiPAM」という美術館とカフェを、迷路の街「土庄町」でやっています。
MeiPAMのビジョンは「この街ににぎわいを取り戻す」です。
私は、横浜で生まれ・育ち、2013年4月に小豆島へ移住して来ました。
と話し始められました。
〔競争して大企業へ〕
いわゆる団塊ジュニアの世代。
同世代が多いので、大学進学も、就職も、競争が激しかった時代。
そして、大きな会社に入れば良いという時代。
そんな中、大企業に就職され、ロンドンへ留学、帰国後は会社のメイン部署で働き、
30歳前半で大きなプロジェクトを任されます。
〔何とかしようとMBAへ〕
ところが、失敗。会社に大きな損失を与えてしまったそうです。
落ち込んで、改めて社内を見渡すと、同世代はいっぱいいるし、上もいっぱいいる。
こんな中でやっていかないといけないのか。
人間関係でもつまずいて、このまま働いても、難しいかなと思うようになっていた時、
同期がMBAを取ったというのを聞き、自分も取ろうと、週末、大学へ通い始められます。
〔君は、東京ではコモディティだ〕
MBAで、一つの会社だけで働いていること、なんて意味のないことかと知りました。
その会社で偉くなるためのスキルしか学んでない。
財務諸表も読めないのに、プロジェクトリーダーになって意気揚々としてたし、
浅い仕事しかしてないと痛感しました。
そんなある日、出会った教授に言われたそうです。
「君みたいなのは、東京にはイッパイいる。
そういうの、コモディティって言うんだ。君は、東京ではコモディティだよ」
ガクゼンとしたそうです。そりゃそうでしょうね。
その教授は続けて、
「君は、でかい会社ではやっていけないよ。人間関係とか使いこなせないでしょ。
君みたいなピュアなタイプは、地域へ行きなさい」と。
競争に勝とうとMBAの大学へ来てるのに、「君は地域が良いよ」と言われて…。
全く、飲み込めなかったそうです。

〔地域へ〕
でも、東京。確かに、オレみたいなのはイッパイいるんですよ。電車に乗って見渡すだけでもイッパイいる。
コイツらと競争してるのか。
自分の個性を伸ばすとかじゃなく、ただ、勝つために。
でも、それって、何か変じゃないか。
競争に勝つという気持ちでしか仕事ができなくなっている自分に気がついたそうです。
それで、改めて、地域。日本のあるエリアで起きている問題を考えてみると、
その問題は、将来、必ず、日本全国、東京でも起きる問題。
それを、自分の目で、目の当たりに見て、肌で感じる。
それって、最先端じゃないか。
そう気づいた時、自分の中で文脈がバチンと変わったそうです。
地域の方が良い、地域へ行こう。
〔日本のミニチュア、小豆島〕
そして、縁があって、小豆島に来られた磯田さん。
小豆島。さっき、ケリーちゃんも言ってたけど、加工業が盛んだし。
海、山があって、商業があって、街がある。
東京とかの人は、日本の原風景、農村ってイメージなんだろうけど、違う。
農業の島とかでなく、多様性がある島。まさに、日本の超ミニチュア。
ココで何かの問題解決に向かうことは、今後の日本、20年後の東京につながる。
〔軸〕
ケリーちゃんは「醤油、産業で人をつなぐ」という<軸>を見つけているけど、僕は、まだ、模索していて。
最近、3か月ぐらい前、これが軸になるかなと頭に置いてることは、「小豆島に仕事をつくる」ということ。
土庄高校で話をする機会があって、
高校生に、卒業後、どうするのかって聞いたら、9割が島から出ていくという。
驚いた。
人口減少対策だといって、「移住政策」が盛んにいわれてるけど、
移住って、すごいリスクです。そんな簡単にできるのか。
私は移住者だけど、サラリーマンです。
オリーブオイルの会社に勤めていて、仕事でMeiPAMをやってる。
私は、仕事と地域活性が一体化してるという、非常に恵まれた環境にいるけど、こんな人、ほとんどいないと思う。
移住政策よりも、高校生たちが、ここで学んで、ここで働ける。そういうシステムができないか。
MeiPAMがココにあって、空き家再生プロジェクトみたいなのをやっていて、近くに小学校や高校がある。
そういう場で、人がつながったり、感じたりできないか。
そんなことを軸に、5年10年やってみたいと思っています。
*
眞鍋さん
そうなんですよね。小豆島、高校が2つあって、去年だと、卒業生があわせて239人いて、でも、島に残る卒業生は1割もいない。
19歳で移住してくる人、まず、いないから、小豆島、人口3万人だけど、19歳は20人もいない。そんな状況なんですよ。
でも、高校を卒業して出て行くことが、必ずしも悪いことだとは思わないんですよね。
僕は、出て行かないようにしようというのではなく、
出て行くのは自由だけど、戻ってくる選択肢、働き場をつくることが必要なんじゃないかと思ってるんですが。
磯田さん
そのとおりだと思います。
説明不足だったんですが、気になってるのは、ネガティブに出て行く高校生なんです。
「親が言うから(出て行く)」、「どうせ、島ではやることないから(出て行く)」。
そこを何とかしたいと思ってます。
尾野さん
1年半前に移住してこられて、仕事というか“なりわい”としてMeiPAMとかをやってこられて、つい3か月前ぐらい前に、自分がやりたいことに気づいた。(そうです~磯田さん)
その間、どういう想いで暮らしていましたか。
磯田
東京の生活とのギャップは、すぐには埋まらなくて、体と考え方を慣らせるのに、猶予期間が必要でした。
振り返ると、オリーブの会社で仕事をする中で、小さい企業、地域の企業で働くということをゆっくり感じ取っていったんじゃないかと思います。
そして、見えてきた現実、思いと違ってたこととかが明らかになってきて、
それが一つずつ問題意識になって、
自分とからめた時に、どう解決できるのか。
それを、ここ3か月で考え始めた。そんな状況です。
(3)塾の紹介
最後に塾の紹介を。

尾野さんから塾を紹介
<会場>は、コンクリート禁止にしています。今回の蔵、MeiPAMのように、古くて良いモノを活かすということを意識してやっています。
<今年は全国8箇所>で開催します。東北が2箇所、石川県の七尾市、高松市、岡山県が津山市と笠岡市、そして、島根県が江津市と、最初、2011年に始めた雲南市です。
5回シリーズの講座では<毎回、マイプランを考えます>。そして、6回目に最終発表会をします。
マイプランを考えるために、枠がある資料をお配りしますので、枠に沿って、自分が考えていることを書いて埋めていきます。そして、発表してもらいます。
誰でも発表できます。発表できるよう、我々も全力でサポートします。皆さんの良い話を引き出します。
<毎回、前半は>、地域で活動している方のゲストプレゼンを聞きます。
<後半は>、グループワークとして、自分たちが考えているマイプランを話し、聞いてもらいます。
<夜は>、気楽に、話をしあいます。お酒を飲んで遅くまで話し合う地域もあれば、ノンアルコールでやっている地域もあります。
<視察>に行きます。やろうとしてることに参考になる人を紹介しますので、視察に行って視野を広げます。
<一番の特徴>は、塾が終了した後、起業しなくても良いということです。
起業しなくて良いのですが、4年ぐらいやっているので、これまでに<卒業した塾生の状況>がわかってきはじめました。
まず、10人塾生がいると、マイプランをそのまま実践し続ける方は、1人か2人です。
そのまま実践してはいないけど、マイプランを考えた結果、地域づくりにもっと関わっていきたいと、中間支援機関とか、別のカタチで地域づくりに携わる方が、2~3人でしょうか。
そのほかの方は、そのままですが、他の塾生の活動を手伝ったりして、ゆるく、つながっている人もいます。
今回の高松は1期目ですが、できれば、2期、3期と続いて、20~30人のゆるやかなつながりの輪ができていく。そういう場を見届けたいと思っています。
難易度でいうと、収益計算とかもやらない<簡単な入門編>です。
興味があれば、資金計画とかをやるガチンコの塾はたくさんありますので、紹介します。
<塾への参加方法>は、塾生になる以外に、単発で参加する一般聴講でも参加可能です。
お待ちしています。
尾野さんからの紹介後、人見さん、眞鍋さんからもコメントがありました。
人見さん
この講座は、「意味」を考える講座だと思っています。
意味がわかっていないと、カタチにとらわれがちです。カタチを整えようとします。
この場合の「カタチ」とは、法人格とか団体。
しかし、この講座は、意味をとことん考えます。
従って、終了後、そのまま活動している人は1~2割だけれど、残りの人は、中間支援機関に携わったり、ほかの人の活動を助けたり、自分なりに意味のある活動へと展開しているのだと思います。
自分なりの意味をとことん考える、そんな半年間だと思ってください。
眞鍋さん
今回、はじめて副塾長をやるので、ホットながらも、ちょっと客観的に塾の紹介を聞いてました。
創業セミナーってよくありますよね、商工会議所や会計事務所がよくやってるセミナー。
事業計画・モデルや資金計画をつくるのなら、そういうセミナーの方が優れているのかも知れないですけど、
この塾の特徴は、「近さ」なのかも知れないなと感じました。
まあ、講師だといいながら、2人ともハーフパンツを履いている時点で、近いんですけど(笑)
何でも聞けるのが良いんだと思います。
そして、何回も何回もマイプランを練って、プレゼンするっていうのは、各々が舞台に上がって、各々が当事者になるということ。まさに地域づくりと同じですよね。
そういう機会が用意されているのが、この塾の特徴のような気がします。
そういうところに飛び込んでみたい、仲間入りしたいと思う方は、ぜひ、参加されたら良いんじゃないかと思います。

終了後、大人気の眞鍋さん。
磯田さんに写真を撮ってもらってます。
そして、磯田さんに案内いただき、迷路のまち「土庄」の街歩きへ。
子供たちが元気いっぱい でした。


文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
2014年09月06日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」プレセミナー(第1回)
動きだしました、「地域づくりチャレンジ塾」。
「本講座」は2014年10月11日からの半年間・6回ですが、
「本講座」に先立ち、こんなんしますよという、お披露目の「プレセミナー」を2回やる予定になっていて、
今回、8月24日(日)は、その第1回目。
まさに、最初の一歩(半歩?)です。
会場はJR高松駅前。玉藻公園(高松城跡)の被雲閣(ひうんかく)。国の重要文化財。
この日も暑い夏日でしたが、中に入ると風がとおって気持ちいい。
(↑高松市 市民政策局の城下局長も、挨拶でそうおっしゃられていました)

被雲閣の玄関

玄関には会場の案内が
そして、始まるまではひどく暑かったのですが、途中で夕立のような雨が降って、
終了する頃は雨があがって涼しくなって…。
天候にも恵まれました。
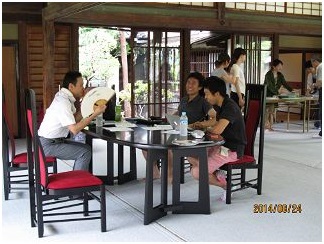
開会前。人見コーディネータ(左)と、<進行役>のお2人、尾野塾長(中)と眞鍋副塾長(右)とが打合せ

冒頭、城下局長からご挨拶を
まず、主催の高松市市民政策局長(城下正寿)より挨拶。
本市は「高松市自治基本条例」に掲げる「市民主体のまちづくり」を図るため、「高松市自治と協働の基本指針」を策定し、それぞれの地域の特性を生かしながら、多様な主体が参画・協働するまちづくりに取り組んでいる。
地域活動の重要性を理解し、地域の課題を解決できる人材の育成が、何より重要。
高松市市民活動センターでまちづくりのリーダー育成に努めるなか、一人でも多くの方が、このチャレンジ塾で学んだことを生かし、地域づくりに向けた、住民自らの実践活動のすそ野が広がっていくことを願っている。
続いて、共催の四国経済産業局産業部長(藤澤清隆)からも挨拶をいただいて。
今回の塾の前身は、島根県雲南市の幸雲南塾。今日、お越しいただいている尾野様が進められ、非常に好評で、全国に広がってきていると聞いている。その一つが高松市。
また、私ども経済産業省が関わっているスタンスは、新しい事業を興す、地域の課題をビジネスの手法で解決するという点。
だけれど、あまりビジネスという出口にとらわれず、気軽に参加いただいて、この塾の特徴、自分が何をやりたいかというところをしっかり固めて欲しい。そして、結果的にビジネスになれば良いし、ならなくても、何らかの気づきになれば、それで十分。
その後、セミナーへ。
まずは進行役のお2人(尾野塾長、眞鍋副塾長)が、ご自身がやられていること、これまでの経緯などを自己紹介。
※お2人のことは、本講座で詳しくご紹介する機会がありますので、今回は、省略(笑)
そして、本日のメイン。
お越しいただいた4人の方々、
地域課題にコミットメントしている皆さん、
無理しない範囲で楽しくやっておられる(と紹介された)4人の方々がご登壇。
ひとことづつ、自己紹介をいただきましたので、そのままご紹介。
~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原さん
~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~ エラリーさん
~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西さん
~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場さん
皆さん、高松市の方なんですが、やってる場所の説明が、
高松、国分寺、香川県、上之町(かみのちょう)と、全員、違ってたりします。

向かって左側が地元の4人、右側が進行役の2人
まず、進行役の方から今日の進め方について、
今日は、10分発表、10分我々(進行役の尾野さん、眞鍋さん)との質疑応答。これを繰り返します。
「本講座」も、こういうやり方です。皆さんに発表してもらい、我々とやりとりする。
これを毎回、繰り返しています。
今日は、「本講座」のグループワークを客席から見てもらえればと思います。
というガイダンスを受けて始まりましたプレセミナー。
ココでは、<お越しいただいた4人の方々のお話>を紹介させていただき、
最後に、尾野塾長が話された<塾の紹介>を書かせていただきます。
では、どうぞ。
<お越しいただいた4人の方々のお話>
(1)トップバッター ~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原あゆみさん。

上原さん。右手に持たれているのが「菓子木型」
〔お父様は「菓子木型」の職人〕
お父様は、「菓子木型」という、和三盆で「お干菓子(おひがし)」をつくる木型づくりの職人さん。四国で1人、全国でも6~7人だそうです。
〔普通に就職〕
でも、そんなことに関係なくすごされ、地元の短大を出て携帯電話会社に就職。当時は、短大→就職→結婚が当たり前だった時代。
その後、ケーキ屋さんで働くものの、お店が廃業。職安で見つけた直島のアートプロジェクトの2日間の仕事へ行き、そのまま、プロジェクトのスタッフに。
〔菓子木型ってスゴイ〕
それまでアートとは無縁だったそうですが、いろんなアート作品を見ているうち、ウチにいっぱいある菓子木型って、かなりアートじゃないか。
と、初めて菓子木型に興味を持ったそうです。
そんな頃、携帯電話のキャラクター「ドコモダケ」のイベントで、お父様がドコモダケの木型を彫って、東京でドコモダケ和三盆を振る舞うことに。
興味を持つようになっていたので、上原さんも一緒に行って…。
そして、菓子木型を使って干菓子をつくるところを、<初めて見た>そうです。
菓子木型はいつも見ていたけど、それを使っているところ、
菓子木型に、和三盆をキュッ、キュッと詰めて、ポンと出す。
キュッ、キュッ、ポン。何これ、スゴイ。感動。
〔これはみんなに知って欲しい〕
家に帰って、自分で菓子木型を使ってお干菓子をつくって、食べてみたら、
口の中でスーっと溶ける。
すごくおいしい。
“できたて”は全然違う。
これはみんなに知って欲しい。
小さい子とか、絶対に喜ぶ。
そして、「そんなん、ムダ」というお父様の反対を押し切って、体験教室を始められたそうです。
〔夢は〕
特に、地元の小学生に、体験して欲しい。知って欲しい。
高松は、お城があるおかげで、工芸品など良いものがいろいろある。
菓子木型を始め、良いものをいっぱい知って、
高松で生まれ育ったことを誇りに思ってもらえるようになって欲しい。そう思ってやっています。
*
と締めくくられた上原さん。
プレゼン後、進行役の方が言われたとおり、「上原さんの原体験、生き方、そして、自分がつくりたい世の中像」までが凝縮された10分間。
お手本のようなお話をいただきました。
(2)お2人目は、~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~
Helary Jean-Christophe さん。フランス出身の方です。

エラリーさん。10分間、正座で話されました。
〔剣道で日本へ〕
パリの近くで生まれたエラリーさん。
大学で出会った「剣道」がとても楽しくて、
剣道やるなら、いつか日本へ行かないといけない。そのためには、日本語を勉強しないと。
専攻を日本語に変えられ(親に内緒だったそう…)、92年、日本に来られました。
〔翻訳業がリーマンショックで、鬱に〕
日本では国際交流の仕事をやられていたそうですが、
組織での仕事がストレスになり、自分のスキルでできる“翻訳業”で独立。
ところが、2008年の秋。
リーマンショックの後、しばらく、仕事が全くなくなった。
子供が3人いるのに、どうしよう。悩んで、鬱病になってしまった そうです…。
〔ライフスタイルを変える〕
翻訳業といっても、下請けの下請けの下請け…。
どこかに頼っていたら振り回される。
自分と全く関係がないところの影響で、自分の仕事が切られて、終わりになる。
そんな生活じゃなく、地元を熱心に見て、その中で自分は何ができるか。
病院の先生に診てもらい、ライフスタイルを変えようと決心されます。
〔クレープ、アート、トラック〕
そして、PTA活動から知り合ったNPOが日曜日にやってる「さぬきマルシェ」に、趣味でクレープ屋さんを出店。
“クレープ”はフランスが発祥。父の出身地、ブルターニュ半島のお菓子。
国分寺の自宅でもクレープ・パーティをやっていた。子供たちとか集まると楽しいでしょ。
自分も子供の頃、人が集まると楽しかったからね。と話すエラリーさん。
次は、地元の国分寺でアート活動がやれないか、考えてるそうです。
高松市の「芸術士がいる保育所」、ああいうの。
お金にならなくても、人の縁が強くなって、そこから何か活動する人がでてきたりということはあるはず。公民館を借りたりしてね。
夢は、トラックの運転手。来月、普通免許を取りに行くことにした。
*
と、流ちょうな日本語で話されるエラリーさん。
「翻訳」と「クレープ」、そして次は、「アート」に「トラック運転手」。
全く違うテーマが出てきたのですが、
「“普段は翻訳、週末はクレープ”。そんな、本業あってのいろいろな週末活動が、これから、地域づくりの一つの主役になるのではないかと感じてます」という進行役の方のコメントに、なるほど。
そして、エラリーさんのクレープ。
お釣りが必要ないようにという、それだけの理由で“500円”。
その代わり500円の価値にするため、材料は香川県産に限定。砂糖は和三盆だし、
果物も自分がおいしいと思う生産者のところへ行って買って、自分でジャムをつくってるそう。
「500円の価値をだそうとしている、立派なビジネスですね」とのコメントが出ると、
「コストも手間もかかる。収入がないと自分が楽しくないので、収入がないならやりたくない。でも、私の中ではビジネスじゃない。趣味」と強調されるエラリーさん。
クレープをやってるのは、自分の原点に戻るため。
剣道も、自分の原点の一つ。
今、45歳になって、自分の子供たちに何を残すか、
地域の人たちに何を残すことができるかをすごく考えている。
ビジネスも考えないといけないけど、ビジネスとして何をするかというよりも、
地元で何ができるかを考えている。
そう語られたエラリーさん でした。
(3)続いては、~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西智都子さん

小西さん。こういう講座、いろいろ受講されたそうです。
〔お父様は郷土出版を〕
実家は印刷会社で、亡くなった父は、鄕土出版をしていた。
“讃岐のため池”とかっていう感じの本。本屋に置かれない本。図書館にしかない本。
子供だった私にとって全く面白くない本ばかりが家にあった。と話される小西さん。
〔地元愛は、全くなかった〕
関西の大学へ進学されますが、当時、地元愛は全くなかったそうで、
関西に残るつもりだったけど、卒業の3日後が、阪神・淡路大震災。
住む家がなくなり、やむなく地元へ戻ってきた。
だけど、落ち着いたら、また、関西へ行くつもりだった。
〔出版社をやりたい…〕
高松では、高松市の女性センターに勤めて、市民活動されてる方と出会ったり、
新聞社で生活情報誌の編集の仕事をしたり。
自分から望んだわけではないけど、地元情報に囲まれて生活。
その後、フリーランスでデザインや編集の仕事をしてる時、
お父様の仕事、“年配の方が自分史を出版する”仕事を手伝うことになります。
月に一回、その年配の方の家へ伺って、半日かけて話を聞き、
帰って原稿にまとめて、翌月、また、話を聞きに伺う、
それを1年やって1冊の本にする。
それまで扱っていた情報と違う、息の長い取材活動。
そういう経験をして、書籍をつくりたい。息長く残っていく書籍づくりをしたい。
そう思うようになったそうです。
でも、香川に、でそういう仕事をくれる出版社はない。
ないなら、自分でそういう出版社をつくりたい…。でも…。
〔できるはずがない〕
出版社に勤めたこともないし、やったこともない。
出版社なんて、できるはずがない。
だから、出版社をやりたいなんて、絶対、クチに出さなかった。
やりたいと思いながら、1人悩んで、今日のような講座に来ていたそうです。
〔やりたいと、人に話した〕
そんな中で出会った講座が転機になります。
その時の、グループ討議のテーマが、<あなたの課題は何ですか?>。
<あなたのやりたいこと>だったら、出版社をやりたいなんて絶対に言わなかったけど、
<あなたの課題>だったので、
「実は…。出版社をしたいんだけど、どうしたらいいかわからないんです」
〔出版社の立ち上げ〕
初めて人に話します。そしたら、一気に加速したそうです。
私、出版社をやりたいと思ってから立ち上げるまで、3~4年かかってるんですが、
人に話したあの講座から、1年足らずで出版社を立ち上げてしまいました。
振り返ったら、いろんな人にキッカケをもらいながらやってきたなぁと思います。
〔大変だけど、楽しい〕
今、「せとうち暮らし」という瀬戸内海の島の雑誌とかをつくってます。
島の取材って、行き来するだけでも時間がかかるし。
全て直販なので、本屋さん、雑貨屋さん、カフェとかへ行って、
こんな本をつくっているんです、置かせてくださいと言って、置かせてもらう。
今回の講座、<気軽に、ムリなく始める>ということですが、私にとっては、気軽じゃないし、ムリしまくり(笑)
でも、楽しいのは間違いないし、やり始めて後悔したことは一度もないですね。
〔目下の夢、宮島~直島をつなぐ〕
そして、お客さんや取材先の方とかが教えてくれるんです。
「せとうち暮らし」。最初は、香川県の有人島24島だけを取材してたんですけど、
しまなみ海道は? 宮島は?
県境なんて関係ないということに気づかせてもらって、取材先を広げはじめてます。
目下の夢は、<広島県の宮島から、香川県の直島までをつなげた観光ルート>をつくれないかということ。
瀬戸内海。全国の人に知って欲しいけど、外国の方にも知って欲しいんです。
まずは、外国の方に人気がある宮島と直島。これを瀬戸内海という海の道でつなぎたい。
すると、その間でいろんなことがおきるんじゃないか。
なぁんてね。たった4年でも、続けていると、こんな次の夢まで見つけてしまうんですね。
*
優しい語り口ですが、強い想いをお話していただいた小西さん。進行役の方から
「フリーペーパーを発行したいという人、結構、多いんですが、
最初、フリーペーパーから入るのでなく、いきなり独立というのはなぜなんですか?」
との質問に、
「亡き父が反面教師になってます」と言われます。
「父は『地元の良いものを残し、人に伝えるべきだ』と言い続けていました。
そして、父の遺言が『間違っても、本を売って儲けようと思うな』(笑)
でも、つくるだけでは届かないんです。
図書館にあっても、本屋とか身近なところになければ人の手に届かない。
届かないと始まらないんです。」
そして、もう一つ、付け加えていただきました。
「売り物にするかしないかで、作り方は大きく違います。
フリーペーパーは主導権が作り手側にあるので、自分たちが伝えたいことをカタチにして、分かってくれる人が分かってくれれば良い。
でも、売り物は主導権が買い手側にあるから、相手を振り向かせなければいけない。
コンテンツにそれだけの魅力が必要。
作り手にそれだけのレベルが必要なんです。
東京の出版社の方と話していると、東京と地方との情報格差って、作り手のレベルの差にもあるという話がよく出ます。
作り手が、せめぎ合いの中でもまれて、成長することが必要なんです。」
また、
「人に話すって大事ですよね。僕のまわりにも、自分1人で考えて、堂々巡りをしてる人は多いです」
とのコメントを受けて。
「本当にそうです。
自分の覚悟ができたし、人や情報は集まりだすし、
話すことで、自分の頭の中が整理できてブラッシュアップする。
逆に、あまりにもリアクションがない時は、練り直さないといけないと気づかせてくれます。
やったことないんだから、材料ないのが当たり前。
材料がないんだから、自分1人で考えていても、しょうがないんですよね。」
と応えていただきました。
(4)最後は、~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場加奈子さん

馬場さん。話すのが苦手と言われてましたが…。
〔陸上、結婚、出産、離婚〕
中学から大学までの10年間、砲丸投げと円盤投げをしていました。
高校3年の国体で優勝、大学では全国大学生選手権で優勝。
インターハイと国体で、香川県の旗手を務めさせていただきました。
これが、人生で最大の自慢。って、これしかないんですけど…。
そして、大学を卒業する時、実業団へは行かず、
<普通の女の子に戻りたい>と、エステで痩身して体重を半分にして。
OLして、結婚して、子供を産んで、離婚して。そして、今に至ります。
~と話し始められた馬場さん。ポツポツと話されますが、すごい です。
〔独立する〕
子供が3人いるので、働かないといけない。
長女が障害を持っているので、シングルマザーでも、自由に動ける状態でないといけない、
そのために、会社経営を学びたい。
そう思って、法人営業の仕事を探し、保険会社で働き始めました。
仕事で会社の社長さんたちに会えるから、会社経営の勉強ができると思って。
そして、給料をもらいながら学ばせてもらって4年経った時、
長女が養護学校へ入学することが決まったので、そろそろ独立しようと思いました。
〔制服のリユース事業〕
簡単にいえば、不要になった制服を買い取り、きれいにして、また、販売する事業。
昔は、隣近所で、お醤油を借り合ったりするのと同じように、制服のやりとりをしていたと思うんです。でも、今は、無くなってきてるんです。
子供の成長は喜ばしいけど、制服や体操着を買い換えると、結構な金額になります。
私、子供を3人抱えて離婚したので、家計のやりくりが大変でした。
当時、リサイクル店ができはじめていた頃だったので、
リサイクル店に、制服を取り扱って欲しいとお願いに行ったんです。
そしたら、良いですねとは言ってくれる。でも、やってくれない。
その翌年、長女が養護学校に入ることになったので、自分でやることにしました。
〔実店舗を持つ〕
最初は店舗を持たずにやってたんですが、利用してくれない。怪しまれたんです。
「学生服の中古品って、何、それ。なんか変なんじゃないか」。
半年たち、これは店舗がないと信用されないと思い、
今の店舗、コトデン「三条駅」の裏に、14坪の小さなお店を開設しました。
そしたら、お母さんの声が「怪しい」から「こんなお店が欲しかった」に変わって。
そして、お母さんの口コミが広がって、メディアの取材も増えて、
「さくらや」という名前が広がりだしました。
〔FCで展開〕
2年目になった時、「かがわ産業支援財団」からビジネスコンペに応募しないかと言われ、応募しました。でも、ビジネスプラン、書いたこともなかったので、1次審査で落ちました。
ところが、その翌年にも声をかけていただいたんです。
今度は、応募用紙に目一杯、思いの丈を書きこんだら、
一次審査どころか、なんと、最優秀賞になり、300万円の賞金をいただくことができたんです。
実は、お金があったら、やりたかったことがあったんです。それは、
<子育てしながら、お母さん1人で仕事ができるシステムをつくって、全国展開すること>。
それで、300万円をもとにPOSレジを開発して。
今年の3月、宇多津に、フランチャイズ1号店ができました。
〔夢〕
制服の洗濯は、クリーニング店だけでなく、障害者施設にも頼んでいます。
体操服のネームの刺繍取りは、地域のおばあちゃんに頼んでいます。
「さくらや」を通じて、地域の高齢者が交流して、お母さんの交流が広がって、
そして、障害者の方ができる仕事を増やしていきたいと思ってやっています。
*
「なんか、聞き入ってしまいました」と、進行役の方。
「“子育てとの両立”で心がけてることってありますか?」の問いかけに、
「店は、週4日、10~15時の短い営業にしています。
これ、子育てと両立してバランスをとるには必要なんです。
『なめとる』と言われることもあるけど、これは変えたくない。
実は、保険会社で法人営業していた時、仕事が楽しくて、夜も遅かったりして、
子育てを放り出してたこともあった。
会社勤めをやめたら、初めて、子供たちがいっぱい話しかけてきて。
その時、こんなに私と関わりたかったんだと気づいたんです。
子育ては限られた年数。これではダメだ。
本当に仕事と子育てが両立できるようにしないといけないと思いました。」
「最後に、これから何かを始めたい人へ、メッセージを。」
「まわりの人に、どんどん聞きに行けばいいと思います。
リユース事業の手続きでは、行政書士に頼むお金がもったいないので、警察の担当の方に何度も相談しましたし、
起業では、帳簿の付け方も何もわからないので、起業してる人にいっぱい聞きに行きました。
今も聞きに行っています。」
「(会場に向かって)今回のプログラムにも、先進事例のインタビューというのがあります。
どんな事業でも、似たような先進事例は必ずあります。聞きに行くことで得るものはたくさんあると思います。」
「そろそろ、休憩しましょう。」
<休 憩>
いやぁ、事務方の身でこんなこと言うのもなんですが、かなり濃い内容でした。
休憩後は、会場を含めた全員でのやりとりもあり、<面白い話>もあったんですが、
そこはちょっとだけの紹介にさせていただき、
最後、進行役、尾野塾長が話された<塾の紹介>を記して終わりにします。
<面白い話>、ちょっとだけの紹介
*尾野さんが、近所の人から夜逃げしてると思われていた話。
*眞鍋さんが、ニューヨークへ行く飛行機が発つ時、なぜか、太平洋沖でカツオ漁船に乗っていた話。
*上原さんの、和三盆がアメリカの税関で麻薬と間違われ、没収された話。
などなど…。
では、塾の紹介を。


<塾の紹介>(尾野塾長から)
仕事と自分がやりたいこと、両方できる 良い時代になってるなぁと思います。
大きな変革をおこすのは大変ですが、今日の皆さんも、小さな変革を確実におこしています。
昔、まちづくりをする人は、政治家、郵便局長、自治会長とかでした。
でも、今は、何でもない個人がスポットライトを浴びるようになっています。
子育てママ、サラリーマン、平日は別のフリーの仕事をしている人、
そんな人が気軽に街に関わる。
そんな人が束になってかかる。
そんな場をつくるのが、今回の塾です。
そして、この塾の最大の特徴は、<起業しなくて良い起業塾>。
半年間受講した後、行動しなくても良いです。
半年間、考えに考え、そして、半年後、“やっぱり違うな”と気づく。
そういう気づきをする人も少なくない。
だから、ムリして行動する必要はないです。
でも、“違うなと気づく”ことで、次のことを考えやすかったりするから、これも大事。
そして、収益計算もしません。
そんな場です。
前身になっている島根県雲南市の塾の卒業生には、郵便局員もいます。
昼間は郵便局員をやっていて、週末、地元の伝統産業を訪ねてつなげ、明宝探訪というスタンプラリーを始めた人もいます。
酒蔵、刃物…。これらの役場の担当は違っていたんですが、彼がスタンプラリーを始めたことで、役場の担当部署の壁がなくなってしまった。
受講している方、雲南市は、平均すると28歳なんですが、学生から58歳までいます。
会社勤め3割、子育てママ2割、仕事探し系・学生2割、後継者や独立・創業希望者2割。
そんな傾向です。
では、お時間がある方、輪になって、交流会にしましょう。


交流会。最初、全員で自己紹介(写真上)、その後は思い思いに(写真下)。
文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
「本講座」は2014年10月11日からの半年間・6回ですが、
「本講座」に先立ち、こんなんしますよという、お披露目の「プレセミナー」を2回やる予定になっていて、
今回、8月24日(日)は、その第1回目。
まさに、最初の一歩(半歩?)です。
会場はJR高松駅前。玉藻公園(高松城跡)の被雲閣(ひうんかく)。国の重要文化財。
この日も暑い夏日でしたが、中に入ると風がとおって気持ちいい。
(↑高松市 市民政策局の城下局長も、挨拶でそうおっしゃられていました)

被雲閣の玄関

玄関には会場の案内が
そして、始まるまではひどく暑かったのですが、途中で夕立のような雨が降って、
終了する頃は雨があがって涼しくなって…。
天候にも恵まれました。
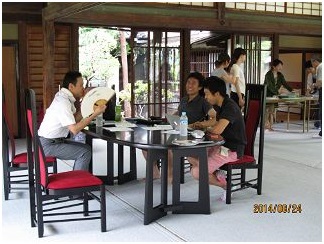
開会前。人見コーディネータ(左)と、<進行役>のお2人、尾野塾長(中)と眞鍋副塾長(右)とが打合せ

冒頭、城下局長からご挨拶を
まず、主催の高松市市民政策局長(城下正寿)より挨拶。
本市は「高松市自治基本条例」に掲げる「市民主体のまちづくり」を図るため、「高松市自治と協働の基本指針」を策定し、それぞれの地域の特性を生かしながら、多様な主体が参画・協働するまちづくりに取り組んでいる。
地域活動の重要性を理解し、地域の課題を解決できる人材の育成が、何より重要。
高松市市民活動センターでまちづくりのリーダー育成に努めるなか、一人でも多くの方が、このチャレンジ塾で学んだことを生かし、地域づくりに向けた、住民自らの実践活動のすそ野が広がっていくことを願っている。
続いて、共催の四国経済産業局産業部長(藤澤清隆)からも挨拶をいただいて。
今回の塾の前身は、島根県雲南市の幸雲南塾。今日、お越しいただいている尾野様が進められ、非常に好評で、全国に広がってきていると聞いている。その一つが高松市。
また、私ども経済産業省が関わっているスタンスは、新しい事業を興す、地域の課題をビジネスの手法で解決するという点。
だけれど、あまりビジネスという出口にとらわれず、気軽に参加いただいて、この塾の特徴、自分が何をやりたいかというところをしっかり固めて欲しい。そして、結果的にビジネスになれば良いし、ならなくても、何らかの気づきになれば、それで十分。
その後、セミナーへ。
まずは進行役のお2人(尾野塾長、眞鍋副塾長)が、ご自身がやられていること、これまでの経緯などを自己紹介。
※お2人のことは、本講座で詳しくご紹介する機会がありますので、今回は、省略(笑)
そして、本日のメイン。
お越しいただいた4人の方々、
地域課題にコミットメントしている皆さん、
無理しない範囲で楽しくやっておられる(と紹介された)4人の方々がご登壇。
ひとことづつ、自己紹介をいただきましたので、そのままご紹介。
~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原さん
~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~ エラリーさん
~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西さん
~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場さん
皆さん、高松市の方なんですが、やってる場所の説明が、
高松、国分寺、香川県、上之町(かみのちょう)と、全員、違ってたりします。

向かって左側が地元の4人、右側が進行役の2人
まず、進行役の方から今日の進め方について、
今日は、10分発表、10分我々(進行役の尾野さん、眞鍋さん)との質疑応答。これを繰り返します。
「本講座」も、こういうやり方です。皆さんに発表してもらい、我々とやりとりする。
これを毎回、繰り返しています。
今日は、「本講座」のグループワークを客席から見てもらえればと思います。
というガイダンスを受けて始まりましたプレセミナー。
ココでは、<お越しいただいた4人の方々のお話>を紹介させていただき、
最後に、尾野塾長が話された<塾の紹介>を書かせていただきます。
では、どうぞ。
<お越しいただいた4人の方々のお話>
(1)トップバッター ~高松で和三盆体験ルーム「豆花」をやってます~ 上原あゆみさん。

上原さん。右手に持たれているのが「菓子木型」
〔お父様は「菓子木型」の職人〕
お父様は、「菓子木型」という、和三盆で「お干菓子(おひがし)」をつくる木型づくりの職人さん。四国で1人、全国でも6~7人だそうです。
〔普通に就職〕
でも、そんなことに関係なくすごされ、地元の短大を出て携帯電話会社に就職。当時は、短大→就職→結婚が当たり前だった時代。
その後、ケーキ屋さんで働くものの、お店が廃業。職安で見つけた直島のアートプロジェクトの2日間の仕事へ行き、そのまま、プロジェクトのスタッフに。
〔菓子木型ってスゴイ〕
それまでアートとは無縁だったそうですが、いろんなアート作品を見ているうち、ウチにいっぱいある菓子木型って、かなりアートじゃないか。
と、初めて菓子木型に興味を持ったそうです。
そんな頃、携帯電話のキャラクター「ドコモダケ」のイベントで、お父様がドコモダケの木型を彫って、東京でドコモダケ和三盆を振る舞うことに。
興味を持つようになっていたので、上原さんも一緒に行って…。
そして、菓子木型を使って干菓子をつくるところを、<初めて見た>そうです。
菓子木型はいつも見ていたけど、それを使っているところ、
菓子木型に、和三盆をキュッ、キュッと詰めて、ポンと出す。
キュッ、キュッ、ポン。何これ、スゴイ。感動。
〔これはみんなに知って欲しい〕
家に帰って、自分で菓子木型を使ってお干菓子をつくって、食べてみたら、
口の中でスーっと溶ける。
すごくおいしい。
“できたて”は全然違う。
これはみんなに知って欲しい。
小さい子とか、絶対に喜ぶ。
そして、「そんなん、ムダ」というお父様の反対を押し切って、体験教室を始められたそうです。
〔夢は〕
特に、地元の小学生に、体験して欲しい。知って欲しい。
高松は、お城があるおかげで、工芸品など良いものがいろいろある。
菓子木型を始め、良いものをいっぱい知って、
高松で生まれ育ったことを誇りに思ってもらえるようになって欲しい。そう思ってやっています。
*
と締めくくられた上原さん。
プレゼン後、進行役の方が言われたとおり、「上原さんの原体験、生き方、そして、自分がつくりたい世の中像」までが凝縮された10分間。
お手本のようなお話をいただきました。
(2)お2人目は、~国分寺で翻訳会社、日曜日、たまにクレープ屋さんをやってます~
Helary Jean-Christophe さん。フランス出身の方です。

エラリーさん。10分間、正座で話されました。
〔剣道で日本へ〕
パリの近くで生まれたエラリーさん。
大学で出会った「剣道」がとても楽しくて、
剣道やるなら、いつか日本へ行かないといけない。そのためには、日本語を勉強しないと。
専攻を日本語に変えられ(親に内緒だったそう…)、92年、日本に来られました。
〔翻訳業がリーマンショックで、鬱に〕
日本では国際交流の仕事をやられていたそうですが、
組織での仕事がストレスになり、自分のスキルでできる“翻訳業”で独立。
ところが、2008年の秋。
リーマンショックの後、しばらく、仕事が全くなくなった。
子供が3人いるのに、どうしよう。悩んで、鬱病になってしまった そうです…。
〔ライフスタイルを変える〕
翻訳業といっても、下請けの下請けの下請け…。
どこかに頼っていたら振り回される。
自分と全く関係がないところの影響で、自分の仕事が切られて、終わりになる。
そんな生活じゃなく、地元を熱心に見て、その中で自分は何ができるか。
病院の先生に診てもらい、ライフスタイルを変えようと決心されます。
〔クレープ、アート、トラック〕
そして、PTA活動から知り合ったNPOが日曜日にやってる「さぬきマルシェ」に、趣味でクレープ屋さんを出店。
“クレープ”はフランスが発祥。父の出身地、ブルターニュ半島のお菓子。
国分寺の自宅でもクレープ・パーティをやっていた。子供たちとか集まると楽しいでしょ。
自分も子供の頃、人が集まると楽しかったからね。と話すエラリーさん。
次は、地元の国分寺でアート活動がやれないか、考えてるそうです。
高松市の「芸術士がいる保育所」、ああいうの。
お金にならなくても、人の縁が強くなって、そこから何か活動する人がでてきたりということはあるはず。公民館を借りたりしてね。
夢は、トラックの運転手。来月、普通免許を取りに行くことにした。
*
と、流ちょうな日本語で話されるエラリーさん。
「翻訳」と「クレープ」、そして次は、「アート」に「トラック運転手」。
全く違うテーマが出てきたのですが、
「“普段は翻訳、週末はクレープ”。そんな、本業あってのいろいろな週末活動が、これから、地域づくりの一つの主役になるのではないかと感じてます」という進行役の方のコメントに、なるほど。
そして、エラリーさんのクレープ。
お釣りが必要ないようにという、それだけの理由で“500円”。
その代わり500円の価値にするため、材料は香川県産に限定。砂糖は和三盆だし、
果物も自分がおいしいと思う生産者のところへ行って買って、自分でジャムをつくってるそう。
「500円の価値をだそうとしている、立派なビジネスですね」とのコメントが出ると、
「コストも手間もかかる。収入がないと自分が楽しくないので、収入がないならやりたくない。でも、私の中ではビジネスじゃない。趣味」と強調されるエラリーさん。
クレープをやってるのは、自分の原点に戻るため。
剣道も、自分の原点の一つ。
今、45歳になって、自分の子供たちに何を残すか、
地域の人たちに何を残すことができるかをすごく考えている。
ビジネスも考えないといけないけど、ビジネスとして何をするかというよりも、
地元で何ができるかを考えている。
そう語られたエラリーさん でした。
(3)続いては、~香川県で小さな出版社「ルーツブックス」をやってます~ 小西智都子さん

小西さん。こういう講座、いろいろ受講されたそうです。
〔お父様は郷土出版を〕
実家は印刷会社で、亡くなった父は、鄕土出版をしていた。
“讃岐のため池”とかっていう感じの本。本屋に置かれない本。図書館にしかない本。
子供だった私にとって全く面白くない本ばかりが家にあった。と話される小西さん。
〔地元愛は、全くなかった〕
関西の大学へ進学されますが、当時、地元愛は全くなかったそうで、
関西に残るつもりだったけど、卒業の3日後が、阪神・淡路大震災。
住む家がなくなり、やむなく地元へ戻ってきた。
だけど、落ち着いたら、また、関西へ行くつもりだった。
〔出版社をやりたい…〕
高松では、高松市の女性センターに勤めて、市民活動されてる方と出会ったり、
新聞社で生活情報誌の編集の仕事をしたり。
自分から望んだわけではないけど、地元情報に囲まれて生活。
その後、フリーランスでデザインや編集の仕事をしてる時、
お父様の仕事、“年配の方が自分史を出版する”仕事を手伝うことになります。
月に一回、その年配の方の家へ伺って、半日かけて話を聞き、
帰って原稿にまとめて、翌月、また、話を聞きに伺う、
それを1年やって1冊の本にする。
それまで扱っていた情報と違う、息の長い取材活動。
そういう経験をして、書籍をつくりたい。息長く残っていく書籍づくりをしたい。
そう思うようになったそうです。
でも、香川に、でそういう仕事をくれる出版社はない。
ないなら、自分でそういう出版社をつくりたい…。でも…。
〔できるはずがない〕
出版社に勤めたこともないし、やったこともない。
出版社なんて、できるはずがない。
だから、出版社をやりたいなんて、絶対、クチに出さなかった。
やりたいと思いながら、1人悩んで、今日のような講座に来ていたそうです。
〔やりたいと、人に話した〕
そんな中で出会った講座が転機になります。
その時の、グループ討議のテーマが、<あなたの課題は何ですか?>。
<あなたのやりたいこと>だったら、出版社をやりたいなんて絶対に言わなかったけど、
<あなたの課題>だったので、
「実は…。出版社をしたいんだけど、どうしたらいいかわからないんです」
〔出版社の立ち上げ〕
初めて人に話します。そしたら、一気に加速したそうです。
私、出版社をやりたいと思ってから立ち上げるまで、3~4年かかってるんですが、
人に話したあの講座から、1年足らずで出版社を立ち上げてしまいました。
振り返ったら、いろんな人にキッカケをもらいながらやってきたなぁと思います。
〔大変だけど、楽しい〕
今、「せとうち暮らし」という瀬戸内海の島の雑誌とかをつくってます。
島の取材って、行き来するだけでも時間がかかるし。
全て直販なので、本屋さん、雑貨屋さん、カフェとかへ行って、
こんな本をつくっているんです、置かせてくださいと言って、置かせてもらう。
今回の講座、<気軽に、ムリなく始める>ということですが、私にとっては、気軽じゃないし、ムリしまくり(笑)
でも、楽しいのは間違いないし、やり始めて後悔したことは一度もないですね。
〔目下の夢、宮島~直島をつなぐ〕
そして、お客さんや取材先の方とかが教えてくれるんです。
「せとうち暮らし」。最初は、香川県の有人島24島だけを取材してたんですけど、
しまなみ海道は? 宮島は?
県境なんて関係ないということに気づかせてもらって、取材先を広げはじめてます。
目下の夢は、<広島県の宮島から、香川県の直島までをつなげた観光ルート>をつくれないかということ。
瀬戸内海。全国の人に知って欲しいけど、外国の方にも知って欲しいんです。
まずは、外国の方に人気がある宮島と直島。これを瀬戸内海という海の道でつなぎたい。
すると、その間でいろんなことがおきるんじゃないか。
なぁんてね。たった4年でも、続けていると、こんな次の夢まで見つけてしまうんですね。
*
優しい語り口ですが、強い想いをお話していただいた小西さん。進行役の方から
「フリーペーパーを発行したいという人、結構、多いんですが、
最初、フリーペーパーから入るのでなく、いきなり独立というのはなぜなんですか?」
との質問に、
「亡き父が反面教師になってます」と言われます。
「父は『地元の良いものを残し、人に伝えるべきだ』と言い続けていました。
そして、父の遺言が『間違っても、本を売って儲けようと思うな』(笑)
でも、つくるだけでは届かないんです。
図書館にあっても、本屋とか身近なところになければ人の手に届かない。
届かないと始まらないんです。」
そして、もう一つ、付け加えていただきました。
「売り物にするかしないかで、作り方は大きく違います。
フリーペーパーは主導権が作り手側にあるので、自分たちが伝えたいことをカタチにして、分かってくれる人が分かってくれれば良い。
でも、売り物は主導権が買い手側にあるから、相手を振り向かせなければいけない。
コンテンツにそれだけの魅力が必要。
作り手にそれだけのレベルが必要なんです。
東京の出版社の方と話していると、東京と地方との情報格差って、作り手のレベルの差にもあるという話がよく出ます。
作り手が、せめぎ合いの中でもまれて、成長することが必要なんです。」
また、
「人に話すって大事ですよね。僕のまわりにも、自分1人で考えて、堂々巡りをしてる人は多いです」
とのコメントを受けて。
「本当にそうです。
自分の覚悟ができたし、人や情報は集まりだすし、
話すことで、自分の頭の中が整理できてブラッシュアップする。
逆に、あまりにもリアクションがない時は、練り直さないといけないと気づかせてくれます。
やったことないんだから、材料ないのが当たり前。
材料がないんだから、自分1人で考えていても、しょうがないんですよね。」
と応えていただきました。
(4)最後は、~上之町で学生服のリユースショップ「さくらや」をやってます~ 馬場加奈子さん

馬場さん。話すのが苦手と言われてましたが…。
〔陸上、結婚、出産、離婚〕
中学から大学までの10年間、砲丸投げと円盤投げをしていました。
高校3年の国体で優勝、大学では全国大学生選手権で優勝。
インターハイと国体で、香川県の旗手を務めさせていただきました。
これが、人生で最大の自慢。って、これしかないんですけど…。
そして、大学を卒業する時、実業団へは行かず、
<普通の女の子に戻りたい>と、エステで痩身して体重を半分にして。
OLして、結婚して、子供を産んで、離婚して。そして、今に至ります。
~と話し始められた馬場さん。ポツポツと話されますが、すごい です。
〔独立する〕
子供が3人いるので、働かないといけない。
長女が障害を持っているので、シングルマザーでも、自由に動ける状態でないといけない、
そのために、会社経営を学びたい。
そう思って、法人営業の仕事を探し、保険会社で働き始めました。
仕事で会社の社長さんたちに会えるから、会社経営の勉強ができると思って。
そして、給料をもらいながら学ばせてもらって4年経った時、
長女が養護学校へ入学することが決まったので、そろそろ独立しようと思いました。
〔制服のリユース事業〕
簡単にいえば、不要になった制服を買い取り、きれいにして、また、販売する事業。
昔は、隣近所で、お醤油を借り合ったりするのと同じように、制服のやりとりをしていたと思うんです。でも、今は、無くなってきてるんです。
子供の成長は喜ばしいけど、制服や体操着を買い換えると、結構な金額になります。
私、子供を3人抱えて離婚したので、家計のやりくりが大変でした。
当時、リサイクル店ができはじめていた頃だったので、
リサイクル店に、制服を取り扱って欲しいとお願いに行ったんです。
そしたら、良いですねとは言ってくれる。でも、やってくれない。
その翌年、長女が養護学校に入ることになったので、自分でやることにしました。
〔実店舗を持つ〕
最初は店舗を持たずにやってたんですが、利用してくれない。怪しまれたんです。
「学生服の中古品って、何、それ。なんか変なんじゃないか」。
半年たち、これは店舗がないと信用されないと思い、
今の店舗、コトデン「三条駅」の裏に、14坪の小さなお店を開設しました。
そしたら、お母さんの声が「怪しい」から「こんなお店が欲しかった」に変わって。
そして、お母さんの口コミが広がって、メディアの取材も増えて、
「さくらや」という名前が広がりだしました。
〔FCで展開〕
2年目になった時、「かがわ産業支援財団」からビジネスコンペに応募しないかと言われ、応募しました。でも、ビジネスプラン、書いたこともなかったので、1次審査で落ちました。
ところが、その翌年にも声をかけていただいたんです。
今度は、応募用紙に目一杯、思いの丈を書きこんだら、
一次審査どころか、なんと、最優秀賞になり、300万円の賞金をいただくことができたんです。
実は、お金があったら、やりたかったことがあったんです。それは、
<子育てしながら、お母さん1人で仕事ができるシステムをつくって、全国展開すること>。
それで、300万円をもとにPOSレジを開発して。
今年の3月、宇多津に、フランチャイズ1号店ができました。
〔夢〕
制服の洗濯は、クリーニング店だけでなく、障害者施設にも頼んでいます。
体操服のネームの刺繍取りは、地域のおばあちゃんに頼んでいます。
「さくらや」を通じて、地域の高齢者が交流して、お母さんの交流が広がって、
そして、障害者の方ができる仕事を増やしていきたいと思ってやっています。
*
「なんか、聞き入ってしまいました」と、進行役の方。
「“子育てとの両立”で心がけてることってありますか?」の問いかけに、
「店は、週4日、10~15時の短い営業にしています。
これ、子育てと両立してバランスをとるには必要なんです。
『なめとる』と言われることもあるけど、これは変えたくない。
実は、保険会社で法人営業していた時、仕事が楽しくて、夜も遅かったりして、
子育てを放り出してたこともあった。
会社勤めをやめたら、初めて、子供たちがいっぱい話しかけてきて。
その時、こんなに私と関わりたかったんだと気づいたんです。
子育ては限られた年数。これではダメだ。
本当に仕事と子育てが両立できるようにしないといけないと思いました。」
「最後に、これから何かを始めたい人へ、メッセージを。」
「まわりの人に、どんどん聞きに行けばいいと思います。
リユース事業の手続きでは、行政書士に頼むお金がもったいないので、警察の担当の方に何度も相談しましたし、
起業では、帳簿の付け方も何もわからないので、起業してる人にいっぱい聞きに行きました。
今も聞きに行っています。」
「(会場に向かって)今回のプログラムにも、先進事例のインタビューというのがあります。
どんな事業でも、似たような先進事例は必ずあります。聞きに行くことで得るものはたくさんあると思います。」
「そろそろ、休憩しましょう。」
<休 憩>
いやぁ、事務方の身でこんなこと言うのもなんですが、かなり濃い内容でした。
休憩後は、会場を含めた全員でのやりとりもあり、<面白い話>もあったんですが、
そこはちょっとだけの紹介にさせていただき、
最後、進行役、尾野塾長が話された<塾の紹介>を記して終わりにします。
<面白い話>、ちょっとだけの紹介
*尾野さんが、近所の人から夜逃げしてると思われていた話。
*眞鍋さんが、ニューヨークへ行く飛行機が発つ時、なぜか、太平洋沖でカツオ漁船に乗っていた話。
*上原さんの、和三盆がアメリカの税関で麻薬と間違われ、没収された話。
などなど…。
では、塾の紹介を。


<塾の紹介>(尾野塾長から)
仕事と自分がやりたいこと、両方できる 良い時代になってるなぁと思います。
大きな変革をおこすのは大変ですが、今日の皆さんも、小さな変革を確実におこしています。
昔、まちづくりをする人は、政治家、郵便局長、自治会長とかでした。
でも、今は、何でもない個人がスポットライトを浴びるようになっています。
子育てママ、サラリーマン、平日は別のフリーの仕事をしている人、
そんな人が気軽に街に関わる。
そんな人が束になってかかる。
そんな場をつくるのが、今回の塾です。
そして、この塾の最大の特徴は、<起業しなくて良い起業塾>。
半年間受講した後、行動しなくても良いです。
半年間、考えに考え、そして、半年後、“やっぱり違うな”と気づく。
そういう気づきをする人も少なくない。
だから、ムリして行動する必要はないです。
でも、“違うなと気づく”ことで、次のことを考えやすかったりするから、これも大事。
そして、収益計算もしません。
そんな場です。
前身になっている島根県雲南市の塾の卒業生には、郵便局員もいます。
昼間は郵便局員をやっていて、週末、地元の伝統産業を訪ねてつなげ、明宝探訪というスタンプラリーを始めた人もいます。
酒蔵、刃物…。これらの役場の担当は違っていたんですが、彼がスタンプラリーを始めたことで、役場の担当部署の壁がなくなってしまった。
受講している方、雲南市は、平均すると28歳なんですが、学生から58歳までいます。
会社勤め3割、子育てママ2割、仕事探し系・学生2割、後継者や独立・創業希望者2割。
そんな傾向です。
では、お時間がある方、輪になって、交流会にしましょう。


交流会。最初、全員で自己紹介(写真上)、その後は思い思いに(写真下)。
文と写真:川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)
2014年08月29日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」 第2回プレセミナー
今年10月から来年3月まで開催する「地域づくりチャレンジ塾」の受講生を募集しています。
まずはプレセミナー(参加無料)を受講してみませんか?
第2回プレセミナーは小豆島で開催! 自らのアイディアを活かし、小豆島の風土や産品の魅力をそれぞれの形で発信している方々の活動を紹介し、また、10月からの本セミナーについても知っていただくことを目的としたプログラムです
日程: 平成26年9月15日(月・祝)
会場: MeiPAM (小豆郡土庄町甲405)
メイン講師:
尾野寛明
((有)エコカレッジ代表取締役、NPO法人てごねっと石見副理事長、NPO法人農家のこせがれネットワーク理事)
真鍋邦大
(㈱459(シマポン)代表取締役社長、ポンカフェオーナー、㈱四国食べる通信代表取締役 兼 編集長)
◆スケジュール◆
13:00 小豆島行フェリー乗り場集合(切符は各自負担)
まずはプレセミナー(参加無料)を受講してみませんか?
第2回プレセミナーは小豆島で開催! 自らのアイディアを活かし、小豆島の風土や産品の魅力をそれぞれの形で発信している方々の活動を紹介し、また、10月からの本セミナーについても知っていただくことを目的としたプログラムです
日程: 平成26年9月15日(月・祝)
会場: MeiPAM (小豆郡土庄町甲405)
メイン講師:
尾野寛明
((有)エコカレッジ代表取締役、NPO法人てごねっと石見副理事長、NPO法人農家のこせがれネットワーク理事)
真鍋邦大
(㈱459(シマポン)代表取締役社長、ポンカフェオーナー、㈱四国食べる通信代表取締役 兼 編集長)
◆スケジュール◆
13:00 小豆島行フェリー乗り場集合(切符は各自負担)
13:40 土庄行フェリー高松発 14時40分土庄着、 徒歩でMeiPAMへ(15分程度)
※雨天や徒歩が難しい方はバス(三都線):ターミナル前 15:05→土庄本町 15:10
15:00 MeiPAM着
15:10-16:10 MeiPAM2 でチャレンジ塾セミナー
16:15-17:00 MeiPAM 「迷路のまち」訪問
徒歩で土庄港フェリー乗り場へ
※バス(西浦線)の場合:土庄本町 17:09→平和の群像 17:13
17:30 土庄発

地元講師:
磯田 周佑 (いそだ しゅうすけ)
1974年 神奈川県横浜市生まれ。 1997年 上智大学経済学部卒業後、KDDI入社。 在職中に多摩大学大学院経営情報学研究科修士課程(MBA)修了し KDDI(株)を退社。2013年4月に小豆島へ移住。 現在、MeiPAM代表を務める他、 豊島オリヴアルス(株)代表取締役、 小豆島ヘルシーランド(株) 地域事業創造部マネージャー、 小豆島 迷路のまち妖怪プロジェクト実行委員会委員長。
黒島慶子(くろしま けいこ)
醤油とオリーブオイルのソムリエ&Webとグラフィックのデザイナー。小豆島の醤油のまちに生まれ、蔵人たちと共に育つ。20歳のときに体温が伝わる醤油を造る職人に惚れ込み、小豆島を拠点に全国の蔵人を訪ね続けては、さまざまな人やコトを結びつけ続けている。
2014年07月31日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」受講生募集
地域で何かやりたいけれど、何をしていいか、
どうすればいいかわからない、という方に。
講師や仲間とともに「マイプラン」を作って、
活動への気持ちを高めていきませんか。
実際に活動をされている先輩との
ネットワークも広がります。
自分のできる活動に、無理のない範囲で
自由に取り組む。
これが、この塾のめざす姿です。
10月から来年3月まで毎月1回(全6回)開催されます。


どうすればいいかわからない、という方に。
講師や仲間とともに「マイプラン」を作って、
活動への気持ちを高めていきませんか。
実際に活動をされている先輩との
ネットワークも広がります。
自分のできる活動に、無理のない範囲で
自由に取り組む。
これが、この塾のめざす姿です。
◆プレセミナー
「がんばれば、わたしもこんなふうに活躍できる!」という
気づきとヒントにみちたトークイベントです。
10月にスタートする本講座についても概要をご説明します。
気づきとヒントにみちたトークイベントです。
10月にスタートする本講座についても概要をご説明します。
| 日時 | 場所 | プレゼンター |
| ①8月24日(日) 13:30~17:00 | 玉藻公園披雲閣 蘇鉄の間 | 上原あゆみ(和三盆体験ルーム豆花店主)エラリー・ジャン=クリストフ(㈱ドゥブレ代表取締役)小西智都子(せとうち暮らし編集長/ルーツブックス代表) 馬場加奈子(学生服リユースshopさくらや/㈱サンクラッド代表) |
| ②9月15日(月・祝) 13:00集合 | 高松港・小豆島行き フェリー内 | 未定(決定次第更新します) 船の中と島がプレセミナー②の舞台です。 |
参加費:無料(入場料等は自己負担)
申し込み:①8月9日(土)まで ②9月2日(火)まで
同実行委員会事務局 (市民活動センター内
℡ 823-2701 FAX 823-2706
℡ 823-2701 FAX 823-2706
e-mail info@flat-takamatsu.net)へ。
http://www.flat-takamatsu.net/bcs/info1704.html
◆マイプランを作る本講座
◆マイプランを作る本講座
10月から来年3月まで毎月1回(全6回)開催されます。
メイン講師:尾野寛明さん
(有限会社エコカレッジ 代表取締役
/NPO 法人てごねっと石見 副理事長
/NPO 法人農家のこせがれネットワーク 理事)
真鍋邦大さん
/NPO 法人てごねっと石見 副理事長
/NPO 法人農家のこせがれネットワーク 理事)
真鍋邦大さん
(株式会社四国食べる通信代表取締役 兼 編集長
/ポンカフェオーナー
/株式会社459(シマポン)代表取締役社長)
/ポンカフェオーナー
/株式会社459(シマポン)代表取締役社長)
【セミナースケジュール】
| 講座① イントロダクション | 10月11 日(土)13:30~17:00 / 仏生山法然寺 |
| 講座② 地域課題を考える | 11月15 日(土)13:30~17:00 |
| 講座③ マイプランを描く | 12月13 日(土)13:30~17:00 |
| 講座④ マイプランを鍛える | 1月17 日(土)13:30~17:00 |
| 講座⑤ マイプランを磨く | 2月7 日(土)13:30~17:00 |
| 講座⑥ マイプランの発表 | 3月14 日(土)13:30~17:00 |
参加費:講座塾生(メイン参加者)5,000円(全6 回分)
講座聴講生(オブザーバー)500円/回
主催:高松市まちづくり学校実行委員会、高松市
共催:四国経済産業局
お問い合わせ先






