2014年10月29日
市民活動団体向けの ブランディング講座~活動の発展を、ブランドの視点から考えてみませんか~
初級編:NPOや市民活動におけるブランディングの意味と役割についての概論
市民活動団体として、次のような悩みを抱えていませんか。
対象としたい人になかなか認知されない。
何をしているのか理解してもらえない。

活動の輪が広がらない。仲間が増えない。
すべて「ブランド」構築の考え方が解決の糸口を握っています。
ブランドという言葉は、企業のみならず、や市民活動団体とも親和性の高いものです。
市民活動団体として、次のような悩みを抱えていませんか。
対象としたい人になかなか認知されない。
何をしているのか理解してもらえない。

活動の輪が広がらない。仲間が増えない。
すべて「ブランド」構築の考え方が解決の糸口を握っています。
ブランドという言葉は、企業のみならず、や市民活動団体とも親和性の高いものです。
その考え方の基礎を学ぶことができる講座です。
開催日時:平成26年12月20日(土)14:00~15:00
開催場所:高松市番町一丁目5-1 四番丁スクエア1F会議室
対 象:市民活動団体、市民活動に関心のある方、
地域コミュニティ協議会など
定 員:25名(先着順)
参 加 費:無料
準 備 物:筆記用具等
申込締切:平成26年12月12日(金)
講 師:クリエイティブ・ディレクター 人見 訓嘉
主 催:高松市市民活動センター
開催日時:平成26年12月20日(土)14:00~15:00
開催場所:高松市番町一丁目5-1 四番丁スクエア1F会議室
対 象:市民活動団体、市民活動に関心のある方、
地域コミュニティ協議会など
定 員:25名(先着順)
参 加 費:無料
準 備 物:筆記用具等
申込締切:平成26年12月12日(金)
講 師:クリエイティブ・ディレクター 人見 訓嘉
主 催:高松市市民活動センター
2014年10月24日
高松市まちづくり学校「地域づくりチャレンジ塾」講座1 イントロダクション
2回のプレセミナーを経て始まりました、地域づくりチャレンジ塾。
10月11日(土)が、その1回目でした。
ことのはじまりは、島根県雲南市が2011年から開催している
地域プロデューサー養成講座『幸雲南塾』。
これが徐々に広がり、2014年度は全国8箇所で開催することに。
高松市も、その1箇所として開催することになりました。
ご応募いただいた塾生は、13人(12組)。
19歳の大学生から57歳の会社員の方まで。平均年齢が37歳。
約半数の方が、働く女性。
そういう皆さんと、これから半年間、自分なりのマイプランを考えていきます。

全国8箇所の塾をやっている尾野塾長(右)と、
地元側(小豆島在住)の眞鍋副塾長(左)
それにしても背景が荘厳。会場のご紹介は後ほど。

第1回のプレゼンターは、写真中央で椅子に座られている3人の方。
左から、地元「仏生山まちプランニングルーム」の“倉橋直嗣さん”と“片山哲也さん”、
そして、高知県室戸市から「(一社)うみ路」の“蜂谷潤さん”にお越しいただきました。
当日のお話、模様をご紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<仏生山まちプランニングルーム>
地元仏生山のプレゼンターは、カフェ経営などを行われている倉橋さんと、IT系の会社にお勤めの片山さんのお2人。
2013年9月、仏生山コミュニティ協議会が、住民から幅広いアイディアを出し合う場をつくった。
仏生山に愛着を持っている人、積極的に発言する人が多いなか、
アイディアを出し合うだけじゃなく、実際にやろう、
役場に頼るんじゃなく自分たちで実現しよう、ということに。
そこで、6人のスタッフによる「仏生山まちプランニングルーム」を立ち上げ、
内外の関心ある人を募って4回のワークショップ(WS)を開催し、
2014年8月に「高松市ゆめづくり推進事業」への応募原案を取りまとめた。
今後の展開として、例えば家具屋さんや大工さんなど町の人に協力いただいて、
みんなで町のベンチづくりをするというWSの企画を進めている。
これからも、楽しみながら町の課題解決をしていきたい。
ということを話されましたが、いきなり、質問が相次ぎます。
Q:立ち上げるの、かなり大変だったと思うんですが、どうやって集めたんですか?
A:カフェに来てた人に声をかけたり、来てくれた元気な人に個別に声をかけて。
Q:6人のスタッフはどんな方がいらっしゃるんですか?
A:金融機関の方、公務員の方、民間企業の方。(皆さん、聴講に来られてました)
Q:巻き込み方、WSのやり方とか、うまいですねぇ。
やってる時、意識してることがあれば教えてください。(by尾野さん)
A:自分が楽しむこと、みんなに楽しんでもらうことでしょうか。
連合自治会単位の活動が重要だと思うんですが、高松市が合併で大きくなり、小回りがききにくくなってるので、こういう活動が必要だと感じてるんです。
Q:そもそも、コミュニティ協議会とか、連合自治会とか、あまり知らないんですけど。
はい、東原次長、出番です。
聴講に来られて、後ろの方で聞かれていた「高松市役所の東原次長さん」へマイクが。

高松市 市民政策局 東原利則次長。予定にないご登壇です。
高松市のコミュニティ制度についてと、地域提案型の補助事業「ゆめづくり推進事業」について説明。

続けて、高松市市民活動センターの吉田センター長が、関連する助成制度を補足紹介すると、
思わぬところから反響が。
「これはスゴイ。小豆島では使えないですか」(小豆島を拠点とする眞鍋副塾長から)
~小豆島を含む高松広域都市圏を対象とする制度もあるそうです。
「高松に拠点がないと使えないんでしょうか」(立て続けに、高知県室戸市を拠点とするプレゼンター蜂谷さんからも 笑)
~こっちは、サスガに難しそう でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<一般社団法人 うみ路>

続いて、室戸市からお越しいただいた、蜂谷潤さん。
岡山市のご出身で、海が好き。海洋研究をやっていて地元に近い高知大学へ進学。
実際に、海に研究フィールドを持つ研究室に入ったら、
そのフィールドが室戸市で、海洋深層水を使ったアワビや海藻養殖の研究をやることになります。
室戸へ通って研究していた蜂谷さん、
考えていたアワビの研究をビジネスプランにまとめ、学生コンテストに応募したら、全国大会で文部科学大臣賞を受賞。
メディアに報道され、地元の人たちの目が、“室戸に来てるよく分かんない大学生”から“室戸のために頑張ってる子”に変わって、気づけば室戸へ移住。
移住後は、地元の人から具体的な課題が聞けるようになり、
大量に捕れるけど鮮度低下が早くて捨てている「ソウダガツオ(メジカ)」をなんとかできないか、と。
地元だけで考えていてもダメだと、室戸外から、料理人、デザイナー、若手社会人を呼んで、漁協の漁師さんと交流したり、
東京の飲食店で、料理してもらったりして、コンフィという調理法と出会い、
ホテルの厨房を借りて、地元のお母さんたちとメジカのコンフィをつくっているそうです。
使ってくれてる料理店へ行って、お客さんが食べてるのを見ると、お母さん、すごい喜んでくれる。
たいしたお金になってないんですけど、目指すところは、売り上げよりも<最大のHAPPY>。
そして、自分のエネルギーは<ワクワクし続ける>こと。
これに<必要とされる>ことが加わって、エネルギーが持続できてるんです。
「地域の課題解決」っていうと、重いじゃないですか。
答えを狙うんじゃなく、自然に生まれてくる<自分やみんなが“ワクワク”すること>をやっています。
と話してくれた蜂谷さん、ほかにも自然発生で、いろいろな事業が動きだしているそうです。
「アワビや海藻の事業化、メジカの利用、お母さんの出番づくりとか、いくつものマイプランのカタマリですね」と、尾野塾長のコメントです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、第1回の会場、高松藩松平家の菩提寺、「法然寺」の本堂をお借りしました。


この後、住職さんにもお話いただき、

後半は、2つのグループに分かれて、グループワーク。
各塾生がマイプランをプレゼンし、グループ毎にディスカッション。

そんな皆さんを見守る、本堂の「葵のご紋」の灯り。
そして交流会へ向かいます。

本堂を出てすぐの交流会場。コチラもお寺の施設をお借りしました。
眞鍋副塾長(右)、人見コーディネータ(左)、大人気。

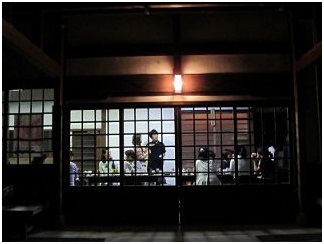
さて、次回(第2回)は11月15日(土)、
5W1Hを意識してマイプランを考えることになりました。
尾野塾長が、次回の案内の時に言われていましたが、
仏生山の皆さんも、室戸の蜂谷さんも同じようなことを言われたように思います。
「地域で何かする」のでなく、「話して反応した人と楽しくやる」(=輪が広がっていく)
でやっていきましょう♪
川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)

10月11日(土)が、その1回目でした。
ことのはじまりは、島根県雲南市が2011年から開催している
地域プロデューサー養成講座『幸雲南塾』。
これが徐々に広がり、2014年度は全国8箇所で開催することに。
高松市も、その1箇所として開催することになりました。
ご応募いただいた塾生は、13人(12組)。
19歳の大学生から57歳の会社員の方まで。平均年齢が37歳。
約半数の方が、働く女性。
そういう皆さんと、これから半年間、自分なりのマイプランを考えていきます。

全国8箇所の塾をやっている尾野塾長(右)と、
地元側(小豆島在住)の眞鍋副塾長(左)
それにしても背景が荘厳。会場のご紹介は後ほど。

第1回のプレゼンターは、写真中央で椅子に座られている3人の方。
左から、地元「仏生山まちプランニングルーム」の“倉橋直嗣さん”と“片山哲也さん”、
そして、高知県室戸市から「(一社)うみ路」の“蜂谷潤さん”にお越しいただきました。
当日のお話、模様をご紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<仏生山まちプランニングルーム>
地元仏生山のプレゼンターは、カフェ経営などを行われている倉橋さんと、IT系の会社にお勤めの片山さんのお2人。
2013年9月、仏生山コミュニティ協議会が、住民から幅広いアイディアを出し合う場をつくった。
仏生山に愛着を持っている人、積極的に発言する人が多いなか、
アイディアを出し合うだけじゃなく、実際にやろう、
役場に頼るんじゃなく自分たちで実現しよう、ということに。
そこで、6人のスタッフによる「仏生山まちプランニングルーム」を立ち上げ、
内外の関心ある人を募って4回のワークショップ(WS)を開催し、
2014年8月に「高松市ゆめづくり推進事業」への応募原案を取りまとめた。
今後の展開として、例えば家具屋さんや大工さんなど町の人に協力いただいて、
みんなで町のベンチづくりをするというWSの企画を進めている。
これからも、楽しみながら町の課題解決をしていきたい。
ということを話されましたが、いきなり、質問が相次ぎます。
Q:立ち上げるの、かなり大変だったと思うんですが、どうやって集めたんですか?
A:カフェに来てた人に声をかけたり、来てくれた元気な人に個別に声をかけて。
Q:6人のスタッフはどんな方がいらっしゃるんですか?
A:金融機関の方、公務員の方、民間企業の方。(皆さん、聴講に来られてました)
Q:巻き込み方、WSのやり方とか、うまいですねぇ。
やってる時、意識してることがあれば教えてください。(by尾野さん)
A:自分が楽しむこと、みんなに楽しんでもらうことでしょうか。
連合自治会単位の活動が重要だと思うんですが、高松市が合併で大きくなり、小回りがききにくくなってるので、こういう活動が必要だと感じてるんです。
Q:そもそも、コミュニティ協議会とか、連合自治会とか、あまり知らないんですけど。
はい、東原次長、出番です。
聴講に来られて、後ろの方で聞かれていた「高松市役所の東原次長さん」へマイクが。

高松市 市民政策局 東原利則次長。予定にないご登壇です。
高松市のコミュニティ制度についてと、地域提案型の補助事業「ゆめづくり推進事業」について説明。

続けて、高松市市民活動センターの吉田センター長が、関連する助成制度を補足紹介すると、
思わぬところから反響が。
「これはスゴイ。小豆島では使えないですか」(小豆島を拠点とする眞鍋副塾長から)
~小豆島を含む高松広域都市圏を対象とする制度もあるそうです。
「高松に拠点がないと使えないんでしょうか」(立て続けに、高知県室戸市を拠点とするプレゼンター蜂谷さんからも 笑)
~こっちは、サスガに難しそう でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<一般社団法人 うみ路>

続いて、室戸市からお越しいただいた、蜂谷潤さん。
岡山市のご出身で、海が好き。海洋研究をやっていて地元に近い高知大学へ進学。
実際に、海に研究フィールドを持つ研究室に入ったら、
そのフィールドが室戸市で、海洋深層水を使ったアワビや海藻養殖の研究をやることになります。
室戸へ通って研究していた蜂谷さん、
考えていたアワビの研究をビジネスプランにまとめ、学生コンテストに応募したら、全国大会で文部科学大臣賞を受賞。
メディアに報道され、地元の人たちの目が、“室戸に来てるよく分かんない大学生”から“室戸のために頑張ってる子”に変わって、気づけば室戸へ移住。
移住後は、地元の人から具体的な課題が聞けるようになり、
大量に捕れるけど鮮度低下が早くて捨てている「ソウダガツオ(メジカ)」をなんとかできないか、と。
地元だけで考えていてもダメだと、室戸外から、料理人、デザイナー、若手社会人を呼んで、漁協の漁師さんと交流したり、
東京の飲食店で、料理してもらったりして、コンフィという調理法と出会い、
ホテルの厨房を借りて、地元のお母さんたちとメジカのコンフィをつくっているそうです。
使ってくれてる料理店へ行って、お客さんが食べてるのを見ると、お母さん、すごい喜んでくれる。
たいしたお金になってないんですけど、目指すところは、売り上げよりも<最大のHAPPY>。
そして、自分のエネルギーは<ワクワクし続ける>こと。
これに<必要とされる>ことが加わって、エネルギーが持続できてるんです。
「地域の課題解決」っていうと、重いじゃないですか。
答えを狙うんじゃなく、自然に生まれてくる<自分やみんなが“ワクワク”すること>をやっています。
と話してくれた蜂谷さん、ほかにも自然発生で、いろいろな事業が動きだしているそうです。
「アワビや海藻の事業化、メジカの利用、お母さんの出番づくりとか、いくつものマイプランのカタマリですね」と、尾野塾長のコメントです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、第1回の会場、高松藩松平家の菩提寺、「法然寺」の本堂をお借りしました。


この後、住職さんにもお話いただき、

後半は、2つのグループに分かれて、グループワーク。
各塾生がマイプランをプレゼンし、グループ毎にディスカッション。

そんな皆さんを見守る、本堂の「葵のご紋」の灯り。
そして交流会へ向かいます。

本堂を出てすぐの交流会場。コチラもお寺の施設をお借りしました。
眞鍋副塾長(右)、人見コーディネータ(左)、大人気。

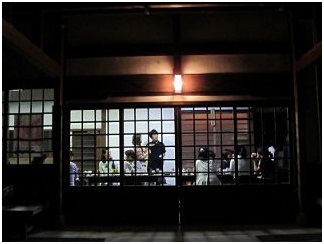
さて、次回(第2回)は11月15日(土)、
5W1Hを意識してマイプランを考えることになりました。
尾野塾長が、次回の案内の時に言われていましたが、
仏生山の皆さんも、室戸の蜂谷さんも同じようなことを言われたように思います。
「地域で何かする」のでなく、「話して反応した人と楽しくやる」(=輪が広がっていく)
でやっていきましょう♪
川井(サブ・コーディネータ、四国経済産業局)

2014年10月07日
スキルアップ特別講座~技を身につけ、みんなを笑顔に~
趣味や特技を活かしてボランティア!!
訪問ボランティアやイベント集客などに
人気のバルーンアートを取り入れよう!
今回は、クリスマス用バルーンなど季節に合った作品を作ります。

開催日時:平成26年11月7日(金)13:30~15:30
開催場所:高松市番町一丁目5-1 四番丁スクエア1F会議室
対 象:市民活動団体、市民活動に関心のある方など。
親子での参加も可
定 員:20名
参 加 費:材料代として300円
準 備 物:なし
申込締切:平成26年10月31日(金)




